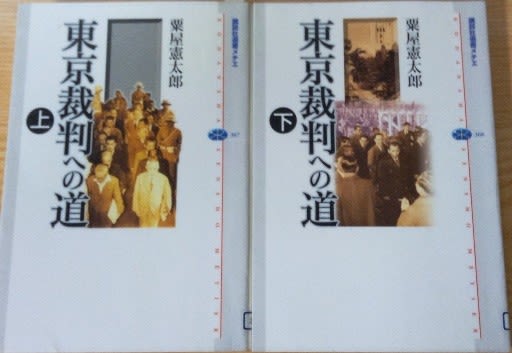粟屋憲太郎『東京裁判への道(上・下)』(講談社選書メチエ、2006年)を読んだ。その後、講談社学術文庫にも収載されたようで、そちらを読みたかったけれど図書館になかったので、講談社メチエ版を読んだ。
読んでからだいぶ時間が経ってしまったうえに、上巻はすでに図書館に返却してしまったので確認もできないけれど、メモを頼りに思い出しながら書いておくことにした・・・。
最初に、東京裁判と軽井沢との関係について。実は軽井沢はわずかながら東京裁判の舞台になっていた。
戦犯に指定されて自殺した近衛文麿の遺書などを捜すために、国際検察局(IPS)は軽井沢にあった近衛の別荘も家宅捜索した(上73頁)。
朝日新聞記者だった小坂徳三郎が、軽井沢で近衛を取材したこともあった(上79頁)。小坂は確か信越化学の創業者の一族で、後に自民党の国会議員になったが、軽井沢の旧中山道沿いに「小坂」という表札のかかった古くて広い別荘がある。以前この近くを歩いていたら、作家の堺屋太一がタクシーで乗りつけて、この別荘に入って行くのを見たことがあった。小坂徳三郎に連なる人物が住んでいるのではないだろうか。
親・近衛派の人物として鳩山一郎が登場するが(上92頁)、終戦の年、霧に覆われた旧軽井沢の別荘地で、特高の目を盗んで近衛、鳩山らの和平派が終戦工作を行っていたことを、御厨貴が新聞記事に書いていた(「新聞に現われた軽井沢」)。
今でも旧軽井沢には「近衛レーン」とか「鳩山通り」などと呼ばれる小道があるらしい。
内大臣の木戸幸一は、弟(東工大学長)が都留重人の岳父だったので(!)、都留のハーバード大学の同窓生を介してGHQに人脈があったという(上101頁)。
その筋から、天皇を無罪とするためには木戸内大臣が無罪となることが絶対条件だと言われ、木戸は日記を提出するなどIPSに協力したのだが、木戸日記は天皇に責任が及びうる記述が多かったため諸刃の剣であった(上112頁~)。IPSの木戸尋問調書は(木戸日記に比べて)詳細に木戸の証言を記録しているという(上121頁~)。
木戸は、長州閥でもあり、農商務省閥でもあった岸信介を擁護し、(長州閥に属した)東條首相の実現の原動力になった(上135頁)。IPS尋問調書によれば、木戸と天皇は「穏健な “火事場泥棒”」とサケット検事に皮肉られている(上140頁)。「火事場泥棒」は、木戸が伝えた天皇自身の使った言葉だそうだ。
木戸はあまり好ましい人物ではなかったようで(上98頁~)、田中隆吉に対する調書によれば、木戸は「日本のヒトラー」(宇垣一成の言葉)であり、「銀座の与太者」(同)と呼ばれていたという(上230頁~)。
木戸と田中は、IPS(国際検察局)の二大協力者だったが(上231頁)、笹川良一なども美談で語られてきたが、IPSの尋問調書によれば、実際には多くの容疑者を告発することでGHQ側に迎合していたことが分かるという(下144頁)。
昭和天皇の戦犯不指名、免責はかなり早い段階でマッカーサーが決意していたが、天皇の免責を目的として作成された『昭和天皇独白録』に関しては、その後、吉田裕がその英語版の存在を確認し、NHK取材班がボナ・フェラーズ文書の中から英語版を発見したが(上174頁)、実は英語版のほうが先に作られたという。寺崎英成が執筆したものと推測されている(上177頁)。
結局、東京裁判で、容疑者の訴追と免責を分けたのは、すでに顕在化しつつあった米ソ間の冷戦であり、アメリカ側はある時期から天皇と財閥を免責する方向に戦略を転換させ、これをキーナン検事も了承していたのだった(下115頁~)。
細菌戦の人体実験を行った石井四郎らの731部隊関係者や(下82頁~)、戦争挑発の先頭に立って宣伝費をばらまいた久原房之助、石原広一郎、中島知久平らは免責された(下118頁)。
松岡洋右の調書は自己弁護に終始しており(下160頁~)、「八紘一宇の名のもとに、多くの若い人が命を落としたことを考えたことはないのか」という検事の質問に対して、平然と「ありません」と答えている。真崎甚三郎の調書も卑屈で自己弁護的な証言で、「もっとも格調の低い調書の1つ」とされる(下135頁。真崎は二・二六事件の軍事裁判での態度も非難されている)。
敗戦前には「大和魂」などと叫んでいた戦争指導者たちが、時には上官、部下、時には同輩に責任をなすりつけ、あるいはアメリカ側に迎合して証言して恥じるところない、その余りにも情けない姿が尋問調書から浮かび上がってきて唖然とさせられる。
唯一の救いだったのは、広田弘毅の態度ではないか。政治は結果責任であるから、戦時中の行動、決断に広田が責任を負うべきは当然だが、免責されたり、釈放された連中に比べた場合に(絞首刑という判決は)不公平感はぬぐえない。城山三郎による刷り込みの影響だろうか。
弁護団の準備不足や、弁護方針の不一致、判事たちの間の不協和音などにも言及がある。
日本の戦争犯罪を糾弾するためにインド政府は、あえてインド人判事の枠を要求して獲得したにもかかわらず、なぜ最初から日本無罪論を主張したパール判事などを選任したのか。そのパール判事は合計109回も公判を欠席してホテルで日本無罪の判決書(少数意見)を書きつづけ、病気の妻を見舞うためにたびたびインドに帰国したという(下182頁)。公判を欠席して判決を書くなど、裁判官の風上にも置けない人間ではないか。
オーストラリア出身のウェッブ裁判長も、マッカーサーらの介入に嫌気してオーストラリアに帰国するなど、53回欠席したという(同頁)。こんな杜撰な裁判官たちによる裁判だったとは知らなかった。
「東京裁判史観」などと称して、東京裁判を批判する論者がいるが、本書の著者は、東京裁判は決して「勝者の裁き」などではなく、日米協調で裁きを免れた負の側面があるとして、朝鮮人強制連行問題、従軍慰安婦問題、毒ガス戦などの問題が戦後に残されたことを指摘する(下183頁)。
そして、著者らが発掘した国際検察局(IPS)の膨大な尋問調書を検討することによって、新たな「東京裁判史観」を確立させることが必要であると述べている。
本書の著者紹介欄を見ると、東京裁判の尋問調書は著者らによって翻訳(?)刊行されているらしいが(『国際検察局(IPS)尋問調書』全52巻!、日本図書センター)、とても読むことはできない。
本書では東京裁判の起訴段階までが対象とされており、開廷から判決までは今後の課題とされているが、その後、裁判から判決の過程を論じた著書は刊行されたのだろうか。
2022年8月22日 記