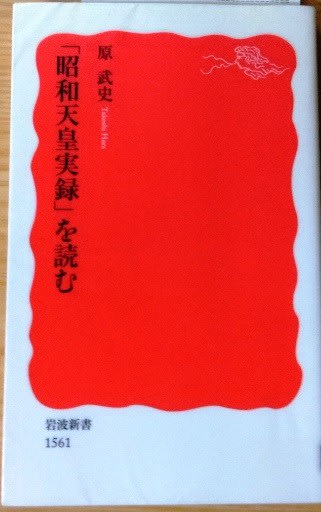原武史『「昭和天皇実録」を読む』(岩波新書、2015年)を読んだ。
『~~を読む』式の本は、対象の本を読まずに済ませることができる場合には便利な本である。
いい書評にもそのような効用がある。自分でヘタに読んで理解できないより、はるかに著者の言いたかったことを的確、簡潔に伝えてくれる書評というのがある。出版社に勤めていた頃、書評(とくに朝日新聞の書評)に取り上げられた本は売れないというジンクスがあった。朝日の書評が一般受けしない本を取り上げる傾向にあったせいもあろうが、書評が分かりやすかったので、読まないで済ませた「読者」が多かったからかもしれない。
さて、『昭和天皇実録』はとても全巻を読むことはできないし、読む気もない。唯一、私の知人が昭和天皇と会った日のことがどのように書かれているかを知りたくて、その該当日の巻だけを図書館で借りてきて確認した。
それでは、誰の解読書を読んで済ませるかだが、誰がよいだろうか。『実録』の解読書は何冊も出ているが、読み比べるほどのこともない。原は、『平成の終焉』(岩波新書)の読後感がよくなかったので迷ったが、他の解読書の執筆者にも違和感がある。消去法で原の本書が残った。
原によれば、天皇制は、天皇を真ん中(中段)にして、その上に「アマテラス」「皇祖皇宗」らの「天つ神」の領域があり、下に「臣民」「国民」が位置する構造になっている(8頁)。臣民らに対する天皇の意思は「勅語」や「お言葉」によって明らかになっているが、今回の『実録』によって祭祀における「御告文」や「御祭文」がはじめて公開され、天皇と「神」との関係が明らかになったという(同頁)。
しかし、「御告文」は、誰かお付きの漢学者あたりが書いているのではないかと私は思うのだが。
本書の特徴は、やはり昭和天皇と宗教との関係に焦点を当てた点だろう。しかも昭和天皇と皇祖皇宗との間に貞明皇太后の存在があったこと、しかも皇太后の天皇に対する影響力が大きかったことを本書ではじめて知った。
読む前には、あまりに宗教の側面に偏りすぎた解読ではないかと心配したのだが、全26巻だったかの『実録』を新書版1冊にまとめるには、どこかに視点を置くしかないだろう。そして本書はそれなりに成功していたと思う。本書は講演の記録らしく、会話体で書かれいる。そして「学術書」ではないからか、敬称略の「裕仁」は出てこなかった(と思う)。
昭和天皇が明治大帝に対するだけでなく、まさに「万世一系」の天皇家の祖先に対する信仰を抱いていたことがわかり、ポツダム宣言受諾に際して「国体の護持」にこだわって逡巡した心情も納得できた。愛人と心中死した娘婿をも悼んでいることには驚いた。
戦勝祈願の御告文の文面など祭祀に対して、実母である貞明皇太后が影響力を行使し介入するのを昭和天皇は嫌って、実母と会うことさえ避けるあたりは(88頁~)、どこの平民の家庭でも起きがちなことである。平民の家庭と違う点は、戦争末期にあって徹底抗戦を唱える貞明皇太后が昭和天皇に影響力を行使することによって、終戦が遅れてさらなる国民や相手国民の生命が奪われる危険があったことである。
天皇や側近たちは貞明皇太后の影響力を排除するために、皇太后を軽井沢に疎開させるのであった(144、153~6頁)。戦争末期の軽井沢には貞明皇太后までもが滞在していたのだ。たしか小学生だった正田美智子さんも戦争中に軽井沢に疎開していたから、皇室につらなる二人までが戦争中の軽井沢にいたことになる。
この天皇と神との関係も含めて、戦前、戦後を通じた昭和天皇の連続性が明らかになる。
昭和天皇が戦前戦後を通して政治、軍事に強い関心をもっていたことは他の本からも明らかだが、本書からは天皇が革命を恐れており、無産政党の動向に強い関心をもっていたことが明かされる(96頁ほか)。それも無産政党を弾圧するのではなく、一定の議席を確保させて毒抜き(という言葉は使っていないが)させたほうがよいのではないかなどと発言している。他方で、小選挙区制の導入によって「一流の人物が落選」する恐れがあるのではないかといった適切な危惧も示されている。
なお、戦後の左翼勢力に対しては183頁以下を(明仁皇太子に対して、わが国で共産主義が有力になることはないだろうと諭している)、また、朝鮮、台湾などの植民地への関心(無関心)については111頁以下などを参照。
昭和天皇は、自分が戦争責任を免責され、かつての臣下たちが東京裁判で断罪、処刑されたことから精神的葛藤があり(203頁)、戦後の一時期カトリックに関心をもち接近した時期があったという(188頁~)。天皇が改宗しても「国体」には変更はないのだという!(195頁)。
社会党の片山哲首相に好意をもち(186頁)、天皇退位を唱える南原繁の講話に関心をもったというのも(173頁)、彼らがキリスト教信者だったからであり、また、美智子妃に終始好意的だったというのも(247~8頁)、彼女が聖心の出身だったからだろうか。
本書で紹介される昭和天皇の日本国憲法への態度や(170頁~。「万世一系」の天皇制を維持する松本案を支持していた)、戦後の新憲法になってからも、たびたび内奏を要求して芦田均首相を困惑させるなどの行動からは、戦後の昭和天皇のもとで「象徴天皇制の定着」(本書第5講の見出し)があったとは思えない。象徴天皇制は明仁天皇の時代に定着したと私は思う。
戦争に対する「反省」をめぐる安倍首相の談話か、明仁天皇の「お言葉」か、「おまえの考えはどちらに近いかと問われれば、ためらうことなく天皇のほうだと答える」と原は言う(256頁)。
私もまさに同感である。この感情が、森達也をして「明仁天皇は何かを語りたいのではないか」と思わせ、そして『千代田区一番地のラビリンス』(現代書館)を書かせたのではないか。そしてこの感情は国民の多数(少なくとも安倍首相の支持者よりは多数)の感情ではないかと私は思う。
ただし原は、天皇の政治権限を一切否定した新憲法のもとで、天皇の「お言葉」に期待することをいましめる(同頁)。これもその通りだろう。
2022年8月11日 記