なぜ「事変」だと言い張ったのか
理由第一・アメリカからの物資輸入を断たせない
――日中戦争は、百万をこえる軍隊を海を渡って大陸に送った点でも、三七年七月から四五年八月まで八年以上にわたって続いた点でも、明治以来日本が経験してきた戦争のなかでもっとも大規模な戦争でした。ところが、日本政府は、戦争を開始した直後の時期に、この戦争は「戦争」と呼ばないで「事変」と呼ぶという方針を決め、そのことを最後まで言い張りましたね。その理由はどこにあったのですか。
不破 日本政府がこんな無理なことに固執した理由は、大きくいって、二つあった、と思います。
第一の理由は、アメリカからの物資の輸入を続けたい、という要求です。当時アメリカは、中立法という法律を持っていました。日本がほかの国と公然とした戦争を始めると、その条項が発動して、アメリカから戦略物資を買えなくなります。日本の戦争は、「英米依存戦争」という皮肉な言葉が生まれたほど、戦争に必要な物資の大きな部分をアメリカやイギリスから買いながらの戦争でした。それが断たれて、戦争の物資が輸入されなくなると困る、という経済的打算が、「事変」の名に固執した大きな理由だとされています。
理由第二・戦時国際法を投げすてた戦争
――それは、よく指摘される点ですね。もう一つの理由というのは…。
不破 第二の理由は、さらに大きな問題です。それは、「事変」と呼ぶことで、日本は、戦時国際法を投げ捨てた戦争をやった、ということです。
当時の世界では、戦争と平和に関する国際法は、まだ大きくおくれていましたが、戦時国際法――捕虜や一般市民にたいする人道的な対応など戦時の行動基準を定めた国際法規はかなり発達していました。日本も、それまでの戦争では、日清戦争や日露戦争でも、第一次世界大戦でドイツに宣戦した場合にも、天皇の「開戦の詔書」のなかで“国際法の範囲内で”行動することを明記し、戦時国際法をまもることを内外に約束しました。
ところが、日中戦争では、そういう約束はいっさいなされず、逆に、出動した軍隊には、“戦時国際法はまもる必要がない”という通達が出されていたのです。
部隊派遣のたびに通牒を出す
不破 実際、盧溝橋事件の約一カ月後、陸軍省から中国駐屯軍にたいして、陸軍次官名で一つの通牒=つうちょう=(三七〔昭和十二〕年八月五日付)が発せられました。それには、国際法の問題について、大要、次のようなことが書かれていました。
「現下の情勢では、帝国は中国にたいする全面戦争をしているわけではないから、戦時国際法の具体的な条項のことごとくを適用して行動することは必要ない」。
同じ「通牒」は、新しい部隊が中国に派遣されるたびに出された、と言います。
日本の軍隊は、こうして、最初から戦時国際法を投げ捨てた上で、中国にたいする戦争を始めたのでした。この戦争が、中国の人びとにたいして、特別に残虐な戦争となった原因の一つはここにある、と私は思います。
「南京事件」を考える
――戦時国際法といえば、南京大虐殺がまず問題になりますね。
不破 この事件に直接かかわることが、さきの「通牒」のなかにあるのですよ。「通牒」は、少し先のところで、“全面戦争でないのだから捕虜(俘虜)という言葉は使うな”と書いています。これで、日中戦争は、捕虜のない戦争、もっと正確にいえば、捕虜をつくってはならない戦争になってしまいました。
捕虜への人道的な取り扱いは、戦時国際法で定められたもっとも大事な内容の一つです。日露戦争のときには、日本も捕虜収容所を各地につくり、割合によい待遇をしたと言われています。ところが、日中戦争は、捕虜をつくってはならない戦争でした。だから、日本軍は、捕虜が出たらどうするか、その対応策をまったく持たないで、あの大戦争をやったのです。
いくら言葉の上で「捕虜のない戦争」と言ってみても、実際に戦争をやれば、多数の捕虜が出ます。しかし、日本軍は、捕虜のための収容所も用意していない、捕虜に与える食糧ももっていない、そうなると、捕虜が出たらとるべき対策は二つしかありません。釈放するか、殺すかです。日本が南京を攻め落とした時には、攻め込んだ日本軍の全体が、この問題に直面したのでした。
私は、『歴史教科書と日本の戦争』(二〇〇二年 小学館)という本を書いた時、『昭和戦争文学全集』(集英社)に収められていた歩兵第三十旅団長(佐々木到一中将)の戦場記録『南京攻略記』から、次の一節を引用しました。
「俘虜ぞくぞく投降し来り、数千に達す。激昂せる兵は上官の制止をきかばこそ、片はしより殺戮する。多数戦友の流血と十日間の辛惨をかえりみれば、兵隊ならずとも『皆やってしまえ』といいたくなる。
白米はもはや一粒もなく、城内にはあるだろうが、俘虜に食わせるものの持合せなんか我軍には無いはずだった」。
「敗残兵といえども、尚山間に潜伏して狙撃をつづけるものがいた。したがって抵抗するもの、従順の態度を失するものは、容赦なく即座に殺戮した」。
ここでは、殺戮が激高した兵士の自然発生的な行為だとされていますが、旅団長である筆者自身、戦時国際法を念頭においている形跡は、まったく見られません。そして佐々木中将の日記には、「我支隊のみで二万以上の敵を解決した」と記録されているとのことです(藤原彰『南京の日本軍』一九九七年 大月書店)。
大虐殺は起こるべくして起きた
不破 八月十三日に放映されたNHKの特集番組「日中戦争――なぜ戦争は拡大したのか」では、同じ南京攻略戦に参加した第九師団歩兵第七連隊(歩兵第六旅団の一部)の記録が紹介されました。その記録には「十二日間で六千六百七十人」を殺した、とありました。
また歩兵第百三旅団からなる山田支隊を率いていた山田栴二少将の日記には、「捕虜の仕末に困り、……学校に収容せし所、一四、七七七名を得たり、斯(か)く多くては殺すも生かすも困ったものなり」(十二月十四日)、南京からの指示は「皆殺せとのことなり 各隊食糧なく困却す」(十二月十五日)、「中佐を軍に派遣し、捕虜の仕末その他にて打合わせをなさしむ」(十二月十六日)、「捕虜の仕末にて隊は精一杯なり、江岸にこれを視察す」(十二月十八日)、「捕虜仕末の為出発延期、午前総出にて努力せしむ」(十二月十九日)など、なまなましい記述が連続しています(藤原彰『天皇の軍隊と日中戦争』二〇〇六年 大月書店)。
南京攻略戦には、まとまった部隊としては十個の旅団が参加していました。一つ一つの旅団あるいは連隊(二つの連隊で一旅団を構成)がこれだけの数の捕虜を「処理」しているのですから、虐殺の規模が莫大(ばくだい)な数にのぼることは、容易に推測できます。
日本の政府と軍部が、この戦争を、戦時国際法を投げすてた戦争として戦ったために、南京の大虐殺が起こるべくしておきたのです。同じ体制のもとで、同じような悲劇が、戦場となった中国の各地で無数にくりかえされたことは疑いありません。私たちは、日本人として、日本の戦争がこういう性格をもっていたことを、忘れるわけにはゆきません。(つづく)
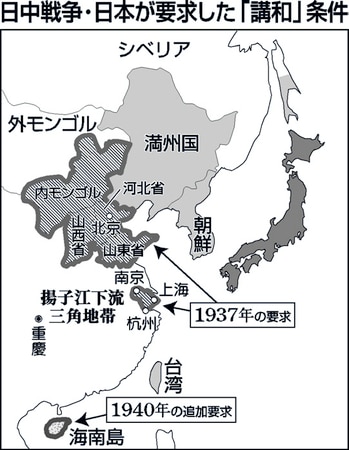 |
(次回は二十日付で「三国同盟と世界再分割の野望」を掲載する予定です)















