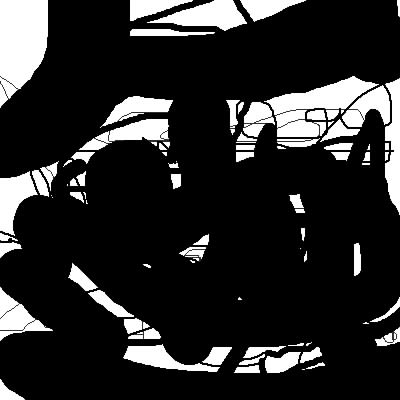
ジ ル
ウイズビー王子はジルと共に地下牢にいた。カルパコの裏切りはウイズビーにとっては意外な展開ではなかった。むしろ最初からカルパコの心根をそのように見ていたのだ。
カルパコは突然ウイズビーの前に現れ、刃物を向けて飛び掛かって来た。その姿は悪魔そのものだった。カルパコを許すわけには行かなかった。牢の中で首を切るつもりだったのだ。
しかし、パルマの説得にあってカルパコを解放した。それが間違いだったのだ。そう思うと、パルマの愚かさが見えて来た。パルマはカルパコを弟子だと言った。そしてこの作戦のためにカルパコが必要だと言って、無理やり奴を地下牢から出させたのだ。その責任は重い。ウイズビーは次期王としての考え方をした。
王たるものは常に国の中心になければならなかった。世界のすべては王の許しの元に存在していた。許すのが王であれば、罰するのもまた王しかいなかった。
捕らわれの身となって地下牢に座っていても、ウイズビーの思考は王道を歩んでいた。牢の中に捕らわれた何体もの骸骨の囚人の苦しみを目の当たりにして、ウイズビーは自分が王として、このもの達を救わねばならぬと思うのだった。
その思考の底には、かつての始祖セブ王の思考がそのまま流れていることに、ウイズビーは気づかなかった。しかしそこには、明らかに、死に瀕した砂漠の民をセブズーまで導いた始祖王の思考があったのだ。
ウイズビーは牢の中を歩き回り、囚人の話を聞いて回った。その横にはジルがまるで従者のように付いていた。
「王子様、これはあまりにもむごいですな。」ジルがウイズビーに言った。
二人の足元には背骨をへし折られた骸骨がうめいていた。その骸骨は、毎日体を折り畳まれて重い切石の下敷きにされる刑を受けていた。一度石を乗せられると、何時間もそのままにされて放置されるのだ。
「死にたい、死なせて下さい。王子様。」骸骨はうわ言のように何度も繰り返した。
「一体どういう訳でこんな目にあっているのだ。」王子が訊いた。
「私は恋人に花をプレゼントしようとしたのです。」
「プレゼントだと。」
「崖に咲くきれいな花でした。花を採ろうとして足を滑らせて崖から落ちてそのままこの国に来たのです。」
「それがどうして、毎日このような責めに会うのじゃ。」
「足を滑らせたのは恋人のせいだ。その恋人を憎めと言うのです。」
「そなたが死んだのは恋人のせいだ。そう思えと強要しているというのか、馬鹿げたことを。」
「私にはとてもそんなことは考えられません。」
「当然だろう。一体いつからそんな恐ろしい拷問を受けているのだ。」
「もう何十年も同じ繰り返しです。」
「何だって、」王子はことばを失った。
「こんな事があって良いはずはない。」ジルがうめいた。
「もうすぐ、私は石うすに引かれて粉にされてしまいます。これ以上心を変えられないと、処刑が決まったのです。」
「粉にされるとどうなるのだ。」
「永遠に、苦しみ続けます。死ぬことも生きることもできず、苦しみだけが永遠に続くのです。恋人を憎めないために、私は死ぬことも許されないのです。」
「死ねばまた新たな命の中に生まれ変われるというのに、それさえ出来ないとは、なんという恐ろしいことだ。この悪魔の仕業、許せない。」ジルが身を震わせて言った。
「名を何と申す。」王子が訊いた。
「セルザと申します。」
「しかと覚えておこう。恋人の名は何と申す。」
「ロゼッタと言いました。」
「奇遇じゃ。私の母君と同じ名とは。」
「もったいのうございます。サンパスという港町の商家の娘、身分が違い過ぎます。」
「セルザとロゼッタの恋物語り、しかとこの胸に刻み込んだぞ。」
「おお、何ということ、こんな地獄にも喜びがあったとは、王子様、これでたとえ粉々にされましても、私は幸せです。」
「何十年もひどい責め苦に合いながら、よくぞそなたの愛を貫き通した。その恋人に変わって礼を申すぞ。」
「ああ、王子様、」骸骨は忘れていた喜びの感情で体を震わし、眼窩の暗い穴から涙を流した。
そのとき牢の扉が開いて、骸骨兵が呼びかけた。
「セルザ、出ませ!」
「セルザはもう歩けぬ。」王子が骸骨兵に叫び返した。
「何だと、ではこちらに連れて来い。」
「だれもお前の言うことを聞くものはおらぬ。」
「おのれこしゃくな、大口をたたきやがって、痛い目に合わして欲しいのか。」
骸骨兵は数人で牢に入り、囚人を威圧しながら、セルザを鞭打った。無惨にもセルザの体はバラバラになってしまった。骸骨兵はその骨をかごに拾い集めた。かごの中で、頭蓋骨があごをカタカタ鳴らしていた。
「助けて」
骸骨兵はおかまいなしにセルザの骨を土ごとすくい上げてかごに入れ終わると、牢を出て行こうとした。
「待て!」ジルの大きな声が響いた。
「な、何だ、」
骸骨兵達はジルの大声にびっくりして立ち止まった。
「その骨を下に置け!」
「何だと、もう一度言ってみろ。」
骸骨兵が振り返った。
「その骨を下に置くんだ。」
「お前か、デブっちょ、よく言った。」
そう言って骸骨兵がムチをしならせ、ジルに向かって横払いに打った。ムチはジルを直撃した。しかしジルはムチを避けずに、自分の右手にムチを巻き付けた。そしてそのままからめ捕って、ムチを持っている骸骨兵を引き倒した。
大きな体に似合わず、ジルの動きは機敏だった。ジルは奪ったムチを使ってかごを持っている骸骨兵を攻撃した。ムチは骸骨兵の腕を打ち、かごが地面に落ちた。
「畜生!」
骸骨兵が捨てぜりふを吐いて牢から走り出た。そして錠を掛けた。その鉄格子からジルに向かって言った。
「覚えていろ。一生拷問にかけてやる。」
バラバラになったセルザの骸骨がかごからこぼれて地面に散乱していた。ジルはその骨を丁寧に拾い、一か所に集めて置いた。頭蓋骨がカタカタあごを鳴らして礼を言った。
「どうするつもりなのだ。」ウイズビー王子が訊いた。
「セルザを成仏させてやりましょう。」
「そんな事が出来るのか。」
「ごらん下さい。」
ジルはそう言うと、地面に集めたセルザの骨に向かって両手をかざした。するとジルの手のひらから白い光が発せられてセルザの骨を包んだ。骨が静かに振動しているように見えた。セルザの頭蓋骨が涙を流していた。
「ありがとうございます。」
セルザが喜びに震える声を上げると同時に骸骨は白い光の中でさらさらと白い粉になっていった。白い粉は地面に溶け込んで行き、やがてそこから一本の植物が芽を出した。緑のかわいい双葉がぐんぐん大きくなって、ついにその植物は美しい花を咲かせた。
「おお、素晴らしい。」王子が感嘆の声を上げた。
牢の囚人がジルとセルザの周りを取り囲んで合掌していた。
「ああ、あなたさまは神様ですね。」囚人達が口々にそう言ってジルを崇め頭を地につけ、そして手を合わせた。
「今ある苦しみに耐えなさい。悪に負けてはならぬ。やがて皆、解放されるだろう。私はジル。神ではないが、悪魔でもない。神と悪魔が一つになったとき、真の解放があるのだ。私はそのしもべだ。悪を憎んではならぬ。神を求めてはならぬ。ともに愛するのだ。よいか、そのとき必ずこの苦しみは消えよう。貴方達は最上の喜びを見いだすだろう。」
「おお、私達は救われるのですか。ジル様。」
「それはもしや、パルマの教えではありませんか。」完全に白骨化した囚人が跪いたままで胸に手を合わせてジルを見上げた。その白骨の肩の骨には、ほとんど擦り切れてしまった黄色いふだが貼り付いていた。
「いかにも、パルマの教えだ。パルマは今この国にやって来た。あなた達を解放するために。」
「おお、パルマ。」
囚人達は抱き合って喜んだ。目のない眼窩から涙があふれていた。
「我らの救い主、どうか私も花にして下さい。次の命をお与え下さい。」片腕のない骸骨がジルの足元に進み出て、その足に口づけをした。ジルはその骸骨の肩に優しく手を当てて言った。
「やがてあなた達は、あなた達のなるものになるだろう。それまで待ちなさい。セルザは花になった。セルザの心は癒されたが、しかし見なさい。ここでは花は育たない。残念だがまだその時期ではないのだ。」
白い光の中で美しく咲いた花は喜々として花びらを開いていた。しかし、ジルのかざした光が薄れると次第に力を失って、そのまま涸れてしまった。
「この花は、セルザが恋人に与えようとして採ろうとした、崖に咲く花かも知れぬな。」 王子が立ち枯れた花の前で両手を合わせた。囚人達も王子に従った。牢の中には喜びと期待と、そして悲しみの交錯した強いエネルギーが動き初めていた。
「どんな地獄でも苦難の中でも、同じ量の喜びがある。それを見いだすのだ。」ジルは囚人達を見て言った。
「ジル、お前は一体・・・・」何ものなのだという言葉を王子は飲み込んだ。今まで見たことのない引きしまった表情のジルだった。
その時、地下牢の外が騒然となった。槍を持った骸骨兵の集団が隊列を整えてやって来たのだ。地下通路は骸骨兵であふれかえった。骸骨兵は王子達の入れられている牢の前に隙間なく並び、槍を構えた。
「ジル、出ませい!騒ぐとためにならぬぞ。」
骸骨兵は牢の扉を開けた。
「ジル様。」囚人達は不安そうにジルを取り巻いた。
「心配しなくてもよい。すべては自然に任せるのだ。」
「出るのだ!ジル。」骸骨兵が苛立って叫んだ。
ジルは黙ってゆっくりと牢を出た。骸骨兵達は一瞬気圧されて後ずさりした。ジルが前に立つと、骸骨兵は槍をジルの首の前で交差させて威圧し、ロープで後ろ手に縛り上げた。
「ジル様、」囚人達が鉄格子に顔を押し付けてジルの名を呼んだ。
「今や救い主は現れた。解放は間近いぞ。」ジルは地下牢の隅々まで通る澄み切った声で皆に告げた。
「黙れ!」骸骨兵は槍の柄でジルの脇腹を殴りつけた。
「お前は直ちに処刑される。覚悟するんだな。」
骸骨兵はロープを乱暴に引っ張り、ジルを連れ出した。骸骨兵の半数がそこからいなくなった。
「ウイズビー、出ませい!」
今度は王子が呼び出された。
「王子様。」囚人達は驚きの声を上げた。
王子は抵抗する事なく牢から出た。骸骨兵は王子を土間に跪かせた。そこに骸骨の将軍ゲッペルが現れた。その後ろにカルパコが付き従っていた。
「ウイズビー王子、そなたは今宵、王家の儀式を受ける事になった。謹んでお受けするように。」
「何をばかなことを。私は次期王だぞ。」
「これを見よ。」
ゲッペルは始祖王の書いた儀式の書を王子の前に広げた。そこにはくさび型の文字が並んでいた。その中に一行、ウイズビー王と書かれた文字だけが読みとれた。
「ばかな、ランバード王国も終わりだな。」
「さあ、来ていただこう。儀式はわしが取り仕切る。それまで、そなたの世話はこのカルパコがする。よいな。」
「カルパコ、お前、悪魔に魂を売ったのか。愚か者め。」
「ギギギギ」カルパコの肩や頬に幾筋ものムチの跡が付いていた。その傷を隠すように、カルパコは顔を伏せた。
「儀式は厳粛に執り行われる。無駄な抵抗をしないで従うように、始祖王の名の下に申し付ける。」
「さあ、来て下さい。」カルパコが王子の横に付き、王子を誘導した、槍をもった骸骨兵が三体、槍の切っ先を王子の腰に突き付けて後に続いた。
骸骨が去った地下牢に闇のような静寂が訪れた。気が付くと、いつの間にか処刑場の石うすの音が消えていた。終日回り続けていた石うすが止められたのだ。両耳が圧迫されるような静けさだった。



























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます