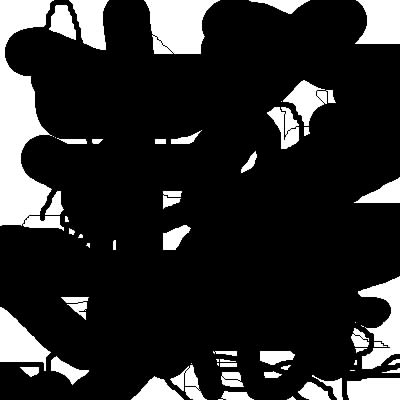
『その日』の十二日前から、王の食事はクルソンの樹皮と木の実、そして飲み物は水とコンク酒だけになる。そして一日二十時間、ヴォウヅンクロウゾの名を唱えながら祈り続けなければならないのだ。
しかし王宮で何が起こっているのか、知るものは誰もいない。その間の王の世話は王子が一人ですることになる。そうして十二日目の夜、王は八人の生娘の手によって体の隅々まで洗い清められる。儀式の間に、この時だけ、例外として娘達が王宮に入るのだ。そしてその八人の生娘達はその王の守人となる。
やがて身支度を整えた王は、王子に伴われて王宮の地下室に降りて行く。何段も階段を降りて行くと、通路が三本に別れて伸びている。その真ん中の通路を進むと両脇に地下牢がいくつも続く。そこをさらに進むと、広い地下の空間がある。その空間に石の祭壇が設けられている。
王がその石の祭壇に腰を据えると、王子から最後のコンク酒が与えられる。王はその最後のコンク酒を静かにのみ飲み干すと、王の千回声明が始められるのだ。
千回声明というのは、王がヴォウヅンクロウゾの名を千回、切れ目なく唱えることだ。その千回声明が始まると、王子は山刀を手に持ち、王の声明に照応して王の側に立ち、少しずつ、王の体にコンク酒を注いでゆく。王が唱え終わると、王子は山刀を振り下ろして王の首を切り落とすのだ。
王子は王の首をさらに高い祭壇に安置し、王を引き継ぐ証しとして、王子は千回声明を唱えなければならない。鮮血の臭いの中で、ヴォウヅンクロウゾの名を千回唱えるのだ。そして首のない王の体を地下牢に運び、牢の中の壁に取り付けられた手かせにつなぎ止める。王の体はそのまま手かせにつながれ、骨となっても地下牢の壁につながれたままとなるのだ。首の方は祭壇に置いてヴォウヅンクロウゾの貢ぎ物となる。王の首はいつの間にか地下牢から姿を消す。それはヴォウヅンクロウゾが王の首を食らうためだといい伝えられているのだ。
千回声明が終わると、王子は地下室を出る。そしてその翌日には、空の柩に石を入れて王の死を告げるのだ。王の葬儀が国中の民の悲しみとともに執り行われ、空の柩は花で埋められる。やがて八人の守人と共に石の入った棺が永遠に埋葬される。こうして王家の秘密は何百年も続いて来たのだ。
王子は淡々とした口調で語り終えた。感情を交えると、とても話し通すことの出来ないような残酷な話だった。
「むごい事じゃ。」
「何て恐ろしいこと。」
「信じられない。その八人の女の人も可哀想だわ、殺されるんでしょう。」
「地下牢で見た、白骨、あれが王の、」カルパコが声を詰まらせた。
「見たのか。」
「牢の中に手を吊るされた白骨がありました。」
「我らが殺めたのだ。墓に入れられもせず王は朽ちるまであのままだ。愚かなことだ。」 王子の目に涙が光った。
「しかしなぜ、屍を鎖でつなぐ必要があるのでしょう。」ジルが小さな声で言った。
「それがしきたりなのだ。」
「王子、よく話してくれた。これで相手がはっきりと見えた。」パルマが言った。
「それにしても、気の毒にのう。我らの手で、必ず先王達の亡きがらを葬ってやろうではないか。のう王子、それにゲッペルよ。」パルガが二人を交互に見て言った。
「無論望む所だ。しかし、パルマ、相手が見えたとは、それを話してはくれぬか。ヴォウヅンクロウゾとは何ものなのだ。」
「ヴォウヅンクロウゾとは悪魔の成れの果てなのだ。」
「成れの果てだと。」王子は息を呑んだ。
「世界は光と闇とでできておる。そして、悪魔は闇の意志なのだ。その意志が世界を支配しようと動き出した。本来一つに結び合っていた世界が二つに分かたれた。それが不幸の始まりだったのだ。」
「二つに、生の国と黄泉の国もまたそうなのか。」
「そういう事じゃ。」
「して、成れの果てとはどういう意味なのだ。」
「悪魔は意志だが、その意志を実行するための実体はなかった。そのために悪魔は自らをヴォウヅンクロウゾと名付け、始祖セブと契約を結んで王の体に入ることで実体を得ようとしたのだ。」
「その契約のために、王家が翻弄されて来たというのだな。」
「そういう事だの。そしておそらく、王子の考えは正しいだろう。」
「考えというと。」
「契約が逆にヴォウヅンクロウゾの足かせとなったのだ。ヴォウヅンクロウゾはセブ王のからだから離れる事が出来なくなったという意味でな。しかし王の体は無限ではない、いつかは朽ちてなくなってしまうだろう。ヴォウヅンクロウゾもそれと共に滅びるしかないのだ。そのために王家の儀式が必要になったという訳だろう。」
「すると、儀式の後、王の遺体を鎖でつなぐのは、」
「黄泉の国の王は始祖セブ王でなければならぬからだろうよ。始祖王以外の王を黄泉の国に入れないためにそうするのだろう。」
「それに、新しい王の力を吸い上げるためもあろうの。」パルガが付け足した。
「そうだな、いずれにしても、王家の儀式は、始祖王の体に新たなエネルギーを与えるために必要なのだ。それがなければ、王の体は朽ち果て、ヴォウヅンクロウゾも居場所を失うのだ。」
「そうなる前に、世界を完全に自分のものにしようとたくらんでいるのじゃ。最近の動きから見ると、ヴォウヅンクロウゾは焦っているように見える。始祖王の体が朽ち果てようとしているのかも知れぬ。」パルガが言った。
「儀式を断った王子の決心はよかった。ヴォウヅンクロウゾには大きな打撃なのだ。」
「そうだったのか、お陰で確信が持てるようだ。礼を言う、パルマそれにパルガ。」
「ところで王は今どうしておるのじゃ。」
「最初は激怒して興奮していたが、次第に落ち着いて来た。それから儀式について何度か話し合ったが、王はこのことを理解しようとはしない。その代わり夜ごとの苦しみがひどくなっていくようだ。」
「そうか。」
「つい先日、王は儀式の日を宣告した。」
「なに、それはいつじゃ。」
「次の満月の夜にと。この月の半ばには儀式を始めねばならぬ。私があくまでそれを受け入れなければ、王子を廃すると言った。次期王に代わりの者を立てるつもりらしい。断れば私は反逆の罪人として処刑されるだろう。」
「王様も追い詰められているのだな。」バックルパーが唸った。
「王は苦しんでいる。」
「ヴォウヅンクロウゾが王を苦しめておるのじゃ。」
「姉様、わしが王の部屋に結界を張りましょうぞ。」
「そうだな、それがよいだろう。王もまた救わねばならぬ。」
「王を救ってくれるのか。」ウイズビー王子は身を乗り出して訊いた。
「当然の事じゃ、我らとともに黄泉の国に行ってくれるかの。」
「無論だ、いかほどの軍を出せばいいのだ。王軍は五千を数えるが、しかし今すぐと言われると場内の二百が限度だ。」王子が言った。
「いや、そのような戦いではない。軍は必要ないのだ王子。」
「では何を、」



























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます