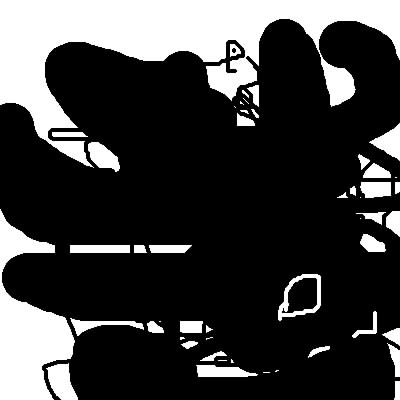
女牢一
エミーは骸骨兵に抱きかかえられて地下牢の一番奥に運ばれた。間近に巨大な石うすが見えた。ズズズズ、ズズズズ、ズズズズ、石うすの回る音が体の底に響くように聞こえて来た。太い丸太に両手を添えて押し続け、石うすを回している囚人達は、白骨になっているものは少なく、この国ではまだ若い囚人達だった。中には胸に黄色いふだを貼り付けている囚人も見えた。石うすの上には骸骨兵が立っていて、上から容赦なくムチを振り下ろしている。その度に囚人の腐りかけた肉が破れ、肉片が飛び散った。ムチを当てられた背中に、細長い溝が幾筋も出来て痛々しい傷を負った囚人がうめきながら地面に崩れ落ちた。石うすを回す囚人達はそれでも足を止める事を許されなかった。倒れた囚人は自分で起き上がらない限り、そのままたくさんの囚人の足で踏みつぶされた。
「なんていうこと、これではあまりにひどすぎる。」
エミーはそんな光景を目の当たりにして、恐ろしさと同時に深い悲しみに襲われた。そして思わず涙を流した。
「さあ、来るんだ。」骸骨兵がエミーを引っ張ってエミーを女牢に連れて行った。
女牢は、石うすの処刑場を横切った所に設けられていた。石うすから出る白い粉が舞い上がって、乾燥した空気の中で限りなくもやっていた。そのもやがドロリとしたオレンジの光を吸収して窒息するような息苦しさを感じさせていた。その奥に大きな地下牢があって、そこにエミーは入れられたのだ。女ばかりを集めた女牢だった。
ズズズズ、ズズズズ、ズズズズ、ズズズズ、絶えず石うすの低い響きが牢の中を気味悪く振動させていた。
エミーは複雑な心の動揺のままに、何をしていいのかも分からず、牢の入り口に座り込んでしまった。カルパコの事が頭を離れなかったのだ。
一体どうしてあんなことをしたのか、エミーには信じられなかった。あれはまるで別人のカルパコだった。カルパコが魔物の味方をして王子の首にナイフを突き付けるなんて、どう考えても理解出来なかった。
カルパコとは幼いころからの友達だった。何でも相談したし、エミーもまた、カルパコの事なら何でも知っていると思っていた。愛という感情がエミーの心に育って来た今、エミーは抵抗なくカルパコの愛を受け入れ、自分もまたカルパコへの愛の中にいると信じていたのだ。
カルパコの事は何でも知っているはずだった。それにエミーは突然起こって来た様々な事件に巻き込まれて、想像さえ出来ない体験を繰り返して来た。そのためにエミーの心は随分大人びて見えた。
しかし、実際の所、まだ子供だったのだ。子供のエミーにはまだカルパコの本当の心が見えていなかった。カルパコの変心の深いところに何があったのか、それが見えないエミーは何度も心の中でカルパコに問い続けた。
『どうしてあんなばかなことをしたの。』
『どうして悪魔に心を売ってしまったの。』
エミーは悲しみに耐え切れずにそのまま泣き崩れた。
「いつまでも泣いていないで、こちらに来なさい。」
優しくも弱々しい声がエミーの上から聞こえた。エミーが見上げると、骸骨が跪いてエミーを見下ろしていた。
「何をしてここに連れて来られたのかは知らないけれど、いつまでもこんな所にいたら、兵隊達の目について、拷問室に連れて行かれるよ。」
「拷問室?」エミーは深く考えられないままオウム返しに訊いた。
「さっ、こちらに来なさい。目立ってはだめなのよ。」
エミーは骸骨の言うままに従って、牢の奥の方に歩いて行った。思った以上にそこは広かった。入り口は二張りの鉄格子がはめられた牢だったが、その奥は広い洞窟になっていたのだ。その洞窟の隅の奥まった所に何体もの骸骨がひしめいて座っていた。中には恐ろしい形相で、目を背けたくなるような醜い囚人もいたが、今のエミーにはそんな外見に惑わされるようなゆとりはなかった。エミーの目には、自分に向けられた救いと優しさだけが映っていた。名も知らぬ骸骨にエミーは心から礼を言った。その骸骨の胸の骨には黄色いふだが貼られていた。
「その黄色いふだは?」エミーが小さな声で訊いた。
「これ?そうね、これは私の勲章よ。」
「あなたはもしかして、パルマを知っているのですか。」
「あなたもパルマを?」
「私エミーと言います。これを見て下さい。」エミーはそう言ってから、パルマにもらった黄色いふだを取り出した。
「あなたも、『黄色いふだ』の仲間だったのね。私はモリスというのよ。ここに捕まって二年は経つわ。もっとも、正確には分からないけど。もしかするとエミー、あなたテリーを知ってるのではない?」
エミーは黙って首を横に振った。
「そう、残念だわ。」モリスは淋しそうにうなずいた。
「ねえモリス、あの石うすは囚人を処刑する所だって本当なの?」
「そうよ。」
「あまりにもひどすぎるわ。」
「それがセブ王のやり方なの。」
「信じられないわ。」
「それより、あの石うすですりつぶされた粉はその囚人の苦痛と悲しみ、それに怒りそのものなのよ。セブ王は私達から憎しみだけを取り出そうとしているの。そしてその粉を生の国にばらまいているのよ。恐ろしいことだわ。」
「生の国に?」
「そう、あの憎しみの粉は生の国の空気を少しずつ汚しているのよ。汚れた空気を吸った木は枯れていくの。鳥は歌を忘れ、人はいわれのない怒りを心に生み出すのよ。」
「でもどうしてそんなことを?」
「セブ王は生の国を死の国に変えようとしているのよ。」
「そんな、」エミーは次のことばが出なかった。
「私達はパルマの教えに従って、それを止めようと戦っているの。でも力がなくて、このままでは皆牢につながれるかも知れない。セブ王は大きすぎるわ。」モリスが力なく言った。
「パルマは私達と一緒に今この国に来ています。」
「それは本当なの。」モリスは一瞬目を輝かせた。
「ええ、セブ王に取り付いている魔物を封印するために。」
「いよいよ動き出したのね。」そう言って、モリスは目を閉じた。その目から一条の涙がつたい落ちた。
それを見てエミーは言葉を失った。
「長い苦しみだったわ。でももう少しの辛抱だわね。パルマが来てくれたんだもの。」
モリスは手を合わせて神に祈りを捧げた。エミーは洞窟の壁に背を預けてゆっくり目を瞑った。疲れが溜まっていたのだろう、エミーはそのまま深い眠りについた。
次を読む



























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます