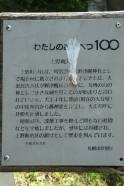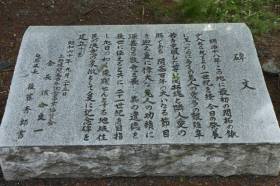アルテピアッツァ美唄(美唄)前編 撮影日 2010.6.12(土) [HomePage][Yahoo!地図]

・こちらは美唄の山間部のかつての学校跡地を、安田侃氏の作品を展示する彫刻公園として改装した施設です。こちらでの演奏会の合間にカメラ片手に園内を散歩。当日はとても良い天気の散歩日和でした。


・こちらは坂の上の広場。新たな彫刻作品が設置されるとかで、重機用の道がついていました。



・『真無(MAMU)』 ホームページに現時点で記載されていないところをみると、これが新しい彫刻でしょうか。


・笹の生い茂る斜面の上にもニョッキリと彫刻が頭を覗かせています。また斜面下の笹の中にも彫刻を発見。


・『天秘(TENPI)』 こんなところにも彫刻があったとは初めて気がつきました。まるで碁石のような質感。


・彫刻の上には、何やら草のお供え物が。


・『妙夢(MYOMU)』


・札幌駅ビルの構内にも同じ形の彫刻がありますが、それを倒して展示しただけで全く別の作品に見えてくるから不思議です。



・周囲をひと回りし、あれこれ撮影。



・初夏でも真っ赤な葉の紅葉と『意心帰(ISHINKI)』。


・次に場所を移して旧校舎内のギャラリーへ。廊下の真ん中に佇むのは『めばえ(MEBAE)』。


・教室内に点在するオブジェ。手前より『相響(SOKYO)』、『妙夢(MYOMU)』、『風(KAZE)』。


・床に近い視点より。


・『妙夢(MYOMU)』


・じっと見ていると何かの機械の部品のようにも見えてきます。


・『風(KAZE)』
(後編に続く)
[Canon EOS 50D + EF-S17-55IS, EF-S10-22]

・こちらは美唄の山間部のかつての学校跡地を、安田侃氏の作品を展示する彫刻公園として改装した施設です。こちらでの演奏会の合間にカメラ片手に園内を散歩。当日はとても良い天気の散歩日和でした。


・こちらは坂の上の広場。新たな彫刻作品が設置されるとかで、重機用の道がついていました。



・『真無(MAMU)』 ホームページに現時点で記載されていないところをみると、これが新しい彫刻でしょうか。


・笹の生い茂る斜面の上にもニョッキリと彫刻が頭を覗かせています。また斜面下の笹の中にも彫刻を発見。


・『天秘(TENPI)』 こんなところにも彫刻があったとは初めて気がつきました。まるで碁石のような質感。


・彫刻の上には、何やら草のお供え物が。


・『妙夢(MYOMU)』


・札幌駅ビルの構内にも同じ形の彫刻がありますが、それを倒して展示しただけで全く別の作品に見えてくるから不思議です。



・周囲をひと回りし、あれこれ撮影。



・初夏でも真っ赤な葉の紅葉と『意心帰(ISHINKI)』。


・次に場所を移して旧校舎内のギャラリーへ。廊下の真ん中に佇むのは『めばえ(MEBAE)』。


・教室内に点在するオブジェ。手前より『相響(SOKYO)』、『妙夢(MYOMU)』、『風(KAZE)』。


・床に近い視点より。


・『妙夢(MYOMU)』


・じっと見ていると何かの機械の部品のようにも見えてきます。


・『風(KAZE)』
(後編に続く)
[Canon EOS 50D + EF-S17-55IS, EF-S10-22]