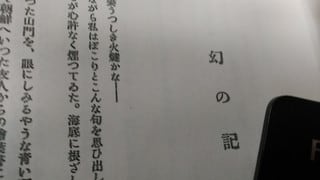
沖崎猷之介「幻の記」(『コギト』6)は、悲痛な名調子の短篇である。「腰抜けの妻うつくしき火燵かな――」という蕪村の句が、右のように「――」という記号に接続されてライトモチーフのようにあらわれては消える。これは、語り手「私」の愛した文学であり、もしかしたら日本の文化を背負っているのかもしれない。というのは、語り手は「幻」?のなかで、朝鮮の梵魚寺を訪ねてその美しさと何かに酔っているからである。梵魚寺は「――」という記号に導かれてあらわれるのであるが、それは、「階級――」とか、「――とうとうやられた――」(ある混血の芸術家が逮捕された場面に遭遇したとき)、「――現実」とか「――空腹」といった変奏をしながら蕪村の句を次々思い出す私を覚醒させ続けている。――そういうミニマルミュージックのような趣であるが、芭蕉と自分の自分の年齢を比べてああだこうだと考えていた脳裏に、次の詩句が、突然飛び込んでくる。
Dans ton île, ô Venus! je n'ai trouvé debout
Qu'un gibet symbolique où pendait mon image ...
これは作中には書いてないが、ボードレールの「シテールへの旅」の最後の連の一節である。清水まさ志氏の論文中(「ボードレールの詩篇「シテールへの旅」を読む」)の訳を掲げれば、次のようである。
お前の島で、ああヴィーナスよ! 私が立っているのを見出したのは
私の像が吊るされている象徴的な絞首台だけ・・・
私は、レールのそばに死体を見出したりしながら、自分はすでに死んでるのではないかと思ったりする。
時を殺すこと、思へば性懲りもなく、私は時計の鍵をいぢりまわして来たものだ。[…]私は力が欲しい。生きたものがほしい。私をどやしつけて動かすものが欲しい。
腰抜けの妻うつくしき火燵かな
ああ、美しきと言い切った蕪村、所謂二十何年間の生涯は私からなくなった。人間は一生に一度しか死ぬなんてことは嘘っぱちだ。ただ墓碑銘なんてものはないだけだ。私の経歴のなくなる日、――私は碑文を書くかはりに私の日記を引き裂こう。
こういった「私」殺害をくわだて生まれ変わった人々は昔も今もいる。上でも「――」がなくなった蕪村の句は蕪村の句にすぎなくなり、私は「時を殺すこと」によってのみ成り立つ文学への陶酔を断ち切り、ある種の「自立」を遂げたように見える。しかし、この自立は幻想である。ブキッシュな幻想からの自立は、むしろ葛藤からの逃避であり、現実という幻想への逃避である。この短篇で問題になっている朝鮮やヨーロッパとの関係からの逃避でもある。
結局、沖崎(中島栄次郎)は、三十六才で戦死した。
追記)
東浩紀の「テーマパークと慰霊」(『ゲンロンβ33』)における、大連のテーマパークというのは、上でいえば、可視化され実体化された幻想みたいなものである。確かに、慰霊碑やテーマパークは、上のような極端な行動や幻想を押しとどめる、地縛霊みたいなものなのであろう。ただ、地縛霊に可塑性があるのかという問題があるような気がするのである……。東浩紀氏は、それゆえ、ちょっと地縛霊をみて帰ってくるという観光客であり続けようとしている。かかるあり方が許される限り、われわれは自由である。中島にはなかったのだ。









