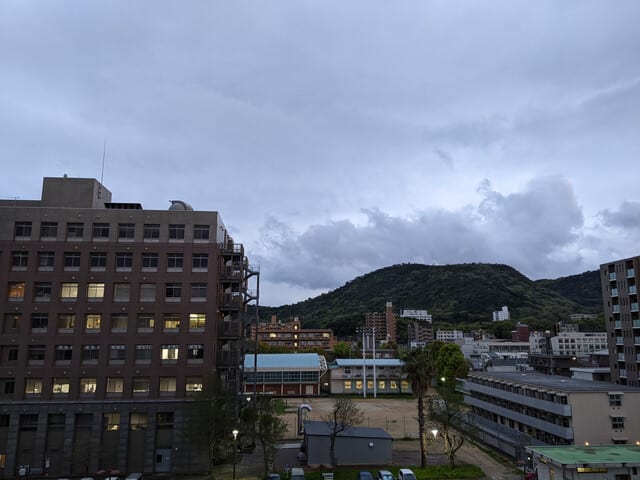
子曰、君子欲訥於言、而敏於行。
源氏物語で、光源氏が息子に「漢学をしないと大和心をつかえるようになりまへんで」と言ったのは、そもそも論語なんかに上のように「君子とは、口べたであっても行いが素晴らしい人といきたいもんだねえ」とか言っていたからでもあろう。光源氏の住んでいたのは日本であって、これはしかたのない条件であり、この条件から生じるよいこととは行いの良さである――言語的文化では中国にかなわない――からして、中国の言語(教え)の力を借りて、行いの美質の正当性を得る、と。こんな気分であったかもしれない。
たしかに、我々は言語の使用に於いて迫力を持つことが難しく、むしろ言語に頼るとひたすら堕落し、空気を読むみたいな俊敏さに基づく行動において美点を発揮出来るのではないかと思うこともある。――それほど言行不一致のやからが目につくということだ。言行不一致の当事者でさえそう思っているのだから深刻だ。
さっきテレビで先日なくなったムツゴロウ氏の追悼番組をやってて、むかしの映像がいくつか流れていて、アナコンダに締め付けられて殺されかけている氏の映像が晩ご飯の時間帯に流れていた。そういえば、これが昭和の雰囲気であった。普段何事も経験が大事とかいいたいひとは、ムツゴロウ氏のように(テレビだからなんともいえないが)アナコンダに絞め殺されかけてから言うべきで、とにかく、正論ぽい事を言えばいいみたいな風潮ほんと駄目ですね。
今日、ある新書を読みはじめて、あこれは「月刊Hanada」の文体だと思ってしらべてみたら初出がほんとにそうだった。もう研究はあると思うが、こういうのってわりとわかるよな。例の人工知能にもあるかもしれん。あればわかると思う。――いや、本当は、まだ「ハナダ」はある種の色を持っているからあれなんだが、我々の文体が行動に裏付けられず文体を失っているのは確かだと思う。ほんとは、文体が行動された行動の情報と相俟って、そういう文体にみえるのだと言う人もいるだろう。そうかもしれないが、そういう分析は、現実に即してもいなければ文章に即してもいない、ゲスの勘ぐりを唯物論みたいに言っているだけではないか。――もっとも、うえの書物もそうであったが、調査不足なのか視野が狭いのか、とにかく結果的に嘘を書いている其の勢いみたいなものが文体を形成していて、こういう文体は単に学校や大学で添削すればあえるていど防ぐことが出来る。









