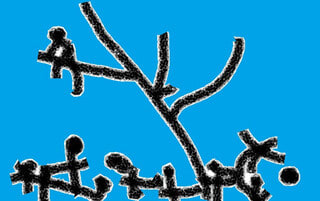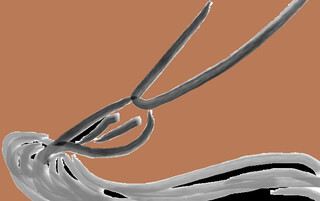大事を思ひたたん人は、去りがたく、心にかからん事の本意を遂げずして、さながら捨つべきなり。「しばし、この事はてて」、「同じくはかの事沙汰しおきて」、「しかしかの事、人の嘲りやあらん、行末難なくしたためまうけて」、「年来もあればこそあれ、その事待たん、ほどあらじ。もの騒がしからぬやうに」など思はんには、えさらぬ事のみいとどかさなりて、事の尽くるかぎりもなく、思ひ立つ日もあるべからず。おほやう、人を見るに、少し心あるきはは、皆このあらましにてぞ一期は過ぐめる。近き火などに逃ぐる人は、「しばし」とや言ふ。身を助けんとすれば、恥をも 顧みず、財をも捨てて遁れ去るぞかし。命は人を待つものかは。無常の来る事は、水火の攻むるよりも速かに、遁れがたきものを、その時、老いたる親、いときなき子、君の恩、人の情、捨てがたしとて捨てざらんや。
こんまり氏の「ときめかなかったら即捨てよ」という主旨の本があるらしい。わたくしはまだ読んでない。(いや、読んだかもしれない)寺山修司のように「書を捨てよ街へ出よう」の現代バージョンと言ってよい。しかし、この断捨離というやつでわたくしが最初に想起したのは、上記の徒然草の第五十九で、求道者はさっさといろいろ捨てましょう、死はいつ来るか分からないぞ、早くしなきゃ、みたいな文章である。
仄聞したところによると、こんまり氏は本やコピーも同様だ、と言っているらしいんだが、学者はこの論旨に勿論反発する人が多いらしい。徒然草を読むと、書物に埋もれて研究計画ばかり考えているのは、我々が求道者として思いきっていないからかもしれないとも思うのであった。しかし、われわれはいろいろ捨てて書庫に籠もったのだ。
しかし、果たして、徒然草の作者は、その断固決断してどうなったんであろうか?結構、捨てるべき世間と離れないエッセイを書いたのではないだろうか。
幼い頃、「無常の風が吹いて来ると人が死ぬ」と母は云つた。それから私は風が吹く度に無常の風ではないかと恐れ出した。私の家からは葬式が長い間出なかつた。それに、近頃になつて無常の風が私の家の中を吹き始めた。先づ、父が吹かれて死んだ。すると、母が死んだ。私は字が読める頃になると「無常」の風とは「無情」の風にちがひないと思ひ出した。所が「無情」は「無常」だと分ると、無常とは梵語で輪廻の意味だと云ふことも知り始めた。すればいづれ仏教の迷信的な説話にすぎないと高を括つて納まり出したのもその頃だ。その平安な期間が十年も続いて来た。もう私は無常の風が梵語であらうがなからうが全く恐くはなくなつてゐた。
――横光利一「無常の風」
我々は横光利一よりあとの人間だ。内面に無常の風を吹かしている後の人間である。これ以前に帰っても仕方がない。むろん、「無常」自体が、「死」を軽量化するトリックだった側面があるから、内面に場所をうつしても耐えられたのだ。いまは起こっているのは、内面化でも死の軽視でもない。