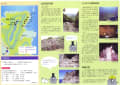白嶽の還り、タクシーで厳原まで行ってもらいながらタクシーの運転手から教わったことなど順不同でいくつか。
・最近は山でも猪が多くなり、時々人に被害が出る。→これは入山前に教えて欲しかった。
・韓国の人は山登りが好きで20名くらいのもの団体でこの白嶽にもよく来る。
・対馬には蘭が自生しているが、残念ながら自衛隊が演習で踏みにじり射撃でダメにしてしまう。
・韓国人の登山者も蘭を持ち帰ってしまう人が多い。日本人の登山者にも悪いのがいることは確かだが‥。
・対馬の人はお墓を立派なのに仕立てる。石も立派なものを建てるし、石に刻んだ文字も金箔で飾り立てる。
・上対馬(北部)は山が多少なだらかなので上対馬にも足を運んで欲しい。
・対馬は山が深く、水が豊かなので水不足ということはまずまい。
・厳原の川沿いにはスナック等が120件もひしめいている。厳原町15,000人に比して多すぎる数といわれる。客は漁師中心といわれ、観光客はあまり利用しない。漁師の気風といわれる。


さて昨日記載忘れしたのが、「半井桃水」についての大納言様からの質問。対馬についたその日に半井桃水の旧居に寄ったのを忘れていた。大納言様のその日の質問に「桃水は樋口一葉のことをどう思っていたのか」というのがあった。この山登りの翌日、対馬最後の日に旧居を再度訪れたが休館日で詳しくは調べられなかった。私の記憶の範囲で展示内容を書いてみる。


まず、桃水は一葉の才能を見出したものの想定以上であったことを後日語っていたらしい。また一葉の死後、一葉の思いが桃水にあったことを日記の公開で知ったらしいが、そのことについては論評は控えたらしい。
桃水自身は妻を早くに亡くしたらしいが、当時の男としては珍しく24年間再婚はせずにいたらしい。最初の妻の死後24年後に再婚したが、出来た子は若くして亡くなったようだ。
桃水がどのように一葉のことを考えていたかはわからなかったものの、人に口外するような軽薄な男ではなかったと思われる。




そしてもうひとつ私が書きたいのは雨森(あめのもり)芳洲とその「誠信の交わり」について。
1990年、盧泰愚(ノテウ)大統領は、「...二百七十年前、朝鮮との外交にたずさわった雨森芳洲は、<誠意と信義の交際>を信条としたと伝えられます。彼の相手役であった朝鮮の玄徳潤は、東莱に誠信堂を建てて日本の使節をもてなしました...」と述べ、日本では忘れられていた雨森芳洲が俄然脚光を浴びた。
芳洲を顕彰する「雨森芳洲庵」が、1984年生地の高月町雨森に建設された。当時の滋賀県知事だった武村正義は、この事業を積極的に推進したようだ。
略歴は、1668年(寛文8)~1755年(宝暦5)、対馬藩に仕えて李氏朝鮮との通好実務にも携わった。木下順庵の推薦で、当時、中継貿易で潤沢な財力をもつ対馬藩に仕官。対馬藩朝鮮方佐役として藩政に関する上申書『治要管見』や朝鮮外交心得『交隣提醒』を書いている。思想的には自身が日本人である事を悔やみ「中華の人間として生れたかった」と漏らした記録が後世に伝わる。朝鮮語通詞養成所を対馬府中に創設。明治期まで多くの名通詞を輩出させるこの学校では,当時軽視されていたハングルで書かれた小説を教材に用いるなど、芳洲独自の教育理念・方法が貫かれていた。
盧泰愚大統領の言葉は芳洲のその内容はこの交隣提醒によっていて「朝鮮の風俗・習慣をよく理解し、違いを尊重して外交に当たるべきことを事例を挙げて説き、偏見や蔑視を抱いてはならないと強く主張している。また『誠信の交わり』については、互いに欺かず、争わず、真実をもって交わることこそ、まことの誠信である」との内容を踏まえている。
列島に人間が住み着いて以来、半島と列島の間で人の交流が続いてきた。歴史家にいわせると戦い・争いも交流の一環ということだが、歴史の節目節目にはとてつもない戦いが行われる。白村江・元寇・秀吉の侵略・明治以降の侵略支配、その間に元寇に対する復習から始まったといわれる倭寇等にはじまり、再び緊張が高まりつつある現在、日本・韓国・中国の政治家に求められるのはこの芳洲の言葉かもしれない。芳洲は朝鮮通信使の儀礼についての日本側の傲慢に近い変更要求(新井白石発案)に朝鮮側との折衝に苦心しながら対応している。
私などこの言葉に大いに惹かれる。国という思想上の足かせとも言える概念に振り回される昨今、本当の意味での国際化が必要なのだが、大いに噛み締めたいと思う言葉だ。
厳原町もこの人の顕彰に力を入れているようだ。小学校の通学路に横断防止策にこの人の言葉を鋳物にして掲げている。小学生にはとても難しい言葉が並ぶが、馴染むことはいいことだ。
お墓はこの小学校の傍の長寿院というお寺にある。境内を登っていった竹やぶの中にひっそりと静かに建っている。人柄のように静かに周囲の竹林の雰囲気にぴったりと沿うように建っている。とてもいいところだ。訪れて良かったと思っている。


このほか、対馬班の御用船のドック兼桟橋ともいえる「お船江跡」も見学した。明治はじめの頃の写真も案内に表示されており、当時の港のようすもわかるように公園として整備され興味深かった。
しかし今回の訪問では、対馬の最高峰である矢立山(649m)に登ることが出来なかった。さらに下対馬だけを回ったことになり、上対馬については足を踏み入れなかった。また浅茅湾の美しい景色も城山から眺めただけで、逆に海岸から金田城を眺めることも敵なかった。さらに最北部の比田勝港も訪れることが出来なかった。 訪れる機会がもし人生の中で残されているとしたら、是非とも訪れてみたいものである。
・最近は山でも猪が多くなり、時々人に被害が出る。→これは入山前に教えて欲しかった。
・韓国の人は山登りが好きで20名くらいのもの団体でこの白嶽にもよく来る。
・対馬には蘭が自生しているが、残念ながら自衛隊が演習で踏みにじり射撃でダメにしてしまう。
・韓国人の登山者も蘭を持ち帰ってしまう人が多い。日本人の登山者にも悪いのがいることは確かだが‥。
・対馬の人はお墓を立派なのに仕立てる。石も立派なものを建てるし、石に刻んだ文字も金箔で飾り立てる。
・上対馬(北部)は山が多少なだらかなので上対馬にも足を運んで欲しい。
・対馬は山が深く、水が豊かなので水不足ということはまずまい。
・厳原の川沿いにはスナック等が120件もひしめいている。厳原町15,000人に比して多すぎる数といわれる。客は漁師中心といわれ、観光客はあまり利用しない。漁師の気風といわれる。


さて昨日記載忘れしたのが、「半井桃水」についての大納言様からの質問。対馬についたその日に半井桃水の旧居に寄ったのを忘れていた。大納言様のその日の質問に「桃水は樋口一葉のことをどう思っていたのか」というのがあった。この山登りの翌日、対馬最後の日に旧居を再度訪れたが休館日で詳しくは調べられなかった。私の記憶の範囲で展示内容を書いてみる。


まず、桃水は一葉の才能を見出したものの想定以上であったことを後日語っていたらしい。また一葉の死後、一葉の思いが桃水にあったことを日記の公開で知ったらしいが、そのことについては論評は控えたらしい。
桃水自身は妻を早くに亡くしたらしいが、当時の男としては珍しく24年間再婚はせずにいたらしい。最初の妻の死後24年後に再婚したが、出来た子は若くして亡くなったようだ。
桃水がどのように一葉のことを考えていたかはわからなかったものの、人に口外するような軽薄な男ではなかったと思われる。




そしてもうひとつ私が書きたいのは雨森(あめのもり)芳洲とその「誠信の交わり」について。
1990年、盧泰愚(ノテウ)大統領は、「...二百七十年前、朝鮮との外交にたずさわった雨森芳洲は、<誠意と信義の交際>を信条としたと伝えられます。彼の相手役であった朝鮮の玄徳潤は、東莱に誠信堂を建てて日本の使節をもてなしました...」と述べ、日本では忘れられていた雨森芳洲が俄然脚光を浴びた。
芳洲を顕彰する「雨森芳洲庵」が、1984年生地の高月町雨森に建設された。当時の滋賀県知事だった武村正義は、この事業を積極的に推進したようだ。
略歴は、1668年(寛文8)~1755年(宝暦5)、対馬藩に仕えて李氏朝鮮との通好実務にも携わった。木下順庵の推薦で、当時、中継貿易で潤沢な財力をもつ対馬藩に仕官。対馬藩朝鮮方佐役として藩政に関する上申書『治要管見』や朝鮮外交心得『交隣提醒』を書いている。思想的には自身が日本人である事を悔やみ「中華の人間として生れたかった」と漏らした記録が後世に伝わる。朝鮮語通詞養成所を対馬府中に創設。明治期まで多くの名通詞を輩出させるこの学校では,当時軽視されていたハングルで書かれた小説を教材に用いるなど、芳洲独自の教育理念・方法が貫かれていた。
盧泰愚大統領の言葉は芳洲のその内容はこの交隣提醒によっていて「朝鮮の風俗・習慣をよく理解し、違いを尊重して外交に当たるべきことを事例を挙げて説き、偏見や蔑視を抱いてはならないと強く主張している。また『誠信の交わり』については、互いに欺かず、争わず、真実をもって交わることこそ、まことの誠信である」との内容を踏まえている。
列島に人間が住み着いて以来、半島と列島の間で人の交流が続いてきた。歴史家にいわせると戦い・争いも交流の一環ということだが、歴史の節目節目にはとてつもない戦いが行われる。白村江・元寇・秀吉の侵略・明治以降の侵略支配、その間に元寇に対する復習から始まったといわれる倭寇等にはじまり、再び緊張が高まりつつある現在、日本・韓国・中国の政治家に求められるのはこの芳洲の言葉かもしれない。芳洲は朝鮮通信使の儀礼についての日本側の傲慢に近い変更要求(新井白石発案)に朝鮮側との折衝に苦心しながら対応している。
私などこの言葉に大いに惹かれる。国という思想上の足かせとも言える概念に振り回される昨今、本当の意味での国際化が必要なのだが、大いに噛み締めたいと思う言葉だ。
厳原町もこの人の顕彰に力を入れているようだ。小学校の通学路に横断防止策にこの人の言葉を鋳物にして掲げている。小学生にはとても難しい言葉が並ぶが、馴染むことはいいことだ。
お墓はこの小学校の傍の長寿院というお寺にある。境内を登っていった竹やぶの中にひっそりと静かに建っている。人柄のように静かに周囲の竹林の雰囲気にぴったりと沿うように建っている。とてもいいところだ。訪れて良かったと思っている。


このほか、対馬班の御用船のドック兼桟橋ともいえる「お船江跡」も見学した。明治はじめの頃の写真も案内に表示されており、当時の港のようすもわかるように公園として整備され興味深かった。
しかし今回の訪問では、対馬の最高峰である矢立山(649m)に登ることが出来なかった。さらに下対馬だけを回ったことになり、上対馬については足を踏み入れなかった。また浅茅湾の美しい景色も城山から眺めただけで、逆に海岸から金田城を眺めることも敵なかった。さらに最北部の比田勝港も訪れることが出来なかった。 訪れる機会がもし人生の中で残されているとしたら、是非とも訪れてみたいものである。