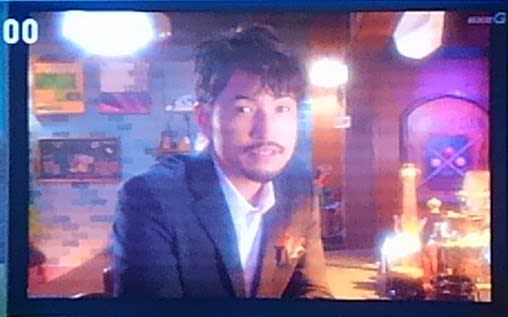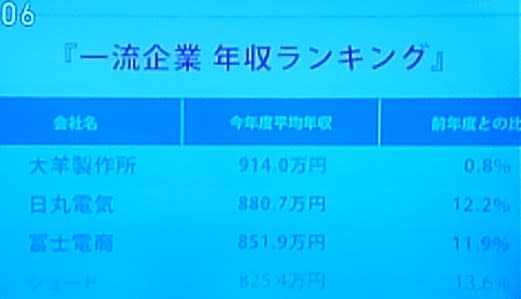■精神疾患の親がいる子 どう支援@あさイチ
専門家ゲスト:蔭山正子さん(大阪大学大学院 医学系研究科准教授)
ゲスト:宮崎美子さん、新納慎也さん
リポーター:馬場典子アナウンサー、清有美子記者(NHKさいたま)
【内容抜粋メモ】
 親が精神疾患 その時子どもは
親が精神疾患 その時子どもは
みほさん(仮名15歳 父が躁鬱病):
「気分が悪い」「頭が痛い」と言って寝てばかりで、家族も気を使っているんですけど
今度は私たちがおかしくなるんじゃないかって話をしたりして
躁状態とうつ状態を繰り返す「双極性障害」

みほさん:
機嫌を損ねると何をされるか分からないところがあるので、全然話もしないし、
たまに部屋から出てきたら、みんなスッて避けるような感じで
「精神疾患で変な人でしょ」て周りのイメージが悪いみたいで
外部にはうかつに漏らせませんでした
「死んでやるぞ!」みたいなことを言って、
自分の首すじのところに刃物をあてて、目がイっちゃっていて、
正気じゃない感じだったので、大慌てで母と止めに入りました
「もう死なせてくれ」って言ってすごく怖かったです

「警察に通報して精神病院に入院」
みほさん:
その後、本人が「家に帰りたい」と主張し、3週間で家に戻ってきて、どう接していいか分からなかった
本当に心の準備ができていないので、迎え入れる準備は全然できていなかったです

「こういう支援がありますよ」とか紹介してくれたり、話を聞いてくれるとか
訪問看護も病院で父に勧めてもらえたら、もっと違ったんじゃないかなと思います
記者:
色々なサービスはあるけれども、治療自体は病院の中だけで完結しているので
きめ細かい対応をしてくれる病院ばかりではなく
取材させていただいた多くのケースで、なかなかきめ細かいサポートが受けられていない家族が
孤立した状態で、みんなで面倒を見ている
そのしわ寄せが子どもにいってしまうというケースが多かったです
Q:3週間で本人の意思が尊重されるんですか?
専門家:
他の人に暴力を振るうとか、危害を加えるような場合は
本人が「出たい」と言っても出られないケースがあるんですけれども
今回は、他の病気と同じで、本人が出たい、家族がいるという場合は
「すぐに退院してください」ということになった 精神疾患の場合の難しさがあります
 把握しづらい理由
把握しづらい理由
1.分かりずらい
2.言いづらい
専門家:
そもそも精神疾患は外から見てわからない
例えば子どもが虐待を受けていたり、
長期的に学校を休んでいたりする場合は分かるけれども、外からはなかなか見えづらい
精神疾患は「偏見」を持たれていて、子どもが親族などから「他の人には言ってはいけない」
と言われているケースや、そういう話をしているのを聞いて
「外に言ってはいけない病気なのかな」と子どもが思って、
周囲に言わずに隠してしまうケースも多い
大吉:
今回出てくれたのは、15歳の娘さんでしたけれども
もっと小さいお子さんでしたら意味も分からないだろうし
馬場:
みほさん自身も、お父さんの症状の発症は10年前なので
小さい時から大人になるまで、誰にも自分の思いを伝えられずに抱えている人が多い
 患者本人だけでなく、家族への支援を
患者本人だけでなく、家族への支援を
最近こういった、誰にも言えなかった思いを「共有」できる場が出来始めてる
【今年6月 東京 清瀬 ワークショップ】
精神疾患がある親をもつ子どもたちの「家族会 こどもぴあ」
医師や、看護師、研究者も集まった


彼らは誰にも助けを求められず、孤独だった当時の気持ちを打ち明けて
患者だけでなく、その家族にも支援してほしいと訴えた
家族会では、当時の思いや、今の悩みを相談し合える会合を
東京や大阪などで定期的に開いていて、今後、全国的に活動を広げて行こうとしている
参加者:
負担に思って当たり前で、辛くなって
逃げ出してよかったと、今では思っています
記者:
集まっているのは大学生くらいから40歳くらいまでの方々なんですけれども
初めて同じ境遇の方々に出会ったと言う方も多かったですし
初めて自分の思いを、他の人に伝えられた、受け止めてもらえた、という方が多くて
中には、涙しながら話している方も多くいらっしゃいました
専門家:大人になったからようやく話せるという面もあるかもしれません
精神疾患の家族支援を研究し、ご自身も保健師である蔭山正子さん

Q:たとえ大人になってからでも、言えるようになったというのは大きな一歩でしょうか?
蔭山:
そうですね 誰にも言えず心にフタをして「自分は普通の家で育ってこなかった」
「自分には欠けたものがある」という風に思っている方が
たくさんの同じ境遇の人に会うことによって
「これは自分がダメだったわけではないんだ」
「親が病気になれば、こういうことが起こるんだ」と分かることで
自分に自信を取り戻していくという効果があると思います
 周りの大人はどうサポートしたらいいのか
周りの大人はどうサポートしたらいいのか
母親が精神疾患を患うやよいさん(仮名 30歳):
食事の支度もしてくれていたのができない状態になったりとか
どんどん変になっちゃっている感じでした

母親がうつ病の診断を受けたのは、やよいさんが小学5年生の時
母は自殺未遂を何度も繰り返していた
やよいさん:
お薬を飲み過ぎちゃったりとか、ちょっと体を傷つけてみたりとか
それを小学6年生、中学生ぐらいで受け止めていて
Q:お母さんが「死にたい」って言うのを聞いてどういう気持ちでした?
やよいさん:
まず、一番ショックでしたし、自分が悪いことをしているせいで
母が辛い思いをしているんじゃないかって思っていたので
また死にたいって思わせちゃって、私が何か悪いことしたのかなと思っていました
●精神疾患の親を持つ子どもの6割が、成人した後、うつ病や不安障害になっている可能性が高い

やよいさん:
自分自身を傷つけるまで追い込まれた
リストカットしてしまったり、何かそうすると落ち着くみたいな
本当に病気だったと思うんですけど、その時の自分は、
自分で自分を罰しているとちょっと許されるような気がした
記者:
こうした子どもたちにとって支えとなるのは、周囲の大人の存在
やよいさんにとっては、中学3年生の時の担任の教師でした

やよいさん:
小さい時からすごく大変な思いをしてきたんだとか、
お母さんが自殺未遂を何回もして精神科に入院しているんだとか
そういう話をすごく聞いてくれた
この時の担任のひと言が彼女を勇気づけてくれた
「あなたは、あなたの人生を歩んでいいのよ」
やよいさん:
今まで誰にも言えなかった気持ちを受け入れてくれる人に初めて出会えた
それは、今でも私の中にすごく大きな考え方として残っていて
「私の人生ってあるんだな」って思って、ちょっとずつ変わっていきました
「やよいさんは、中学卒業と同時に母親と離れる決断をした」

やよいさん:
児童相談所の職員と相談し、自らの意思で児童養護施設に入った
中学校の先生の「私の人生を歩むように」っていう助言を思い出して
母との生活はずっとうまくいかなかったので
私は自分で選んで、家族から離れるという決断をしました
母親のケアは、保健師など、地域の福祉サービスを利用することにしました
プロの手を借りるようになると、母との関係も変わってきた

すごく母と接することが楽になりました
冷静に母のことを見られるというか、心に余裕があるので
母の話を聞いたり、距離感が取れるようになった
馬場アナ:
一般的にここまでうまくいくケースばかりではない
彼女はものすごく葛藤があった
「人に言ってはいけない」と思っていたので、相談もできなかったですし
彼女の場合は、中学校1年の時から、担任に「大丈夫?」と声をかけてもらい
ようやく3年生の時に初めて自分の思いを打ち明けることができた
それで「相談してもいいんだ」という思いになって、次のステップに進めたという形なんですね
 私たちには何ができるのか?
私たちには何ができるのか?
1.気づくこと
2.聞くこと
専門家:
「気づく」というのも難しい
子どもは必死に普通の家庭を見せますので、なかなか明らかな変化はないんですけれども
親の集まりに来なくなったとか
子どもも精神的に不安定になってくるので「爪噛み」とか落ち着きがないとか
学校ですと「忘れ物をするようになった」とか、遅刻する、授業中に居眠りをする
朝ごはんを食べずに倒れてしまうとか
学校が終わった後、以前は友だちと遊んでいたのが、すぐに家に帰ってしまう
逆になかなか家に帰りたがらないということもある
近所だと、回覧板を回すのを子どもがやっているとか
家に電話しても、前は親が出ていたのが、子どもが出るとか
そうした時に「お母さんどうしたの?」と聞いても
「今、ちょっと忙しいから」と言う
ちょっと何かおかしい嘘をついてると思わせるような素振りがあったりして
小さな変化なんですけれども、気づくポイントみたいなものは一応あります
「聞く」ということが大切なんですけれども
今まで人に甘えたり、相談するということをしてこなかった子たちなので
何回も何回も気にかけてあげる
「あなたのことを心配しているんだよ」「あなたの力になりたい」
というメッセージを出し続けていただきたい
 具体的にどんなところに相談したら力になってくれるのか?
具体的にどんなところに相談したら力になってくれるのか?

児童福祉関係の窓口にまずは尋ねてみてください
保健所も相談にのってくれます
「チャイルドライン」
18歳以下の子ども向けの電話 0120-99-7777 通話無料 ※携帯からもかけることができる
Q:家族に注意してもらいたいことはありますか?
専門家:
「こんなに大変なんです」と言うのはなかなか難しいんですけれども
ありのままを、正確に伝えていただくことで、早く適切な機関につながることができると思います
Q:子どもにどんな声をかけたらいいですか?
専門家:
おそらく前は大好きだったお父さんや、お母さんが、
最近はなんか優しくないと思っているかもしれないですけれども
きっと親は子どものことを一番大切に思っているはずです
ですから
「子どもが苦しかったら、周りに助けを求めていいんだよ それを親も望んでいるんだよ」
というようなことを伝えていただきたいと思います
専門家ゲスト:蔭山正子さん(大阪大学大学院 医学系研究科准教授)
ゲスト:宮崎美子さん、新納慎也さん
リポーター:馬場典子アナウンサー、清有美子記者(NHKさいたま)
【内容抜粋メモ】
 親が精神疾患 その時子どもは
親が精神疾患 その時子どもはみほさん(仮名15歳 父が躁鬱病):
「気分が悪い」「頭が痛い」と言って寝てばかりで、家族も気を使っているんですけど
今度は私たちがおかしくなるんじゃないかって話をしたりして
躁状態とうつ状態を繰り返す「双極性障害」

みほさん:
機嫌を損ねると何をされるか分からないところがあるので、全然話もしないし、
たまに部屋から出てきたら、みんなスッて避けるような感じで
「精神疾患で変な人でしょ」て周りのイメージが悪いみたいで
外部にはうかつに漏らせませんでした
「死んでやるぞ!」みたいなことを言って、
自分の首すじのところに刃物をあてて、目がイっちゃっていて、
正気じゃない感じだったので、大慌てで母と止めに入りました
「もう死なせてくれ」って言ってすごく怖かったです

「警察に通報して精神病院に入院」
みほさん:
その後、本人が「家に帰りたい」と主張し、3週間で家に戻ってきて、どう接していいか分からなかった
本当に心の準備ができていないので、迎え入れる準備は全然できていなかったです

「こういう支援がありますよ」とか紹介してくれたり、話を聞いてくれるとか
訪問看護も病院で父に勧めてもらえたら、もっと違ったんじゃないかなと思います
記者:
色々なサービスはあるけれども、治療自体は病院の中だけで完結しているので
きめ細かい対応をしてくれる病院ばかりではなく
取材させていただいた多くのケースで、なかなかきめ細かいサポートが受けられていない家族が
孤立した状態で、みんなで面倒を見ている
そのしわ寄せが子どもにいってしまうというケースが多かったです
Q:3週間で本人の意思が尊重されるんですか?
専門家:
他の人に暴力を振るうとか、危害を加えるような場合は
本人が「出たい」と言っても出られないケースがあるんですけれども
今回は、他の病気と同じで、本人が出たい、家族がいるという場合は
「すぐに退院してください」ということになった 精神疾患の場合の難しさがあります
 把握しづらい理由
把握しづらい理由1.分かりずらい
2.言いづらい
専門家:
そもそも精神疾患は外から見てわからない
例えば子どもが虐待を受けていたり、
長期的に学校を休んでいたりする場合は分かるけれども、外からはなかなか見えづらい
精神疾患は「偏見」を持たれていて、子どもが親族などから「他の人には言ってはいけない」
と言われているケースや、そういう話をしているのを聞いて
「外に言ってはいけない病気なのかな」と子どもが思って、
周囲に言わずに隠してしまうケースも多い
大吉:
今回出てくれたのは、15歳の娘さんでしたけれども
もっと小さいお子さんでしたら意味も分からないだろうし
馬場:
みほさん自身も、お父さんの症状の発症は10年前なので
小さい時から大人になるまで、誰にも自分の思いを伝えられずに抱えている人が多い
 患者本人だけでなく、家族への支援を
患者本人だけでなく、家族への支援を最近こういった、誰にも言えなかった思いを「共有」できる場が出来始めてる
【今年6月 東京 清瀬 ワークショップ】
精神疾患がある親をもつ子どもたちの「家族会 こどもぴあ」
医師や、看護師、研究者も集まった


彼らは誰にも助けを求められず、孤独だった当時の気持ちを打ち明けて
患者だけでなく、その家族にも支援してほしいと訴えた
家族会では、当時の思いや、今の悩みを相談し合える会合を
東京や大阪などで定期的に開いていて、今後、全国的に活動を広げて行こうとしている
参加者:
負担に思って当たり前で、辛くなって
逃げ出してよかったと、今では思っています
記者:
集まっているのは大学生くらいから40歳くらいまでの方々なんですけれども
初めて同じ境遇の方々に出会ったと言う方も多かったですし
初めて自分の思いを、他の人に伝えられた、受け止めてもらえた、という方が多くて
中には、涙しながら話している方も多くいらっしゃいました
専門家:大人になったからようやく話せるという面もあるかもしれません
精神疾患の家族支援を研究し、ご自身も保健師である蔭山正子さん

Q:たとえ大人になってからでも、言えるようになったというのは大きな一歩でしょうか?
蔭山:
そうですね 誰にも言えず心にフタをして「自分は普通の家で育ってこなかった」
「自分には欠けたものがある」という風に思っている方が
たくさんの同じ境遇の人に会うことによって
「これは自分がダメだったわけではないんだ」
「親が病気になれば、こういうことが起こるんだ」と分かることで
自分に自信を取り戻していくという効果があると思います
 周りの大人はどうサポートしたらいいのか
周りの大人はどうサポートしたらいいのか母親が精神疾患を患うやよいさん(仮名 30歳):
食事の支度もしてくれていたのができない状態になったりとか
どんどん変になっちゃっている感じでした

母親がうつ病の診断を受けたのは、やよいさんが小学5年生の時
母は自殺未遂を何度も繰り返していた
やよいさん:
お薬を飲み過ぎちゃったりとか、ちょっと体を傷つけてみたりとか
それを小学6年生、中学生ぐらいで受け止めていて
Q:お母さんが「死にたい」って言うのを聞いてどういう気持ちでした?
やよいさん:
まず、一番ショックでしたし、自分が悪いことをしているせいで
母が辛い思いをしているんじゃないかって思っていたので
また死にたいって思わせちゃって、私が何か悪いことしたのかなと思っていました
●精神疾患の親を持つ子どもの6割が、成人した後、うつ病や不安障害になっている可能性が高い

やよいさん:
自分自身を傷つけるまで追い込まれた
リストカットしてしまったり、何かそうすると落ち着くみたいな
本当に病気だったと思うんですけど、その時の自分は、
自分で自分を罰しているとちょっと許されるような気がした
記者:
こうした子どもたちにとって支えとなるのは、周囲の大人の存在
やよいさんにとっては、中学3年生の時の担任の教師でした

やよいさん:
小さい時からすごく大変な思いをしてきたんだとか、
お母さんが自殺未遂を何回もして精神科に入院しているんだとか
そういう話をすごく聞いてくれた
この時の担任のひと言が彼女を勇気づけてくれた
「あなたは、あなたの人生を歩んでいいのよ」
やよいさん:
今まで誰にも言えなかった気持ちを受け入れてくれる人に初めて出会えた
それは、今でも私の中にすごく大きな考え方として残っていて
「私の人生ってあるんだな」って思って、ちょっとずつ変わっていきました
「やよいさんは、中学卒業と同時に母親と離れる決断をした」

やよいさん:
児童相談所の職員と相談し、自らの意思で児童養護施設に入った
中学校の先生の「私の人生を歩むように」っていう助言を思い出して
母との生活はずっとうまくいかなかったので
私は自分で選んで、家族から離れるという決断をしました
母親のケアは、保健師など、地域の福祉サービスを利用することにしました
プロの手を借りるようになると、母との関係も変わってきた

すごく母と接することが楽になりました
冷静に母のことを見られるというか、心に余裕があるので
母の話を聞いたり、距離感が取れるようになった
馬場アナ:
一般的にここまでうまくいくケースばかりではない
彼女はものすごく葛藤があった
「人に言ってはいけない」と思っていたので、相談もできなかったですし
彼女の場合は、中学校1年の時から、担任に「大丈夫?」と声をかけてもらい
ようやく3年生の時に初めて自分の思いを打ち明けることができた
それで「相談してもいいんだ」という思いになって、次のステップに進めたという形なんですね
 私たちには何ができるのか?
私たちには何ができるのか?1.気づくこと
2.聞くこと
専門家:
「気づく」というのも難しい
子どもは必死に普通の家庭を見せますので、なかなか明らかな変化はないんですけれども
親の集まりに来なくなったとか
子どもも精神的に不安定になってくるので「爪噛み」とか落ち着きがないとか
学校ですと「忘れ物をするようになった」とか、遅刻する、授業中に居眠りをする
朝ごはんを食べずに倒れてしまうとか
学校が終わった後、以前は友だちと遊んでいたのが、すぐに家に帰ってしまう
逆になかなか家に帰りたがらないということもある
近所だと、回覧板を回すのを子どもがやっているとか
家に電話しても、前は親が出ていたのが、子どもが出るとか
そうした時に「お母さんどうしたの?」と聞いても
「今、ちょっと忙しいから」と言う
ちょっと何かおかしい嘘をついてると思わせるような素振りがあったりして
小さな変化なんですけれども、気づくポイントみたいなものは一応あります
「聞く」ということが大切なんですけれども
今まで人に甘えたり、相談するということをしてこなかった子たちなので
何回も何回も気にかけてあげる
「あなたのことを心配しているんだよ」「あなたの力になりたい」
というメッセージを出し続けていただきたい
 具体的にどんなところに相談したら力になってくれるのか?
具体的にどんなところに相談したら力になってくれるのか?
児童福祉関係の窓口にまずは尋ねてみてください
保健所も相談にのってくれます
「チャイルドライン」
18歳以下の子ども向けの電話 0120-99-7777 通話無料 ※携帯からもかけることができる
Q:家族に注意してもらいたいことはありますか?
専門家:
「こんなに大変なんです」と言うのはなかなか難しいんですけれども
ありのままを、正確に伝えていただくことで、早く適切な機関につながることができると思います
Q:子どもにどんな声をかけたらいいですか?
専門家:
おそらく前は大好きだったお父さんや、お母さんが、
最近はなんか優しくないと思っているかもしれないですけれども
きっと親は子どものことを一番大切に思っているはずです
ですから
「子どもが苦しかったら、周りに助けを求めていいんだよ それを親も望んでいるんだよ」
というようなことを伝えていただきたいと思います