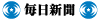「飛
"飛行第二四四戦隊歌(飛燕戦闘機隊々歌) 唄:御堂諦" を YouTube で見る
燕」公開!日本の戦闘機は新時代を迎えられるか
ニュースイッチ 10月14日(金)11時53分配信

『公開された「飛燕(ひえん)」川重が15日から記念展 川崎重工業は同社が細部にわたり修復・復元した戦闘機「飛燕(ひえん)=写真」を神戸市内で報道陣に公開した。神戸ポートターミナル(神戸市中央区)で15日から開く「川崎重工創立120周年記念展」の目玉展示物となる。川重が第二次世界大戦中に開発・製造し国内で現存する唯一の機体を、3次元データをとり当時の状態に近い形で復元した。 飛燕は岐阜工場(岐阜県各務原市)で全長約9メートルの機体を、明石工場(兵庫県明石市)では約1年かけてエンジン部品となる過給器を修復・復元した。川重では「文化財としての価値を認識しながら復元した。当社の技術者魂や誇り高い情熱を感じてほしい」としている。記念展は11月3日まで。入場無料。
 初飛行する「X―2」どうなるステルス実証機「X―2」 戦前の日本は航空機大国の名をほしいままにしていた。零戦、二式大艇、紫電改、九七戦、九六艦戦、隼(はやぶさ)、飛燕、疾風(はやて)など多くの航空機をつくりあげた。1944年には2万9000機も生産し、100万人を超える従事者を数えた。それが敗戦で産業が解体された。 それから約70年。今年、防衛省は相手のレーダーに捕捉されにくいステルス戦闘機開発のための先進技術実証機「X―2」の初飛行に成功した。 X―2は機体だけでなくエンジンも国産化した初のステルス機で、今後岐阜県内で飛行試験を実施し、ステルス能力や機動性を検証。2018年度までに航空自衛隊のF2戦闘機の後継機を、戦後初の純国産化するかどうかを決める予定。純国産機の生産が決まれば、国内航空機産業への波及効果が見込める。初飛行がその第一歩になると期待される。 X―2は愛知県営名古屋空港(愛知県豊山町)から航空自衛隊岐阜基地(岐阜県各務原市)までを4月22日に飛行した。開発費は約394億円で、機体の形状や電波を吸収する素材の採用により、ステルス性を得るほか、高い運動性を有する。三菱重工業が機体製造を取りまとめ、IHIがエンジンを供給。富士重工業、川崎重工業など約220社が参画した。 F2戦闘機は30年代に退役すると見込まれる。防衛省は後継機を18年度までに純国産化するか、国際共同開発するかを判断する。F2戦闘機が米国との共同開発だったように、これまで日本単独で戦闘機を開発できていない。実現すれば、国内航空機産業の発展に大きな意味を持つ。 航空機産業は民間向けと防衛向けが技術、生産両面で深く結びつく。戦闘機開発で技術力を培い、旅客機開発に生かせる。純国産戦闘機の生産は、航空機産業の底上げにつながる。』
初飛行する「X―2」どうなるステルス実証機「X―2」 戦前の日本は航空機大国の名をほしいままにしていた。零戦、二式大艇、紫電改、九七戦、九六艦戦、隼(はやぶさ)、飛燕、疾風(はやて)など多くの航空機をつくりあげた。1944年には2万9000機も生産し、100万人を超える従事者を数えた。それが敗戦で産業が解体された。 それから約70年。今年、防衛省は相手のレーダーに捕捉されにくいステルス戦闘機開発のための先進技術実証機「X―2」の初飛行に成功した。 X―2は機体だけでなくエンジンも国産化した初のステルス機で、今後岐阜県内で飛行試験を実施し、ステルス能力や機動性を検証。2018年度までに航空自衛隊のF2戦闘機の後継機を、戦後初の純国産化するかどうかを決める予定。純国産機の生産が決まれば、国内航空機産業への波及効果が見込める。初飛行がその第一歩になると期待される。 X―2は愛知県営名古屋空港(愛知県豊山町)から航空自衛隊岐阜基地(岐阜県各務原市)までを4月22日に飛行した。開発費は約394億円で、機体の形状や電波を吸収する素材の採用により、ステルス性を得るほか、高い運動性を有する。三菱重工業が機体製造を取りまとめ、IHIがエンジンを供給。富士重工業、川崎重工業など約220社が参画した。 F2戦闘機は30年代に退役すると見込まれる。防衛省は後継機を18年度までに純国産化するか、国際共同開発するかを判断する。F2戦闘機が米国との共同開発だったように、これまで日本単独で戦闘機を開発できていない。実現すれば、国内航空機産業の発展に大きな意味を持つ。 航空機産業は民間向けと防衛向けが技術、生産両面で深く結びつく。戦闘機開発で技術力を培い、旅客機開発に生かせる。純国産戦闘機の生産は、航空機産業の底上げにつながる。』
私が、本物の飛燕(ひえん)を初めて見たのは、中学生1年生で、阪神百貨店梅田本店の屋上の遊園地でした。
航空自衛隊の説明担当者が、一人いまして1万メートル 間で何分掛るか聞いたのですが不親切で中学生の私は答えてくれませんでした。旧大日本帝国陸軍軍人として7年間闘った子供に対し真に無礼でした。
玉手山遊園地で、信太山の特科連隊の自衛隊の展示会が有り、亡き父に連れられて行きましたが、小学生の私に父の年齢から戦争体験の有る人と思ったのだと感じ、陸上自衛隊戦車の説明担当者が、戦車に登ることを許可してくれ丁寧に説明してくれました。
三菱重工の61式中戦車でしたが、チビの私は、戦車の砲塔の上に上がるのになかなかでした。どうして製造会社名前がわかったと言いますと後ろから攀じ登った時に金属板に会社名が、貼って有ったからです。とても人間では戦車を 装甲の厚さで破壊でき無いと思いました。
思ったより小さい機体と操縦席の一人乗りの飛燕を見まして、空中で子供心に怖くなかったのかなあ、空の要塞と言われた巨大なB29によく果敢に攻撃したと正直に思いました。
帝都防衛で活躍された若き飛燕の撃墜王は、戦死されたそうですが。
当時の大日本帝国陸軍航空隊の飛燕の操縦士は、本当に命懸けで闘われた肝っ玉の有る操縦士と思いました。
今国の為に死なない平気で、公言する与党政治家では、日本と国民を守れるかと言うことです。
戦前の世界一の工業生産力のアメリカと対峙した当時の日本とは違い工業生産力と総合的な科学開発力が今の日本には有るので、航空機、戦闘機に限らずこれからも新時代を切り開いていけると思います。

川崎 キ61 三式戦闘機「飛燕」
1944年3月、台湾・松山飛行場に駐屯する第37教育飛行隊所属の三式戦一型甲(キ61-I甲)
用途:戦闘機
設計者:土井武夫
製造者:川崎航空機
運用者: 大日本帝国(日本陸軍)
初飛行:1941年12月
生産数:2,750 - 3153機 (諸説あり)
生産開始:1942年
退役:1945年
運用状況:退役
三式戦闘機(さんしきせんとうき)は第二次世界大戦時に大日本帝国陸軍が開発し、1943年(昭和18年)に制式採用された戦闘機である。開発・製造は川崎航空機により行われた。設計主務者は土井武夫、副主任は大和田信であ。
ドイツの液冷航空エンジンDB601を国産化したハ40を搭載した、当時の日本唯一の量産型液冷戦闘機である。防弾装備のない試作機は最高速度590km/hを発揮したが、防弾装備や燃料タンク等を追加した量産機では鈍重な戦闘機になり下がり、アメリカ軍に「もっとも食いやすい(つまりアメリカ軍にとっては攻撃し易い)戦闘機」という印象を与えている。基礎工業力の低かった当時の日本にとって不慣れな液冷エンジンハ40は生産・整備ともに苦労が多く、常に故障に悩まされた戦闘機としても知られる。ハ40の性能向上型であるハ140のエンジン生産はさらに困難であり、これを装備する予定であった三式戦闘機二型はわずか99機しかエンジンが搭載できず、工場内に首無しの三式戦闘機が大量に並ぶ異常事態が発生した。そこで星型空冷エンジンを急遽搭載した日本陸軍最後の制式戦闘機五式せんと戦闘機かされが生産された。
blockquote>"飛行第二四四戦隊歌(飛燕戦闘機隊々歌) 唄:御堂諦" を YouTube で見る