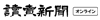jlj0011のblog
JR総連は健在<本澤二郎の「日本の風景」(4667)
- 2022/12/27 09:21
- コメント1
- 16
- 前の記事
- ホーム
JR総連は健在!<本澤二郎の「日本の風景」(4667)
<連合執行部の右翼ボケに警鐘、労働組合の模範労組として活躍>
A4サイズの4ページの機関紙が郵送されてきた。JR総連(全日本鉄道労働組合総連合会)の12月15日付紙面の1面は、憲法改悪反対と軍事大国化反対の2つのスローガンが踊っている。見る人によっては「すごい」と感動するだろうが、日本の現状を認識している者からすると、当たり前のスローガンである。ただし、日本の言論界の右傾化が災いして、岸田内閣の戦争準備を「肯定」する市民も増えているとも一部で報じられていると聞いた。
昨日も日刊ゲンダイの小塚編集局長が、このことについてコメントを求めてきた。報道は事実?だとすると、右傾化報道の成果といえなくもない。戦争準備に国民の半数前後が「容認」しているということは、右翼化言論による意図的に
つくられた調査結果であろう。
半数の日本人が、突如として精神の異常をきたしたものか。日本医師会の出番となるのだが、つくられた世論は真実の前に屈する。JR総連は朝日新聞読者と赤旗新聞読者と連携するといい。
「日本人の平和主義はいい加減なものではない」とは宇都宮徳馬が、手塩にかけた渡辺恒雄が、こともあろうに正力松太郎や岸信介に屈して、読売を改憲新聞に切り替えたころの叫びである。平和国民は、憲法改悪と軍事大国化の阻止でもって、連携してA級戦犯の亡霊政権に立ち向かうべきである。
小異を残して大道につく2023年を誓う必要があろう。2023年は神道・統一教会・創価学会のカルト政党を打倒する時でもある。
改めて、日本の鉄道労組の健在ぶりに敬意を表したい。孫文が好んで使った敬天愛人で、国家主義の日本を打倒しよう。強く訴えたい。
<国民の命を守る平和運動は松崎明イズムが今も!>
JR総連の時代を正確にとらえた2大スローガンを見たときに、亡き山崎明さんを思い出す。既に、日本の右翼化を背後で指揮してきたJR東海の葛西某は亡くなった。安倍晋三も。
しかしながら、松崎イズムは敢然として生きていた。JR総連の運動方針はびくともしていない。ということは、松崎の労働運動指導者としての偉大さと正義の戦いが、日本国民の思いと一体だったことの証明であろう。
松崎明は、今も労働運動の指導理念として生きているのである。例えばだが、宏池会の池田勇人や前尾繫三郎、大平正芳、宮澤喜一、加藤紘一の護憲平和の理念は、岸田文雄によってドブに捨てられた。
創価学会の池田大作も病に倒れた途端、公明党の太田ショウコウや山口那津男、北側一夫らによって、これまた消されてしまった。偉大な指導者の要件は、いい後継指導者を生み出したかどうかで決まる。その点で、松崎は圧倒している。
<連合の89回中央委員会で熊谷書記長が芳野会長を厳しく批判>
機関紙2面を開くと、熊谷書記長の連合中央委員会(12月1日)の執行部の春闘方針案に対して、右にばかり転んで波紋を作り出している芳野会長に対して、厳しく批判して執行部を震え上がらせたことを報じていた。
「岸田政権が防衛費をGDP比2%にすると、国民生活はさらに追い込まれる。JR総連は軍拡に反対し、憲法9条を守り、平和な社会の実現、そして労働者の生活を守るための運動を進めていく」
「組合員から連合の芳野会長に多くの疑問の声が上がっている。麻生らとの会食、安倍国葬に参加するなど、連合はどこに向かっているか、とJR総連に見解が求められている」
これらの当たり前の怒りの指摘を、立民や共産党からも聞こえてこない。野党の猛省と共に、連合の右傾化阻止が国民にとって不可欠な課題であろう。世界第三位の軍事大国は、憲法を破壊し、第三次世界大戦を誘引する。東アジアの火薬庫に小躍りする欧米戦略にはまってなるものか。
このほかJR総連近畿地協、同東海地協の定期委員会でも平和運動の重要性が指摘されている。
<情報通信関係労組交流会で暴かれた真実の差別的賃金格差>
「2022年の年収374万円は、1994年の505万円と比較すると、131万円も下がっている、非正規雇用の全労働者に占める割合は、1995年の17%から40%に異常急拡大している、他方で役員報酬1億円企業2010年の166社から287社にほぼ倍増している、労働者は騙されている」との報告は、情報通信関係労組の交流会で明かされた。
日本の労働者の賃金は、清和会統一教会政治のもとで、途方もなく激減していたのだ。非正規労働者の急増の悲劇と比例して、大手企業は自社株買いで経営陣は暴利。投資をやめて株転がしで暴利の日本財界・財閥の日本は、森喜朗・小泉純一郎・安倍晋三ら清和会政治のもとでの確たる実績だ。アベノミクス・竹中平蔵に怒りが込み上げてくるではないか。
連合は松崎イズムを貫徹する時代の劈頭に立たされている。
本日も監視電話がかかった。「間違いないでした」といって切る。犯人は見当がつくのだが。
2022年12月27日記(政治評論家・日本記者クラブ会員)
拍手する 16
コメントを書く
コメント(1件)
カテゴリなしの他の記事
- 精神病患者の群れ<本澤二郎の「日本の風景」(4666)
- 五輪疑獄=安倍・森・石原が本命<本澤二郎の「日本の風景」(4665)
- 二階俊博の暴言<本澤二郎の「日本の風景」(4664)
- 世論に敵対する岸田内閣<本澤二郎の「日本の風景」(4663)
- 伊藤詩織さんに続け<本澤二郎の「日本の風景」(4662)
コメント 1
1.桃子
2022年12月27日 11:30
日本の政治の悪政はすべて支配者です。
愛国心のないことが、今露呈しています。政府政治家は操られた人形とかしています。政治家は皆、皇居にて認証式に出席します。また国会には天皇が来ることもあります。象徴天皇制だからと本当に思いますか?
彼らの上には天皇家があるという意味です。そして、それらを操る本家本元の朝廷は自ら影に隠れていつも操作してきました。
彼らは世界を操るために、陰に回っただけです。彼らはサイコパスです。彼らは欲が深く愛を知りません。愛を真似る事はできますが、それは欲望と執着です。サイコパスはすでに世界中に広まっています。彼らの時代は、もうすぐ終りになります。
支配者層のトップはすでにこの世にはいなくなりましたが、
下部組織は自分たちの欲望を失う事を良しとしていません。
また資金が量子銀行システムに変えられたために、欲望による資金の
送金は出来なくなりました。これは神のシステムだからです。
その為に、国民からあらゆる方法でお金を集めるような政策を
私達は見ています。支配者に日本人が気づくまで続くかもしれません。
彼らの正体は公家、朝廷、ウラ天皇たちです。彼らは税金を納めることはありませんでした。暴利謀略の裏を隠して表の顔を見せています。
彼ら一族はこれから、どうなるのでしょう。
私達は、彼らの激しい抵抗のありようを今見ているのです。
アクマのサイコパスの最後の抵抗です。
彼らは追い詰められていますが、それも隠しています。
この戦いは、すでに私達の勝利です。あと少しでわかるでしょう。
0
コメントを書く
読者登録
livedoor Blog
PCモード
トップへ
Powered by livedoor Blog