本日、 。
。
昨日は、4年前に研修させていただいた(財)自然農法国際研究開発センターを見学しました。
今回は、職員さんのご都合がつかなかったため、なぜか私が見学を誘導することになりました。
師匠たちの試験栽培をうまく説明しきれないのは承知してもらい友人一行さんと見学しました。

上は、交互栽培の事例です。「生態制御チーム」の試験区です。
左は、青山在来という大豆が育っています。前作は、麦でした。
右は、トマトです。トマトの後に麦を植えます。
つまり、小麦→大豆→トマト→小麦と左と右を毎年交互に栽培することで、
安定した栽培もできます。
また、自給作物である大豆・麦から醤油・味噌・麦の自給もでき、麦ワラもトマトに敷くことができます。

圃場を移動したら、運のいいことに育種課の課長さんがお忙しい中圃場を案内してくれました。

これは、自然農法の育種の一例で、「トマトの自然生え」育種です。
トマトをそのまま土に置き自然に土に還すことによって、
来年桃の花が咲く頃に、トマトが自然に発芽してきます。
育ったトマトの中から食味の良いものを選び、自然と人がお互いに関わりながら育種している事例です。

自然農法センターでは、無農薬栽培で育てやすい種子を育種しています。
写真はキュウリの採種果です。
キュウリは、肥料に依存することなく、自分自身で根がしっかり張れるものを、草と共に育てることで、選抜しています。

こちらは、「自然農法の種」で一番人気の「筑摩野五寸ニンジンです」。
火山灰土のような軽い土壌で、無肥料で育つとても美味しいニンジンです。

こちらは、自然農法センターの田んぼです。
稲は、とてもシンプルで、水と土と太陽で育ちます。
「水稲チーム」では、除草を主に研究しているチームで、
田んぼには稲が勝り、草がすっかり抑えられています。

無農薬・無肥料栽培にむいた「自然農法の種子」はこちらから有料配布できます。
http://www.janis.or.jp/users/infrc/seedservice/index.html

★☆★今月の20~22日に、友人の安曇野地球宿で、★☆★
「ワークキャンプin安曇野」を行います。
うちも受け入れ先農家になったので、↓に紹介されました。
http://azuminoworkcamp.blog38.fc2.com/blog-entry-28.html
http://azuminoworkcamp.blog38.fc2.com/blog-entry-29.html
※ブックマークにも登録しました!!
 ◆◇◆10月14日から始まる冬の家庭菜園講座(NHKカルチャー)のお知らせ◆◇◆
◆◇◆10月14日から始まる冬の家庭菜園講座(NHKカルチャー)のお知らせ◆◇◆
『美味しく簡単にできる無農薬・家庭菜園の法則』
http://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_491207.html
講師: 自給自足Life代表 竹内 孝功
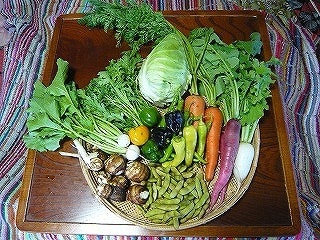
無農薬自然栽培の基本から、毎月育てる野菜をテーマにレクチャーします。
畑の疑問・お悩みにお答えする時間もあります。
10/14-玉ねぎの植え方、サツマイモの収穫・保存、麦で土作り
11/11-来年の畑の準備、野菜の保存の仕方、種の保存の仕方
12/9-有機肥料・補間資材の作り方(クン炭・ボカシ肥)、一年のまとめ(復習)
一日講座(10/3(土)13:30~16:00)は、 こちら↓
コンパニオンプランツで育てるイチゴ栽培
http://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_516004.html

イチゴの他に、ニンニク・ハコベ・ペチュニアを一つのプランターで無農薬栽培で育てます。
もちろん、ミミズも飼います。毎年イチゴプランターを増やしていける持続可能なプラン―栽培法です。
お誘い合わせの上お申込み、よろしくお願いたします。

 。
。昨日は、4年前に研修させていただいた(財)自然農法国際研究開発センターを見学しました。
今回は、職員さんのご都合がつかなかったため、なぜか私が見学を誘導することになりました。
師匠たちの試験栽培をうまく説明しきれないのは承知してもらい友人一行さんと見学しました。

上は、交互栽培の事例です。「生態制御チーム」の試験区です。
左は、青山在来という大豆が育っています。前作は、麦でした。
右は、トマトです。トマトの後に麦を植えます。
つまり、小麦→大豆→トマト→小麦と左と右を毎年交互に栽培することで、
安定した栽培もできます。
また、自給作物である大豆・麦から醤油・味噌・麦の自給もでき、麦ワラもトマトに敷くことができます。

圃場を移動したら、運のいいことに育種課の課長さんがお忙しい中圃場を案内してくれました。

これは、自然農法の育種の一例で、「トマトの自然生え」育種です。
トマトをそのまま土に置き自然に土に還すことによって、
来年桃の花が咲く頃に、トマトが自然に発芽してきます。
育ったトマトの中から食味の良いものを選び、自然と人がお互いに関わりながら育種している事例です。

自然農法センターでは、無農薬栽培で育てやすい種子を育種しています。
写真はキュウリの採種果です。
キュウリは、肥料に依存することなく、自分自身で根がしっかり張れるものを、草と共に育てることで、選抜しています。

こちらは、「自然農法の種」で一番人気の「筑摩野五寸ニンジンです」。
火山灰土のような軽い土壌で、無肥料で育つとても美味しいニンジンです。

こちらは、自然農法センターの田んぼです。
稲は、とてもシンプルで、水と土と太陽で育ちます。
「水稲チーム」では、除草を主に研究しているチームで、
田んぼには稲が勝り、草がすっかり抑えられています。

無農薬・無肥料栽培にむいた「自然農法の種子」はこちらから有料配布できます。
http://www.janis.or.jp/users/infrc/seedservice/index.html

★☆★今月の20~22日に、友人の安曇野地球宿で、★☆★
「ワークキャンプin安曇野」を行います。
うちも受け入れ先農家になったので、↓に紹介されました。
http://azuminoworkcamp.blog38.fc2.com/blog-entry-28.html
http://azuminoworkcamp.blog38.fc2.com/blog-entry-29.html
※ブックマークにも登録しました!!
 ◆◇◆10月14日から始まる冬の家庭菜園講座(NHKカルチャー)のお知らせ◆◇◆
◆◇◆10月14日から始まる冬の家庭菜園講座(NHKカルチャー)のお知らせ◆◇◆
『美味しく簡単にできる無農薬・家庭菜園の法則』
http://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_491207.html
講師: 自給自足Life代表 竹内 孝功
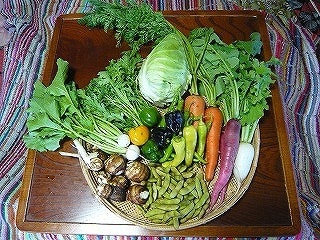
無農薬自然栽培の基本から、毎月育てる野菜をテーマにレクチャーします。
畑の疑問・お悩みにお答えする時間もあります。
10/14-玉ねぎの植え方、サツマイモの収穫・保存、麦で土作り
11/11-来年の畑の準備、野菜の保存の仕方、種の保存の仕方
12/9-有機肥料・補間資材の作り方(クン炭・ボカシ肥)、一年のまとめ(復習)
一日講座(10/3(土)13:30~16:00)は、 こちら↓
コンパニオンプランツで育てるイチゴ栽培
http://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_516004.html

イチゴの他に、ニンニク・ハコベ・ペチュニアを一つのプランターで無農薬栽培で育てます。
もちろん、ミミズも飼います。毎年イチゴプランターを増やしていける持続可能なプラン―栽培法です。
お誘い合わせの上お申込み、よろしくお願いたします。
















 (質問)
(質問) (応答)
(応答)





 ことにしました。
ことにしました。

 。
。















