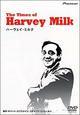★★★★ 2007年/日本 監督/塩田明彦
「目指せ!日本のクリストファー・ノーラン」
「どろろ2」「どろろ3」まで決まっているんですね。何とも壮大な企画です。不気味な予感が漂う冒頭の30分くらいは、とてもいい感じです。やはり、興醒めしてしまうのは、土屋アンナ扮する蛾の妖怪の出来映えのひどさ。「PROMISE」の悪夢再びで頭を抱えました。エンドロールを見ていましたら、複数のVFX担当デザイン事務所とスタッフが出てきます。これは、「1クリーチャー=1デザイン事務所」の分業性ということでしょうか。やはり、エンタメ大作は総合的なタクトを振る力量がモノを言います。いっそのこと、全体のVFXを統括する腕のいい監督を別に置いた方が良いのかも知れません。「ピンポン」「ICHI」を撮った曽利監督あたりがやってくれないものかしら。
そして、戦国時代を思わせる日本が舞台であるならば、やはり「殺陣」シーンのクオリティも、もっともっとあげないといけません。ワイヤーよりもむしろ、チャンバラとしての醍醐味。ここを追求するべきでしょう。ハリウッド大作がアクション監督に力を発揮してもらっているように、これまた担当監督に頑張ってもらわねばなりません。だってね、昨日何気に見ていた「パチンコ・暴れん坊将軍」の15秒CMの方が遙かに殺陣がカッコイイんですよ。これじゃあ、いけません。
そして、音楽。「DEEP FOREST」を思わせるループ系ハウスや、エジプシャンリズムに三味線のアレンジを加えたものなど、無国籍なビートが非常にいい感じです。なのに、なぜか次の対決シーンはフラメンコギターばりばりのラテンサウンド。なんなんだ、この脈絡のなさは。「ダークナイト」や「ワールド・エンド」を手がけるハンス・ジマーばりに音楽だけでも世界観が作られたらなあ…。というわけで、大作ならではの分業制をうまくまとめきれなかった、これに尽きるのではないでしょうか。
しかし、作品全体に流れるムードは決して悪くありません。現代の娯楽大作の潮流ど真ん中である「親殺し」「巡る因果」「血の継承」と言った暗いテーマは、気味の悪い絵作りを得意とする塩田監督にぴったりの素材だと思います。水槽に浮かぶ包帯でぐるぐる巻きにされた赤ん坊など、冒頭の赤ん坊の再生シーンは塩田監督らしさを発揮しています。そして、殺伐とした荒野、セピアトーンの映像。妖怪が出てこないシーンは、十分に世界観を作っている。駄目なところがはっきりしているわけですから、次回はこれを修正すればいい。バットマンシリーズで自分の個性を存分に発揮している、クリストファー・ノーランを目指せばいい。少女の魅力を引き出すのが巧い塩田監督。今後のポイントは、柴咲コウをどう料理するかでしょう。私は次作に期待します。
「目指せ!日本のクリストファー・ノーラン」
「どろろ2」「どろろ3」まで決まっているんですね。何とも壮大な企画です。不気味な予感が漂う冒頭の30分くらいは、とてもいい感じです。やはり、興醒めしてしまうのは、土屋アンナ扮する蛾の妖怪の出来映えのひどさ。「PROMISE」の悪夢再びで頭を抱えました。エンドロールを見ていましたら、複数のVFX担当デザイン事務所とスタッフが出てきます。これは、「1クリーチャー=1デザイン事務所」の分業性ということでしょうか。やはり、エンタメ大作は総合的なタクトを振る力量がモノを言います。いっそのこと、全体のVFXを統括する腕のいい監督を別に置いた方が良いのかも知れません。「ピンポン」「ICHI」を撮った曽利監督あたりがやってくれないものかしら。
そして、戦国時代を思わせる日本が舞台であるならば、やはり「殺陣」シーンのクオリティも、もっともっとあげないといけません。ワイヤーよりもむしろ、チャンバラとしての醍醐味。ここを追求するべきでしょう。ハリウッド大作がアクション監督に力を発揮してもらっているように、これまた担当監督に頑張ってもらわねばなりません。だってね、昨日何気に見ていた「パチンコ・暴れん坊将軍」の15秒CMの方が遙かに殺陣がカッコイイんですよ。これじゃあ、いけません。
そして、音楽。「DEEP FOREST」を思わせるループ系ハウスや、エジプシャンリズムに三味線のアレンジを加えたものなど、無国籍なビートが非常にいい感じです。なのに、なぜか次の対決シーンはフラメンコギターばりばりのラテンサウンド。なんなんだ、この脈絡のなさは。「ダークナイト」や「ワールド・エンド」を手がけるハンス・ジマーばりに音楽だけでも世界観が作られたらなあ…。というわけで、大作ならではの分業制をうまくまとめきれなかった、これに尽きるのではないでしょうか。
しかし、作品全体に流れるムードは決して悪くありません。現代の娯楽大作の潮流ど真ん中である「親殺し」「巡る因果」「血の継承」と言った暗いテーマは、気味の悪い絵作りを得意とする塩田監督にぴったりの素材だと思います。水槽に浮かぶ包帯でぐるぐる巻きにされた赤ん坊など、冒頭の赤ん坊の再生シーンは塩田監督らしさを発揮しています。そして、殺伐とした荒野、セピアトーンの映像。妖怪が出てこないシーンは、十分に世界観を作っている。駄目なところがはっきりしているわけですから、次回はこれを修正すればいい。バットマンシリーズで自分の個性を存分に発揮している、クリストファー・ノーランを目指せばいい。少女の魅力を引き出すのが巧い塩田監督。今後のポイントは、柴咲コウをどう料理するかでしょう。私は次作に期待します。