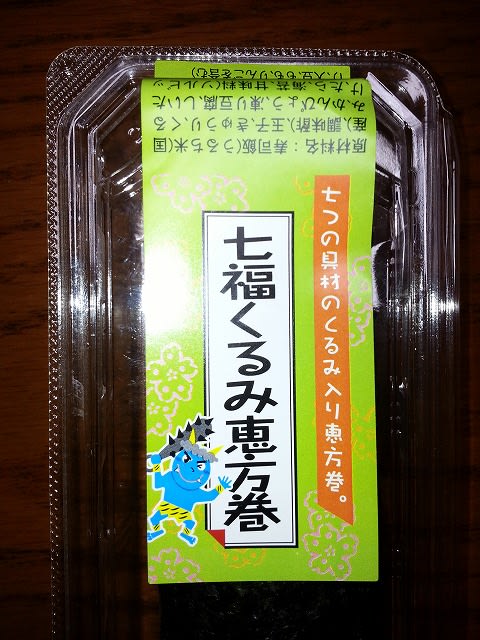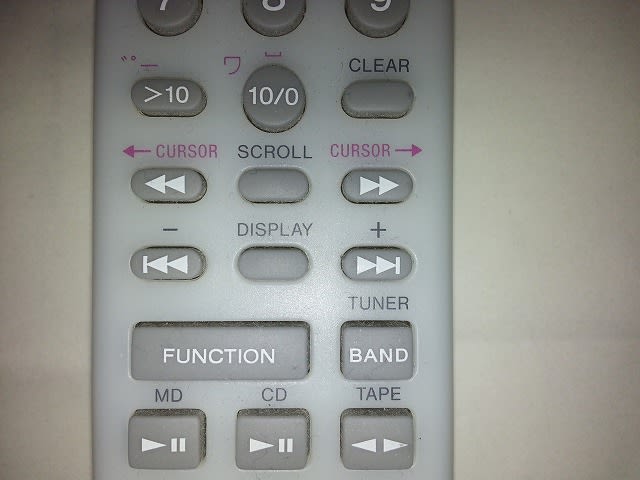今まで不思議に思っていたけど、理由が分からない事は結構あります。
その理由がわかった時は、本当に嬉しく感じます。
先日、とある本を読んでいたら、不思議に思っていたことが氷解しました。
その理由と言うのは、言葉を発音する時の強弱、いわゆるアクセントに関することです。
上越新幹線に乗車して、かなりの回数新潟と東京を往復しました。
その際、停車駅を車内アナウンスをしますが、駅名のアクセントが不思議でした。
例えば「浦佐(うらさ)」です。
車内で自動アナウンスが発音する場合は「う」を強調するアクセントです。
また、車掌が駅名をアナウンスする場合は「う」を強調する人と、「うらさ」全てを強調しない人がいました。
車掌は自分の所属車掌区もアナウンスしますが、私の記憶では「う」を強調する車掌は関東の車掌区に所属する人、全く強調しない車掌は新潟の車掌区に所属する人でした。
完璧に調査をしたわけではありませんが、私の周りでは私を含めて「うらさ」を発音する時には、全て強調しません。
私の疑問を解消してくれた本は、以下の本です。
「日本語ウォッチング(井上史雄著 岩波書店 1998)」
以下は引用です。
共通語アクセントのとのもう一つの規則性は、聞きなれない外来語や無意味な音連続は、「うしろから三拍目までが高く発音される」という「マイナス3」の規則性である。
無意味なことばを読ませると、「おいうえお」とか「ぼんとかあ」「わいろく」「ねがめ」「らしは」のように、後ろから三拍目までが高く発音されることが多い(一拍目ははじめに述べた規則性があるから低く始まる)。二拍の語はうしろから三番目というのがありえないから、「もひ」「らか」のように頭高になる(無意味語の例は、かなをひっくり返して作った。念のため)。 (P182)
さて、一九七〇年代のことだが、雑談のおりに、若い研究仲間が、「オーケストラをやる人は「ドラム」と平板に発音するんですよ」と教えてくれた。標準的なアクセントでは、楽器の「ドラム」は「テレビ」と同じで、最初だけが高く発音されて、すぐに下がる。これを若い人は「タバコ」のアクセントとと同じように、「ドラム」を発音するというのだ。面白いと思って、その後気をつけてウォッチングを試みると、さまざまなことばが平板アクセントで発音されている。しかも、その人が得意な分野の単語のようだ。バイクに乗る人は「バイク」と言うし、コンピュータにくわしい人は「ファイル」と言う。その後はメモ用紙を持ち歩いて、気づいたたびに記していた。ウォッチングによると平板アクセントを使う人は、その道の通というか専門家に多そうなので「専門家アクセント」と名づけた。講義でふれると、学生が興味をもって、実例を教えてくれる。「そういえば」と、身近な例に思いあたるらしい。学年末レポートで、自分の属するサークルの用語の平板化について書く学生もときどき出る。体育系のスポーツ用語でも文化系の専門用語でもアクセントの平板化が起きている。 (P168-169)
現在の外来語の「専門家アクセント」は、実は地名をはじめとした固有名詞の平板化ともからむ。東京の地名は平板アクセントが比較的多いことは指摘がある。金田一春彦氏によれば東海道線の駅名のうち「しながわ」「よこはま」をはじめとして「おだわら」までは平板、「あたみ」からが頭高になる。東京人には親しい地名が平板化するので、アクセントから地元意識の境目が読み取れるのだそうだ。 (P179)
アクセントが平板化するさらに根源の理由は、平板型の方が起伏型よりいろいろな点で楽な事がある。言葉の省エネに結びつくのだ。
まず実際に発音するときに、平板型のほうが簡単である。共通語のアクセントでは、どこかで急に下ることが単語の区別に重要な働きをするのだが、平板アクセントでは、この急な下がり目がない。サイレンの音と同じように、最初高くなり、スイッチが切られると、後は最後に向かってゆるやかに下る。車でいえば、ゆっくりアクセルを踏みこんで発進し、あとはアクセルから足を離してゆっくりと停止するような発音が、平板アクセントなのだ。平板アクセントを発音するには、脳から声帯へのアクセントについての指令は、ごく自然な高さの変動で発音せよという指示が一度あればよい。 (P183-184)
「うらさ」のアクセントへ戻ると、私を含めて新潟県に住んでいる人は「うらさ」は親しい地名です。
したがって「う」にアクセント置かずに、平板に発音して当たり前ということになります。
東京の人にとっては「うらさ」は地元意識に含まれない地域ですから、「マイナス3」の法則で「う」にアクセントを置いて発音することになります。
まあ、これは仮説ですから正解かどうかは分かりませんが、私は腑に落ちました。
私の疑問を氷解させてくれた本は、以前ブックオフで古本を漁っていたとき、何気なく持ち帰った本です。
まさか、こんな有用な情報が書かれていたとは、不思議な縁です。
108円の投資は安かったかなと思います。