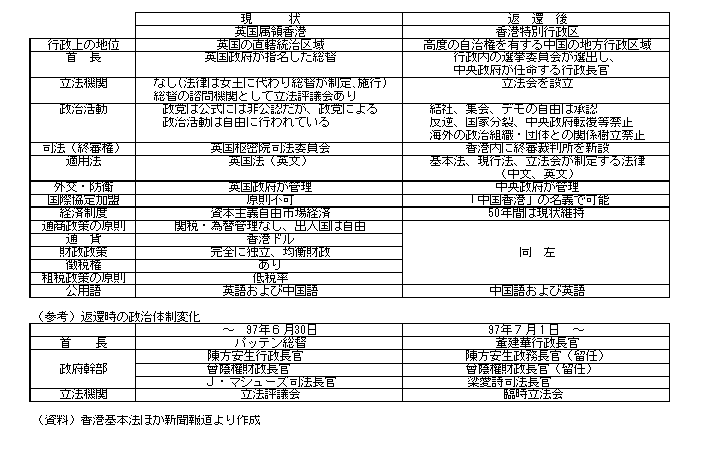【社説②】:教員の性暴力 被害防ぐ一層の対策を
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説②】:教員の性暴力 被害防ぐ一層の対策を
教員による児童生徒への性暴力が後を絶たない。児童生徒へのわいせつ行為について、道教委が2019年度に出した懲戒処分は9件と前年度からほぼ倍増した。
性暴力は、被害者の心身に長い期間、深刻な影響を及ぼす。まして教員が加害者となれば、被害者が受ける苦難は想像を絶する。
文部科学省は懲戒免職された人が再び教壇に立たないようにする仕組みを強化する。採用時に参照できる教員の処分歴の閲覧期間を現行の3年から40年に延ばす。
ただ、これだけでは子供を守る対策として十分とは言えない。
教員への指導を徹底する一方、被害者が声を上げやすい仕組みを整える必要がある。子供たちが安心して学べる環境を早急に整備しなければならない。
文科省によると、18年度にわいせつ行為やセクシュアルハラスメントなどで処分された公立学校の教職員は過去最多の282人に上った。このうち半数近くのケースで教え子が被害者となっている。
文科省は、懲戒免職で教員免許を失った教員の処分歴を閲覧できるシステムを構築し、教育委員会などに情報を提供している。
だが、閲覧可能な期間が短く、処分歴があるにもかかわらず採用された例もあったため、来年2月から閲覧期間を40年に延長する。
教員免許を再取得できるまでの期間を3年から5年に延ばすよう法改正の検討も始めた。
適格性を欠いた人材を採用時に判別し、教育現場への入り口で食い止める一定の効果はあろう。
ただ、処分歴を長期間保持すれば、罪を犯した人の社会復帰の道を閉ざし、人権を侵害しかねない。情報利用の権限を極力絞るなど厳格な運用が欠かせない。
閲覧期間の根拠について、文科省は刑法の有期刑の上限などを参照したとするが、これが妥当なのか議論の余地もあるだろう。
現場の対策も重要だ。教員の性暴力は授業や部活など個別の指導で発生する例が多い。密室性が高くなる場面では複数の教員が関わるといった対応が必要になる。
児童生徒が自らの心身を守り、被害を受けた際には適切に対応できるよう、基本的な知識を伝える性教育も忘れてはならない。相談窓口の拡充も重要だ。
学校は社会と隔絶された空間ではない。教員による性暴力が相次ぐのは、社会の病理の反映とも言えよう。子供が健やかに育つためにはどうするべきか。社会全体で真剣に考えなければならない。
元稿:北海道新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】 2020年09月28日 05:00:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。














 菅義偉首相(2020年9月14日撮影)
菅義偉首相(2020年9月14日撮影)





 航空・旅行アナリストの鳥海高太朗氏
航空・旅行アナリストの鳥海高太朗氏  閑散とした7月の羽田空港国際線チェックインカウンター。今も閑散としている(鳥海氏提供)
閑散とした7月の羽田空港国際線チェックインカウンター。今も閑散としている(鳥海氏提供) 閑散とした7月の羽田空港国際線出発ロビー(鳥海氏提供)
閑散とした7月の羽田空港国際線出発ロビー(鳥海氏提供) 免税店が軒並みシャッターを下ろし、閑散とした7月の羽田空港国際線出発ロビー。今も一部の免税店しか開いていない(鳥海氏提供)
免税店が軒並みシャッターを下ろし、閑散とした7月の羽田空港国際線出発ロビー。今も一部の免税店しか開いていない(鳥海氏提供) 免税店が軒並みシャッターを下ろし、閑散とした7月の羽田空港国際線出発ロビー。今も一部の免税店しか開いていない(鳥海氏提供)
免税店が軒並みシャッターを下ろし、閑散とした7月の羽田空港国際線出発ロビー。今も一部の免税店しか開いていない(鳥海氏提供) 免税店が軒並みシャッターを下ろし、閑散とした7月の羽田空港国際線出発ロビー。今も一部の免税店しか開いていない(鳥海氏提供)
免税店が軒並みシャッターを下ろし、閑散とした7月の羽田空港国際線出発ロビー。今も一部の免税店しか開いていない(鳥海氏提供)