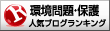2019年9月6日、日本交渉協会の第43回燮会に参加してきました。燮会は交渉アナリスト1級会員のための交渉勉強会です。

いつもの通り、二部構成の第一部は「交渉理論研究」。第8回は意思決定の理論である「決定分析」の三回目。今回は平日開催で土曜開催の燮会よりも時間が短かったため、理論上意思決定の基準となる「貨幣価値」、意思決定者の選好強度を反映した「望ましさの価値」、さらに意思決定者のリスク態度を反映した「効用価値」についてお話ししました。
とりわけリスク態度については、人は自分を標準的だと見なしていることが多いため、口頭の説明だけでは分かりにくい部分もあったかもしれません。しかし、実際にあるリスクの例に対してそれを取るかどうかの挙手を求めたところ、今回参加された皆さんは驚くほど(「驚く」というのも僕の主観ですが)リスク回避的であることが明らかとなり、分かりやすい例になったのではないかと思います。
次回は「意思決定にあたり、人は効用最大化を目指す」という「期待効用理論」に対する様々な批判を取り上げる予定です。

第二部。今回の講師は1級会員で弁護士専門コンサルタントの向展弘さんと、同じく1級会員で最近メディアの露出も大変多い、弁護士の指宿昭一さん。「司法現場での交渉学活用法」と題し、司法の現場に交渉学を持ち込んで成功した事例と、それによって弁護士としての業務効率も改善した実績についてお話しいただきました。向さんは、2012年6月の「第5回燮会」以来の登壇になるかと思います。
そもそも世界で初めて交渉学の講義を始めたハーバード大学において、交渉学は主にロースクールとビジネススクールを母体に発展してきました。そうした背景に加え、一般的にも弁護士は相手側弁護士や裁判官、さらには裁判員(陪審員)と丁々発止の交渉を繰り広げる、「交渉のプロ」のイメージがあります。確かに経験的にはその通りなのですが、実はそうした弁護士が交渉学を体系的に会得し、活用しているかと言えばそうでもないようなのです。少なくとも日本の司法界においては、交渉に関する教育はほとんど行われていないというのが実態だそうです。実際、日本の弁護士が実務において失敗したと感じるのは、法律面のことよりもむしろ交渉学を始めとするコミュニケーションに起因することが多いのだとか。
指宿さん自身、交渉アナリストの古参である向さんとの交流を通じ、またご自身が交渉学を学ばれ、実務に応用した過程を通じて、「弁護士こそ交渉学を学ぶべきである」との思いを強くされたそうです。とりわけ相手とのWin-winを指向する「統合型交渉」は、時間とコストをかけて勝ち負けを争う訴訟よりも、訴訟前の和解を重視する司法界の世界的な潮流の中で、極めて親和性が高いということです。今回は、まずそのような交渉学を用いた成功事例を三つほどお話しいただきました。
事例1は、相手側との価値交換を通じて原告側は合理的な範囲で和解金を上げることに成功し、被告側は逮捕・勾留を免れたというものです。ポイントは、相手側弁護士さえも味方につけ、被告側にとって真に重要な価値を明らかにしたことです。「統合型交渉」の条件の一つは、「お互いの価値に相違がある」ということです。この価値の相違を利用し、互いの価値を交換することでより良い結果を創造することを「価値交換」といいます。特に、こちら側にとって価値の低いものが、相手側にとって高い価値を持っているような場合、交換によってより高い付加価値を創造することができます(不等価交換)。また、この事例では、価値交換によってわずか3日で解決したという、費用面でも、お互いの精神的負担の面でも好影響をもたらす結果となりました。
事例2は、「分配型交渉」の基本である「出発点」、「目標点」、「留保点」を明らかにすることによって、望ましい結果を計画的に導くことができたというものです。しかし、この事例では問題点が2つありました。一つ目は、あくまで目標点に到達するために設定した出発点に、設定したクライアント自身がアンカリングされてしまったという点です。アンカリング(アンカー効果=係留効果ともいいます)とは、あたかも係留された船のように、意思決定が初期値(出発点)に縛られてしまうことを言います。この効果は通常、初期値を提示された側が影響を受けるとされるのですが、実はこの事例のように提示した側が影響を受けることもあります。諺に言う「ミイラ取りがミイラになる」」現象です。
二つ目は、感情の問題です。交渉理論に「コンフリクトのエスカレーション」というものがあります。意思決定者が本来の目的達成よりも勝ち負けに固執してしまう心理的な現象です。『孫子』(作戦篇)に「兵は拙速を聞くも、未だ巧の久しきを睹ざるなり」(たとえ勝ち方に不十分な点があったとしても、目的を達したならば、速やかに終結に導くのが良策である)という言葉がありますが、人は頭では合理的に考えることができても、感情的な問題で不合理な決定をしてしまうことが多々あるのです。また、このようなクライアントの不合理な態度に、弁護士も感情的に反応してしまうという落とし穴があります。この事例においては、感情的な問題に対して、あたかもカウンセリングを行うような要領でクライアントに認知の転換を図ることができたことが成功に結び付きました。自らの感情のコントロールについては、「第15回ネゴシエーション研究フォーラム」の「怒り」に関する研究が役立ちそうです。
事例3も、感情の問題です。訴訟は金銭的、時間的、精神的負担が大きいので、クライアントは訴訟が長期化すると訴訟そのものが目的となってしまい、早期の和解によって訴訟が終わってしまうことを逆に不安に思うようになることがあると言います。また、クライアントが常に合理的、理性的であるとは限りません。感情の問題のみならず、情緒のバランスを崩してしまう場合もあります。この事例でもクライアントはいくつもの不合理な妄想に駆られていました。このような場合、合理的な説得は禁物です。クライアントに寄り添い、粘り強く傾聴と共感を続けるしかありません。
交渉は交渉テーブルの向こう側にいる相手とだけ行う(外部交渉)ものではありません。むしろ交渉者の背後にいるクライアントや複数の利害関係者の合意を取り付ける内部交渉の方が交渉に占める割合が大きい場合も多々あります。この事例も、外部交渉以前に内部交渉の難しさを示していると言えます。この事例では、結果的にクライアントを説得するのに相手側代理人や裁判官までもが協力する形となりました。
さて、弁護士が交渉学を身に着けることには、上記のような問題解決に資するのみならず、弁護士の事業そのものにも様々な好影響があるようです。例えば、
1.迅速な解決→クライアントの満足向上、資金繰り改善につながる
2.付加価値の創造→クライアントの満足・信頼向上
3.2により、紹介やリピートの増加→収入増
4.ストレスと時間の軽減
5.弁護士としての成長
などを指宿さんは挙げておられました。こうした交渉学を会得することのメリットは、弁護士業務のみならず広くビジネスに携わる我々に共通することではないかと思います。それを大変分かりやすい事例で示してくださったことは、我々にとって大きな刺激となりました。
繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした