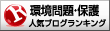3月2日、
日本交渉協会主催の第14回ネゴシエーション研究フォーラムに参加してきました。

今回のテーマは「ペルー日本大使公邸人質事件を通じた海外危機管理~予備的対応と関係者の実際の事件中の対応について」。お話しいただいたのは、海外職業訓練協会国際アドバイザー、株式会社JTB LAPITAアドバイザー、日本ブラジル中央協会常務理事の酒井芳彦氏。ご記憶の方もいらっしゃるかもしれません、1996年「ペルー日本大使公邸人質事件」が起こった時、ペルー味の素の社長として人質の一人となっていた方です。約3時間半にわたり、事件の渦中におられた生々しいお話を伺うことのできた大変貴重な機会でした。
事件の記憶がない方のために簡単に整理しますと、1996年12月17日に、ペルーの首都リマで起きた、テロリスト(MRTA)による日本大使公邸襲撃・占拠事件のことです。1997年4月22日のペルー軍特殊部隊による突入、人質解放まで丸4カ月かかり、人質だったカルロス・ジュスティ最高裁判事と特殊部隊隊のファン・バレル中佐、ラウル・ヒメネス中尉が死亡、MRTAは14名全員が死亡しました。
さて、膨大なお話を全てご紹介することはできませんので、ここでは話題を
1.事件の経過
2.監禁生活の中で
3.日本としての事件の教訓
4.ペルー味の素の当時の危機管理対策
以上の4点に絞って整理したいと思います。
1.事件の経過
1996年12月17日、日本大使公邸ではおよそ10年ぶりとなる天皇誕生祝賀会が催され、政府・民間からの招待客640名がいました。20:20、爆音と共に隣家からトゥパク・アマル革命運動(MRTA)のテロリスト14名が公邸内に侵入、公邸を占拠しました。テロリスト側の要求は当時のフジモリ大統領の社会・経済政策の変更、投獄されている仲間の釈放(リーダーであるネストル・セルパの妻ナンシーも含む)、帰路移動の保証、そして身代金でした。
テロリスト側も14名で640名の人質をコントロールすることができないため、21:50、まず女性全員と70歳以上の男性、使用人、226名が解放されます。その後さらに解放され、最終的に残された人質は72名でした。
リマは南半球なので、12月~2月は日中の気温が27度位まで上がります。しかし、公邸占拠と同時に電気、水道は遮断され、飲料水の差し入れは3日後、弁当などの本格的な差し入れは2週間後からだったそうです。最初の二日目は1枚の食パンを5人で分け、3日目は乾パン1缶を5人で分けたそうです。トイレも使えず、簡易トイレが2週間後から。当然シャワーはなし。携帯電話は没収され、小型のマットレスが搬入されたのは1月30日のこと。それまでは床で雑魚寝だったそうです。衛生環境の悪化からネズミが繁殖していたとか。
ペルー政府とMRTAとの接触は12月28日から。2月1日には、武力解決を指向するペルー政府と平和的解決を望む日本政府との間で首脳会談がカナダのトロントで行われました。2月11日から3月10日にかけては、仲介役のシプリアーニ大司教らから成る保証人委員会とMRTAとの間で10回にわたる予備的会議が行われましたが、進展なく終わりました。
フジモリ大統領に平和的解決という選択肢はあったのでしょうか?結果から見ると、初めから武力制圧しか選択肢になかったように思われます。公邸に侵入するための地下トンネルを最終的には9本掘り、陸軍基地内に実物大の大使公邸模型を2カ月で作り、特殊部隊の訓練を繰り返しました。突入時の手際の良さも、テロリストがいつ、どこに何人いるか情報収集していたことが窺われます。公邸が占拠されてすぐに電気・水道をストップしたのもトンネルを掘るための準備だったと考えられます。
1990年に大統領に就任したフジモリ大統領は、当時から強権的という批判はあったものの、就任時7,650%あったインフレ率を事件の起こった1996年には11.8%にまで鎮めました。特にテロ撲滅には強い態度を示し、1990年に2,779件あったテロ発生件数は1996年には589件にまで減少しています。そのような大統領がこの場合だけテロリストと平和的解決を模索したりするでしょうか?交渉理論の観点で言えば、意思決定は、当事者の持っている価値に目的および目的達成のための手段が規定されるということです。それを日本政府が知らないはずはなく、建前として平和的解決を打ち出しながらも、実際には時間稼ぎをしていたと考えるのが妥当ではないでしょうか。そもそも交渉する意思が双方にない限り、交渉は成立しません。
2.監禁生活の中で
占拠から2週間が過ぎたあたりからの生活は非常に規則正しいものだったそうです。人質が企業のトップや外交官などであったことから、比較的統率はとれていたそうですが、極限状態にあって非公式に現れるリーダーのような者はいなかったようです。外部からの情報がなく、いつ事態が急変するか分からない不安、外出できないことによる運動不足、前述のように日中の暑さといった中で、大切なことは「絶対に死なない」という強い気持ちだったそうです。それでも14畳程度の部屋に11人が監禁されている状態が長く続くというのは、自由、尊厳、プライバシーが無いという苛烈な状況であったことに変わりはありません。
家族との手紙はスペイン語のみ許され、MRTAの検閲の後、国際赤十字を通じ渡されますが、家族の支えは大きかったようです。実物を見せていただきましたが、酒井氏が包装紙などを剃刀の刃で切って作った、娘さんに宛てたバースデー・カードが印象的でした。

誘拐事件や監禁事件などの被害者が、犯人と長い時間を共にすることにより、犯人に過度の連帯感や好意的な感情を抱く、ストックホルム症候群という心理現象があります。MRTA側は人質に対し、「反抗しなければ殺さない」という声明を出していたようですが、それでも彼ら自身の身が脅かされるような事態になれば、どうなるか分かりません。人質になっていた民間企業のトップの方たちは、おおむねスペイン語圏での駐在経験が長く、スペイン語ができたことから、彼らとの挨拶から始め、ピアノの弾き方を教える、オセロゲームを教える、差し入れられた日本の歌のCDを一緒に聞くなどしたそうです。彼らの中にも自分のことを語り始める者がいて、中には「この一件が片付いたら日本で警察官になりたい」とか「海軍に入隊したい」という者もいたそうです。14名も全てがプロのテロリストという訳ではなく、貧しい山岳地帯で生活のために加わったという者が少なくないようでした。中には年端も行かぬ女性が2名含まれていました。
3.日本としての事件の教訓
当時、日本大使公邸がテロリストの標的となったのには、日本のこれまでの対テロリストに対する交渉態度、公邸の危機管理体制の甘さがあったと言わざるを得ません。当時卒業間際の学生だった僕も報道を見て感じたことですが、大使公邸は日本の主権下であるにも関わらず、憲法の制約により、その無力を世界に晒しました。その後、この事件を教訓として、危機管理センターの設置、在外公館の防犯体制強化、テロ防止の国際協力、SATの増員、除法処理能力の充実などが図られたようですが、20年経った現在でも、人質事件が起こるたび、この事件の教訓である「危機管理」という視点での議論はなされているでしょうか?
4.ペルー味の素の当時の危機管理対策
1982年、メキシコの金融危機に端を発した債務危機は、南米諸国を深刻な経済危機に追い込みました。ペルーも1987年頃から急速に治安が悪化、経済も崩壊状態にありました。味の素のペルー進出は早く、1968年のことです。酒井氏がいた1996年当時、ペルー味の素の本社および工場がどんなテロ対策を施していたのか、最後に一端を箇条書きでご紹介したいと思います。
・塀に囲まれた本社入口は、人が二人並んで通れるかどうかの大きさ。高い塀の上にはさらに高い壁が築かれ、外から爆弾を投げ込んだり、狙撃しても弾き返せるようになっている。
・玄関わきの受付は防弾ガラス。内外の監視カメラ、監視塔の設置。
・社用車は厚さ3㎜の防弾ガラス、爆弾除けのため上下に鉄板を貼り、装備だけで250kgsの重さがある。
・営業車には社名が分かる表示をしない、後部ガラスも中の商品が見えないように覆いがしてある(現在は治安が改善し、この営業車はない)。
・工場正門は車両爆弾が突っ込めないよう、鉄のバリケードを設置。
・鉄の門は数m行ったところにもう一つ鉄の門がある。
・車両が入る前の爆弾チェック。
・通勤ルートの変更、電話の録音。
・秘書とは本名で通話しない。
・自宅を含めた24時間警備
グローバル化が進む中、海外勤務は日本人にとって一層身近なものになっています。危機管理の徹底と「自律自衛」の覚悟が求められると、酒井氏もおっしゃっていました。
繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした