後で分かったことですが京都で37.5度を記録したこの日、正午をまわり朝ろくに食べずに横浜を出てきたこともあって少々疲れてきました。本丸から二の丸を出るまでに巡ったところをご紹介していきます。
5.帯郭櫓(腹切丸)

南側の堀を渡ってくる敵を攻撃するための櫓です。曲輪内の井戸や櫓の内部が切腹をする場を連想させることから俗称腹切丸と呼ばれています。勿論こんな場所で切腹が行なわれたはずもなく、あくまで俗称です。

6.お菊井戸

怪談話『播州皿屋敷』のヒロインであるお菊が責め殺され投げ込まれたと伝えられる井戸です。もちろんこれは作り話で、『播州皿屋敷』自体、姫路城の第9代城主小寺則職と家臣青山鉄山の対立を元に作られたものと言われています。
7.るの門

孔門または埋門と呼ばれる門で、菱の門から右側に天守に向かう途中の道からそれたところに隠れるように作られており、抜け道ではないかといわれています。有事にはここを埋めて塞ぐと考えられたことから埋門(うずみもん)とも呼ばれています。姫路城独特のものです。
8.西の丸長局(百間廊下)

菱の門から入ってすぐ左側を登っていくと二の丸です。徳川秀忠の娘でもともと豊臣秀頼に嫁ぎ、大阪夏の陣の後、姫路城4代目城主となる本多忠政の長男本多忠刻に嫁いだ千姫に仕えた侍女たちが居たところで、その名の通り大変長い建物です。

内部は3階にわたり延々と廊下、片側に六畳間位の部屋がいくつも並んでいます。ただ侍女が住むだけならばこのような漆喰の頑丈な建物である必要はないはずですが、これは元々実戦を想定しての渡櫓だったのからではないかと思います。というのは、ここからわずかの距離には男山があり姫路城を攻略する際にはまずこの男山が戦略上重要拠点となったであろうと考えられるからです。
9.化粧櫓

西の丸長局の一番右端は櫓になっており、ここだけが座敷になっています。千姫は男子に恵まれなかった上、夫の忠刻も病気がちだったため()、ここから男山にある男山八幡神社を拝み男子誕生と夫の快癒を祈ったと言われています。しかし、その甲斐も空しく結局忠刻は31歳で急逝、本多家は弟が跡を継ぐことになりました。
このとき千姫が休息所としたのがこの櫓で、化粧櫓と呼ばれていました。これは千姫が本多忠刻に嫁いだ際、徳川秀忠が与えた化粧料10万石でこの櫓を建てたからだと言われています。
繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした
よろしければクリックおねがいします!
↓
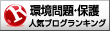
5.帯郭櫓(腹切丸)

南側の堀を渡ってくる敵を攻撃するための櫓です。曲輪内の井戸や櫓の内部が切腹をする場を連想させることから俗称腹切丸と呼ばれています。勿論こんな場所で切腹が行なわれたはずもなく、あくまで俗称です。

6.お菊井戸

怪談話『播州皿屋敷』のヒロインであるお菊が責め殺され投げ込まれたと伝えられる井戸です。もちろんこれは作り話で、『播州皿屋敷』自体、姫路城の第9代城主小寺則職と家臣青山鉄山の対立を元に作られたものと言われています。
7.るの門

孔門または埋門と呼ばれる門で、菱の門から右側に天守に向かう途中の道からそれたところに隠れるように作られており、抜け道ではないかといわれています。有事にはここを埋めて塞ぐと考えられたことから埋門(うずみもん)とも呼ばれています。姫路城独特のものです。
8.西の丸長局(百間廊下)

菱の門から入ってすぐ左側を登っていくと二の丸です。徳川秀忠の娘でもともと豊臣秀頼に嫁ぎ、大阪夏の陣の後、姫路城4代目城主となる本多忠政の長男本多忠刻に嫁いだ千姫に仕えた侍女たちが居たところで、その名の通り大変長い建物です。

内部は3階にわたり延々と廊下、片側に六畳間位の部屋がいくつも並んでいます。ただ侍女が住むだけならばこのような漆喰の頑丈な建物である必要はないはずですが、これは元々実戦を想定しての渡櫓だったのからではないかと思います。というのは、ここからわずかの距離には男山があり姫路城を攻略する際にはまずこの男山が戦略上重要拠点となったであろうと考えられるからです。
9.化粧櫓

西の丸長局の一番右端は櫓になっており、ここだけが座敷になっています。千姫は男子に恵まれなかった上、夫の忠刻も病気がちだったため()、ここから男山にある男山八幡神社を拝み男子誕生と夫の快癒を祈ったと言われています。しかし、その甲斐も空しく結局忠刻は31歳で急逝、本多家は弟が跡を継ぐことになりました。
このとき千姫が休息所としたのがこの櫓で、化粧櫓と呼ばれていました。これは千姫が本多忠刻に嫁いだ際、徳川秀忠が与えた化粧料10万石でこの櫓を建てたからだと言われています。
繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした

よろしければクリックおねがいします!
↓















































