都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「チンギス・ハーンとモンゴルの至宝展」 江戸東京博物館
江戸東京博物館(墨田区横網1-4-1)
「チンギス・ハーンとモンゴルの至宝展」
2/2-4/11
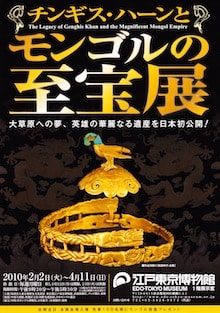
中国・内モンゴル自治区博物院の所蔵品にてモンゴルの歴史、文化を概観します。江戸東京博物館で開催中の「チンギス・ハーンとモンゴルの至宝展」 の特別内覧会へ行ってきました。
「チンギス・ハーン」と聞くと、かの英雄が生きた時代、13世紀前後のみに焦点を当てているのかと思いがちですが、実はそれ以前、古くは紀元前4世紀に始まったモンゴルの歴史を辿るスケールの大きな展覧会です。よって考古遺物、民族衣装、さらには仏像他、チンギス・ハーン云々の他の作品も無数に紹介されています。(出品リスト)全体としてはやや地味ではありますが、次々と時代を超えて展開していく文物に、まさに「大草原への夢」(ちらしより引用)を見るような思いがしました。
 (会場風景)
(会場風景)
なお展示では各時代毎にモンゴル文化を紹介していましたが、ここはあえてもっと簡潔に、私の思うみどころをジャンル別に分けてみました。ご鑑賞の参考になれば幸いです。
1.考古青銅器
中国では戦国時代にあたる頃、モンゴルでも青銅器文化が栄えていました。展示でも多数、青銅器の飾り板の他、短剣などが紹介されています。

「青銅らい」(戦国時代) 「ち」と呼ばれる空想上の動物を象った把手が特徴的です。

「青銅製馬面飾り」(戦国時代) 騎馬民族で知られるモンゴル族ですが、彼らの用いた青銅による馬面の飾りものも展示されていました。
2.金製工芸品
華やかな金細工はモンゴル文化でも富と権力の象徴とされています。時代を問わず、時に細かな意匠の施された金の工芸品はやはり目を見張るものがありました。

「黄金のマスク」(遼代) 当時の皇女の婿の顔に被せてあったというマスクです。一際目立つ作品です。

「銀鍍金冠」(遼代) 16枚の銀板に鍍金した冠です。遼の王が使っていたものとのことですが、その図案には中国の道教の影響も色濃く滲み出ているとの記載がありました。

「金製龍紋はこ」/「冊封鳳文宝ろくばこ」(清代) こちらは清代の金製の大きな箱です。貴族の婦人のアクセサリー入れなどに使われていました。
3.楽器
音楽ファンにとっては、各地域の楽器にも注視すべき面があります。有名な馬頭琴の他、関わりのあったチベット仏教のクラリオンなども出品されていました。

「モンゴル琴」(清代) モンゴル族の伝統的な楽器です。表面には12本の弦が張られていました。中の画にも注目です。

「龍紋彫刻馬頭琴」(清朝) モンゴルで最も有名なのはこの馬頭琴ではないでしょうか。会場では実際にその音色を確かめることも出来ました。(作品の隣にあるボタンを押すと録音が再生されます。)これは嬉しい配慮です。
4.民族衣装

展示で最も美しいセクションが、主に清代に用いられたモンゴルの民族衣装を並べたコーナーに他なりません。

「祭事用龍ほう」(清代) チャムと呼ばれた仮面舞儀礼の際に使われた服です。8匹の龍が刺繍されています。

「大威徳金剛の面」(清代) 同じくチャムの際に使われた巨大なお面です。非常に奇抜な意匠でした。
5.王座

その民族衣装に並び、展覧会最大のハイライトに位置づけられるのが、清代の王の用いていた文字通りの王座です。また佩刀、帽子など、彼らの権勢を伝えるような装飾品も登場していました。

「龍が彫ってある王座」(清代) 堂々たる姿をした清代のモンゴルの長の王座です。金も施された細部の意匠はもとより、手すりの鹿角が強烈な存在感を見せつけていました。

「ルビー装飾の親王の帽子」(清代) 赤い糸で装飾された上にルビーが輝いています。王の冬にかぶる帽子とのことでした。

「錯金龍紋佩刀」(清代) 見事な金の象嵌が施されています。鞘には蜥蜴の皮が張られていました。
ちなみにこれらの文物は殆どが日本初公開だそうです。中国はもとより、時にチベットやインドとの交流を踏まえて花開いたモンゴル文化を知る絶好の機会であることは間違いありません。
なおちらし表紙に美しい金の飾り物が掲載されていますが、そちらについては別記事でもまとめてあります。
「鷹形金冠飾り」 江戸東京博物館(チンギス・ハーンとモンゴルの至宝展)
 (展示風景)
(展示風景)
伺った話によれば比較的、人出は緩やかだとのことでした。あまりストレスなく楽しめるのではないでしょうか。また会期中は全日、先着100名にモンゴル岩塩がプレゼントされます。
4月11日まで開催されています。
注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。
「チンギス・ハーンとモンゴルの至宝展」
2/2-4/11
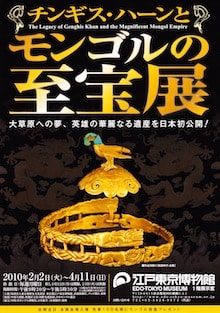
中国・内モンゴル自治区博物院の所蔵品にてモンゴルの歴史、文化を概観します。江戸東京博物館で開催中の「チンギス・ハーンとモンゴルの至宝展」 の特別内覧会へ行ってきました。
「チンギス・ハーン」と聞くと、かの英雄が生きた時代、13世紀前後のみに焦点を当てているのかと思いがちですが、実はそれ以前、古くは紀元前4世紀に始まったモンゴルの歴史を辿るスケールの大きな展覧会です。よって考古遺物、民族衣装、さらには仏像他、チンギス・ハーン云々の他の作品も無数に紹介されています。(出品リスト)全体としてはやや地味ではありますが、次々と時代を超えて展開していく文物に、まさに「大草原への夢」(ちらしより引用)を見るような思いがしました。
 (会場風景)
(会場風景)なお展示では各時代毎にモンゴル文化を紹介していましたが、ここはあえてもっと簡潔に、私の思うみどころをジャンル別に分けてみました。ご鑑賞の参考になれば幸いです。
1.考古青銅器
中国では戦国時代にあたる頃、モンゴルでも青銅器文化が栄えていました。展示でも多数、青銅器の飾り板の他、短剣などが紹介されています。

「青銅らい」(戦国時代) 「ち」と呼ばれる空想上の動物を象った把手が特徴的です。

「青銅製馬面飾り」(戦国時代) 騎馬民族で知られるモンゴル族ですが、彼らの用いた青銅による馬面の飾りものも展示されていました。
2.金製工芸品
華やかな金細工はモンゴル文化でも富と権力の象徴とされています。時代を問わず、時に細かな意匠の施された金の工芸品はやはり目を見張るものがありました。

「黄金のマスク」(遼代) 当時の皇女の婿の顔に被せてあったというマスクです。一際目立つ作品です。

「銀鍍金冠」(遼代) 16枚の銀板に鍍金した冠です。遼の王が使っていたものとのことですが、その図案には中国の道教の影響も色濃く滲み出ているとの記載がありました。

「金製龍紋はこ」/「冊封鳳文宝ろくばこ」(清代) こちらは清代の金製の大きな箱です。貴族の婦人のアクセサリー入れなどに使われていました。
3.楽器
音楽ファンにとっては、各地域の楽器にも注視すべき面があります。有名な馬頭琴の他、関わりのあったチベット仏教のクラリオンなども出品されていました。

「モンゴル琴」(清代) モンゴル族の伝統的な楽器です。表面には12本の弦が張られていました。中の画にも注目です。

「龍紋彫刻馬頭琴」(清朝) モンゴルで最も有名なのはこの馬頭琴ではないでしょうか。会場では実際にその音色を確かめることも出来ました。(作品の隣にあるボタンを押すと録音が再生されます。)これは嬉しい配慮です。
4.民族衣装

展示で最も美しいセクションが、主に清代に用いられたモンゴルの民族衣装を並べたコーナーに他なりません。

「祭事用龍ほう」(清代) チャムと呼ばれた仮面舞儀礼の際に使われた服です。8匹の龍が刺繍されています。

「大威徳金剛の面」(清代) 同じくチャムの際に使われた巨大なお面です。非常に奇抜な意匠でした。
5.王座

その民族衣装に並び、展覧会最大のハイライトに位置づけられるのが、清代の王の用いていた文字通りの王座です。また佩刀、帽子など、彼らの権勢を伝えるような装飾品も登場していました。

「龍が彫ってある王座」(清代) 堂々たる姿をした清代のモンゴルの長の王座です。金も施された細部の意匠はもとより、手すりの鹿角が強烈な存在感を見せつけていました。

「ルビー装飾の親王の帽子」(清代) 赤い糸で装飾された上にルビーが輝いています。王の冬にかぶる帽子とのことでした。

「錯金龍紋佩刀」(清代) 見事な金の象嵌が施されています。鞘には蜥蜴の皮が張られていました。
ちなみにこれらの文物は殆どが日本初公開だそうです。中国はもとより、時にチベットやインドとの交流を踏まえて花開いたモンゴル文化を知る絶好の機会であることは間違いありません。
なおちらし表紙に美しい金の飾り物が掲載されていますが、そちらについては別記事でもまとめてあります。
「鷹形金冠飾り」 江戸東京博物館(チンギス・ハーンとモンゴルの至宝展)
 (展示風景)
(展示風景)伺った話によれば比較的、人出は緩やかだとのことでした。あまりストレスなく楽しめるのではないでしょうか。また会期中は全日、先着100名にモンゴル岩塩がプレゼントされます。
4月11日まで開催されています。
注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )









