都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「白髪一雄」 東京オペラシティアートギャラリー
東京オペラシティアートギャラリー
「白髪一雄」
2020/1/11〜3/22
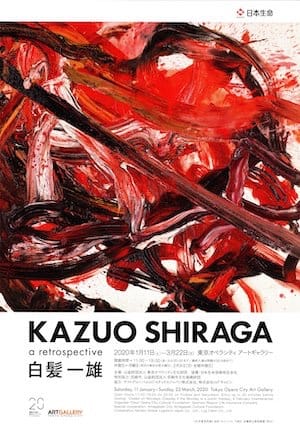
東京オペラシティアートギャラリーで開催中の「白髪一雄」を見てきました。
1924年に兵庫県尼崎市に生まれ、「具体美術協会」のメンバーとして活動した白髪一雄は、足で絵を描くフット・ペインティングの技法を用い、生涯に渡って旺盛に作品を制作しました。
その白髪の都内では初の大規模な個展が「白髪一雄展」で、代表的なフット・ペインティングの他、実験的な立体作品、さらには資料など約130点を公開していました。
鮮烈な色彩と激しいタッチで知られる白髪の作風ですが、何も初めからエネルギッシュな作品ばかりを描いたわけではありませんでした。元々、日本画を学び、美術専門学校時代に油彩へ転向した白髪は、若い頃に街の風景や、具象的なモチーフも垣間見える絵画を制作していて、船や魚の描かれた「難航」などは、おおよそ後の白髪の作品とは似ても似つきませんでした。
1952年に村上三郎や田中敦子らと「ゼロ会」を結成した白髪は、早くも2年後に独自の画風を切り開くべく、フット・ペインティングに挑戦するようになりました。また1955年に「具体美術協会」に参加すると、絵画のみならず、インスタレーションやパフォーマンス・アートなどにも幅広く取り組みました。

「天異星赤髪鬼」 1959年 兵庫県立美術館(山村コレクション)
血のように赤い色彩がキャンバス上でのたうち回るのが「天異星赤髪鬼」で、爛れた皮膚かこびり付いたコゲのような質感の油彩が、まるで鞭を打つかのように四方へと暴力的なまでに広がっていました。

「地暴星喪門神」 1961年 兵庫県立美術館(山村コレクション)
また「地暴星喪門神」は余白を残しつつも、ねっとりとした赤や黒の絵具が画面でぶつかっていて、力強いまでのエネルギーを放っていました。どこか複数の人が踊り狂っているような姿にも見えるかもしれません。
なお赤髪鬼や喪門神などの独特なタイトルにも目を引かれますが、これらは白髪が幼少期より愛読していたという水滸伝の登場人物のあだ名が付けられているそうです。
1960年代に密教へ関心を寄せた白髪は、後に延暦寺で得度すると、天台宗の僧侶として仏門に入りました。そして1972年に具体美術協会が解散した頃から、足に代わってスキージと呼ばれる長いヘラを用いて作品を描くようになりました。

「貫流」 1973年 東京オペラシティアートギャラリー
その1枚が「貫流」で、ヘラを用いたのか、白や黒の色彩が以前よりもやや薄く塗られていました。白髪というと、絵具をぶつけたり、盛っていくイメージがありますが、一連のヘラの作品は異なっているのかもしれません。

「貫流」(部分) 1973年 東京オペラシティアートギャラリー
それらの作品は「濃密な精神性」(解説より)とも捉えられていましたが、私には氷河の流れる大地や天体の運動など、自然や宇宙の光景が表れているようにも感じられました。
一時、円相の作品を多く制作していた白髪でしたが、1978年にフット・ペインティングの技法に戻ると、再び足で絵画を描くようになりました。

「酔獅子」 1999年 個人蔵
こげ茶とも黒などが凝縮するように展開する「酔獅子」では、明らかに足を思わせる形も浮かび上がっていて、まさに身体全体をぶつけては、キャンバスに格闘する白髪の姿を想像させるものがありました。

「游墨 壱」 1989年 東京オペラシティアートギャラリー
一方の「游墨 壱」は、黒が画面中央部を執拗に塗りつぶすように展開していて、まるで黒い雲が重なり合い、何かを隠し、後に現れるかのような不穏な雰囲気も感じられました。
白髪の回顧展として思い出すのは、2009年に横須賀美術館で開催された「白髪一雄 - 格闘から生まれた絵画」でした。ちょうど白髪の亡くなった1年後のことで、生前に画家本人が構想したテーマによって構成された展覧会でした。
初期作から晩年の作品までを網羅した内容で、ともかく絵画そのものの放つ熱気にのまれたことを覚えています。また制作に使ったロープが吊るされていたのも印象的でした。

「うすさま」 1999年 個人蔵
それから約10年超、なかなかまとめて見る機会がなかっただけに、改めて白髪の特異な作品の魅力に感じ入りました。

「色絵」 1966年 兵庫県立美術館
一部の作品の撮影が可能でした。(本エントリに掲載した写真は全て撮影可作品です。)
3月22日まで開催されています。おすすめします。
「白髪一雄」 東京オペラシティアートギャラリー
会期:2020年1月11日(土)〜3月22日(日)
休館:月曜日
*祝日の場合は翌火曜日。2月9日(日)*全館休館日
時間:11:00~19:00
*金・土は20時まで開館。
*入場は閉館30分前まで。
料金:一般1200(1000)円、大・高生800(600)円、中学生以下無料。
*同時開催中の「収蔵品展069 汝の隣人を愛せよ」、「project N 78 今井麗」の入場料を含む。
*( )内は15名以上の団体料金。
住所:新宿区西新宿3-20-2
交通:京王新線初台駅東口直結徒歩5分。
「白髪一雄」
2020/1/11〜3/22
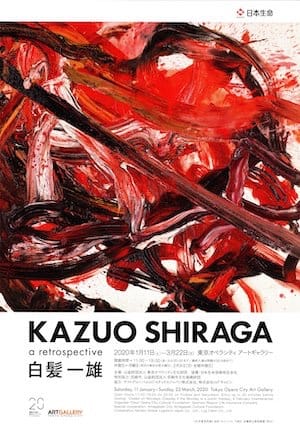
東京オペラシティアートギャラリーで開催中の「白髪一雄」を見てきました。
1924年に兵庫県尼崎市に生まれ、「具体美術協会」のメンバーとして活動した白髪一雄は、足で絵を描くフット・ペインティングの技法を用い、生涯に渡って旺盛に作品を制作しました。
その白髪の都内では初の大規模な個展が「白髪一雄展」で、代表的なフット・ペインティングの他、実験的な立体作品、さらには資料など約130点を公開していました。
鮮烈な色彩と激しいタッチで知られる白髪の作風ですが、何も初めからエネルギッシュな作品ばかりを描いたわけではありませんでした。元々、日本画を学び、美術専門学校時代に油彩へ転向した白髪は、若い頃に街の風景や、具象的なモチーフも垣間見える絵画を制作していて、船や魚の描かれた「難航」などは、おおよそ後の白髪の作品とは似ても似つきませんでした。
1952年に村上三郎や田中敦子らと「ゼロ会」を結成した白髪は、早くも2年後に独自の画風を切り開くべく、フット・ペインティングに挑戦するようになりました。また1955年に「具体美術協会」に参加すると、絵画のみならず、インスタレーションやパフォーマンス・アートなどにも幅広く取り組みました。

「天異星赤髪鬼」 1959年 兵庫県立美術館(山村コレクション)
血のように赤い色彩がキャンバス上でのたうち回るのが「天異星赤髪鬼」で、爛れた皮膚かこびり付いたコゲのような質感の油彩が、まるで鞭を打つかのように四方へと暴力的なまでに広がっていました。

「地暴星喪門神」 1961年 兵庫県立美術館(山村コレクション)
また「地暴星喪門神」は余白を残しつつも、ねっとりとした赤や黒の絵具が画面でぶつかっていて、力強いまでのエネルギーを放っていました。どこか複数の人が踊り狂っているような姿にも見えるかもしれません。
なお赤髪鬼や喪門神などの独特なタイトルにも目を引かれますが、これらは白髪が幼少期より愛読していたという水滸伝の登場人物のあだ名が付けられているそうです。
1960年代に密教へ関心を寄せた白髪は、後に延暦寺で得度すると、天台宗の僧侶として仏門に入りました。そして1972年に具体美術協会が解散した頃から、足に代わってスキージと呼ばれる長いヘラを用いて作品を描くようになりました。

「貫流」 1973年 東京オペラシティアートギャラリー
その1枚が「貫流」で、ヘラを用いたのか、白や黒の色彩が以前よりもやや薄く塗られていました。白髪というと、絵具をぶつけたり、盛っていくイメージがありますが、一連のヘラの作品は異なっているのかもしれません。

「貫流」(部分) 1973年 東京オペラシティアートギャラリー
それらの作品は「濃密な精神性」(解説より)とも捉えられていましたが、私には氷河の流れる大地や天体の運動など、自然や宇宙の光景が表れているようにも感じられました。
一時、円相の作品を多く制作していた白髪でしたが、1978年にフット・ペインティングの技法に戻ると、再び足で絵画を描くようになりました。

「酔獅子」 1999年 個人蔵
こげ茶とも黒などが凝縮するように展開する「酔獅子」では、明らかに足を思わせる形も浮かび上がっていて、まさに身体全体をぶつけては、キャンバスに格闘する白髪の姿を想像させるものがありました。

「游墨 壱」 1989年 東京オペラシティアートギャラリー
一方の「游墨 壱」は、黒が画面中央部を執拗に塗りつぶすように展開していて、まるで黒い雲が重なり合い、何かを隠し、後に現れるかのような不穏な雰囲気も感じられました。
白髪の回顧展として思い出すのは、2009年に横須賀美術館で開催された「白髪一雄 - 格闘から生まれた絵画」でした。ちょうど白髪の亡くなった1年後のことで、生前に画家本人が構想したテーマによって構成された展覧会でした。
初期作から晩年の作品までを網羅した内容で、ともかく絵画そのものの放つ熱気にのまれたことを覚えています。また制作に使ったロープが吊るされていたのも印象的でした。

「うすさま」 1999年 個人蔵
それから約10年超、なかなかまとめて見る機会がなかっただけに、改めて白髪の特異な作品の魅力に感じ入りました。

「色絵」 1966年 兵庫県立美術館
一部の作品の撮影が可能でした。(本エントリに掲載した写真は全て撮影可作品です。)
3月22日まで開催されています。おすすめします。
「白髪一雄」 東京オペラシティアートギャラリー
会期:2020年1月11日(土)〜3月22日(日)
休館:月曜日
*祝日の場合は翌火曜日。2月9日(日)*全館休館日
時間:11:00~19:00
*金・土は20時まで開館。
*入場は閉館30分前まで。
料金:一般1200(1000)円、大・高生800(600)円、中学生以下無料。
*同時開催中の「収蔵品展069 汝の隣人を愛せよ」、「project N 78 今井麗」の入場料を含む。
*( )内は15名以上の団体料金。
住所:新宿区西新宿3-20-2
交通:京王新線初台駅東口直結徒歩5分。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )









