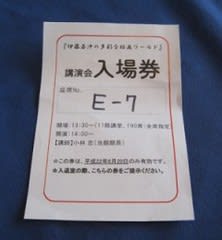○五島美術館 開館50周年記念名品展III『陶芸の美-日本・中国・朝鮮』(2010年6月26日~8月8日)
名品展第3弾は陶芸。当然のように茶道具類を想像して会場に入ると、いきなり古墳時代の水鳥埴輪(でかいなー)が待っていて、フェイントをかまされる。そのあとは、やはり茶の湯に関連したものが多い。鼠志野茶碗「銘・峯紅葉」は堂々とした厚口だが、「成形が巧みなため手に持つと意外と軽い」という解説が気になる。正面から見ると、器の外側にも内側(の奥)にも亀甲文が見え、反対側にまわると、手品のように、外側も内側も亀甲文が隠れ、檜垣文が顔を出す。1碗で2つの顔を持つ不思議。
お茶室ならお道具をまわして拝見するところ、展示室ではケースの周囲を自分でまわってみることで、思わぬ発見がある。古伊賀水指「銘・破袋(やれぶくろ)」も、正面から見たときは、さほど感動しなかったのだが、右横にまわって、開口部から底部に至る、すさまじい断裂を発見したときは、言葉を失ってしまった。これはねえ、ネットで検索しても正面画像しか出てこないけど必見だと思う。しばらく様子を見ていると、正面の姿しか見ていない観客が多くて、もったいなかった。せっかく360度まわれる展示ケースに入っているのに! 背面の底部に刻まれた十文字も、野武士の古傷みたいだった。何だろう、この満身創痍の状態を愛でる、豪胆な美意識は…。
むかしは、伊賀とか備前とか、ゴツいやきものは苦手だったが、最近は好きになった。実際に花をいけて茶室に据えると、大地の一部のような安定感を感じさせる。今回は、特に信楽の水指「銘・若緑」に惹かれた。武野紹鴎が好んだ「鬼桶」と呼ばれる器形だ。暗褐色に緑苔のような釉薬がかかり、眺める位置によって、つるつるにもざらざらにも見えるのが面白い。
それから、中国陶磁の列に進むが、コテコテの「中華味」ではなくて、全体に茶人好みの中国陶磁だと思った。かたちがよくて、品があって、くすっとなごませる。『緑釉牡丹文鳳首瓶(乾瓦窯)』(公式サイトに画像あり)の生真面目に背筋を伸ばした鳳凰。『白磁弁口水注』は把子の人物(少年?)の顔がかわいい。赤絵や染付の文様も、素朴でおおらか。朝鮮陶磁も同様で、『粉青白地掻落牡丹文扁壺』は、パウル・クレーの抽象画みたいな繊細な色彩。鉄絵草花文の扁壺もあったが、「民藝」の美意識が選ぶ朝鮮陶磁とは違うなあ、と感じた。日本陶磁でいうと、古九谷のめずらしい山水文『色絵山水文大皿』 も、古九谷・青手大皿の臭みというか毒がなくて、ほんわかした夢の光景を描いているように見える。
茶碗は、やっぱり長次郎の赤茶碗「銘・夕暮」。初めてじゃない、と思ったら、2008年に五島美術館の『館蔵 茶道具取合せ展』で見ている。黒楽茶碗は「銘・三番叟」しか出ていなかったが、次回展『茶道具の精華』のために取ってあるのかな。井戸茶碗は、まだ、良さがよく分からない。
名品展第3弾は陶芸。当然のように茶道具類を想像して会場に入ると、いきなり古墳時代の水鳥埴輪(でかいなー)が待っていて、フェイントをかまされる。そのあとは、やはり茶の湯に関連したものが多い。鼠志野茶碗「銘・峯紅葉」は堂々とした厚口だが、「成形が巧みなため手に持つと意外と軽い」という解説が気になる。正面から見ると、器の外側にも内側(の奥)にも亀甲文が見え、反対側にまわると、手品のように、外側も内側も亀甲文が隠れ、檜垣文が顔を出す。1碗で2つの顔を持つ不思議。
お茶室ならお道具をまわして拝見するところ、展示室ではケースの周囲を自分でまわってみることで、思わぬ発見がある。古伊賀水指「銘・破袋(やれぶくろ)」も、正面から見たときは、さほど感動しなかったのだが、右横にまわって、開口部から底部に至る、すさまじい断裂を発見したときは、言葉を失ってしまった。これはねえ、ネットで検索しても正面画像しか出てこないけど必見だと思う。しばらく様子を見ていると、正面の姿しか見ていない観客が多くて、もったいなかった。せっかく360度まわれる展示ケースに入っているのに! 背面の底部に刻まれた十文字も、野武士の古傷みたいだった。何だろう、この満身創痍の状態を愛でる、豪胆な美意識は…。
むかしは、伊賀とか備前とか、ゴツいやきものは苦手だったが、最近は好きになった。実際に花をいけて茶室に据えると、大地の一部のような安定感を感じさせる。今回は、特に信楽の水指「銘・若緑」に惹かれた。武野紹鴎が好んだ「鬼桶」と呼ばれる器形だ。暗褐色に緑苔のような釉薬がかかり、眺める位置によって、つるつるにもざらざらにも見えるのが面白い。
それから、中国陶磁の列に進むが、コテコテの「中華味」ではなくて、全体に茶人好みの中国陶磁だと思った。かたちがよくて、品があって、くすっとなごませる。『緑釉牡丹文鳳首瓶(乾瓦窯)』(公式サイトに画像あり)の生真面目に背筋を伸ばした鳳凰。『白磁弁口水注』は把子の人物(少年?)の顔がかわいい。赤絵や染付の文様も、素朴でおおらか。朝鮮陶磁も同様で、『粉青白地掻落牡丹文扁壺』は、パウル・クレーの抽象画みたいな繊細な色彩。鉄絵草花文の扁壺もあったが、「民藝」の美意識が選ぶ朝鮮陶磁とは違うなあ、と感じた。日本陶磁でいうと、古九谷のめずらしい山水文『色絵山水文大皿』 も、古九谷・青手大皿の臭みというか毒がなくて、ほんわかした夢の光景を描いているように見える。
茶碗は、やっぱり長次郎の赤茶碗「銘・夕暮」。初めてじゃない、と思ったら、2008年に五島美術館の『館蔵 茶道具取合せ展』で見ている。黒楽茶碗は「銘・三番叟」しか出ていなかったが、次回展『茶道具の精華』のために取ってあるのかな。井戸茶碗は、まだ、良さがよく分からない。