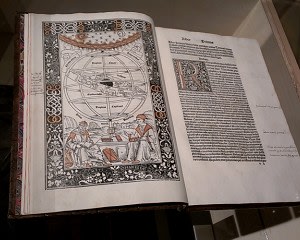○森岡孝二『雇用身分社会』(岩波新書) 岩波書店 2015.10
 カバーの折り返しに「この30年で様変わりした雇用関係を概観し、雇用身分社会から抜け出す道筋を考える」とある。30年前といえば、ちょうど私が学業を終えて社会に出た頃だ。「フリーター」という言葉が使われ始め、多様な働き方を選べる時代が始まったかに見えた。私も大学卒業後、しばらく不安定な働き方をしていたが、バブル崩壊の少し前に、いまの仕事に落ち着いたのが、振り返れば幸運だったと言える。
カバーの折り返しに「この30年で様変わりした雇用関係を概観し、雇用身分社会から抜け出す道筋を考える」とある。30年前といえば、ちょうど私が学業を終えて社会に出た頃だ。「フリーター」という言葉が使われ始め、多様な働き方を選べる時代が始まったかに見えた。私も大学卒業後、しばらく不安定な働き方をしていたが、バブル崩壊の少し前に、いまの仕事に落ち着いたのが、振り返れば幸運だったと言える。
日本は、この30年間、経済界も政界も「雇用形態の多様化」を進めてきた。その結果、働く人々が、総合職正社員、一般職正社員、限定正社員、嘱託社員、契約社員、パート・アルバイト、派遣労働者のいずれかの「身分」に引き裂かれた「雇用身分社会」が出現したというのが著者の見立てである。
そもそも古い時代の日本ではどうだったのか。第1章は『職工事情』や『女工哀史』を参考に、戦前の日本企業の雇用関係と働かされ方を見ていく。一度きちんと調べてみたいと思っていた事柄で、非常に面白かった。紡績工場の中には文部省認可の小学校を併設しているところもあったが、これは「初等教育を受けていない少女を集めるため」であって、「肯定的に評価することはできない」と著者は述べている。労働時間は11時間を原則としながら、残業が強制されていたり、強制でなくても、わずかな手当のために残業に応じる者が多かったなど、問題の根は現代と変わらないように思った。
戦前の女工たちの多くは、募集人によって集められ、工場に送り込まれた。戦前の日本では、募集人・周旋屋・口入屋・手配師など、労働市場の多様な仲介人が存在し、労働者を食いものにする悪質業者も多かった。企業もまた、仲介業者を利用することで、募集の手間や使用者責任を逃れようとしていた。戦後の1947年、職業安定法に制定によって「使用者と労働者のあいだに中間業者が介在する」前近代的な慣行は原則として禁止された。
しかし、60~70年代になると、職安法の理念はずるずると後退していく。1985年に労働者派遣法が成立し、違法であったはずの労働者供給事業が「労働者派遣事業」として合法化される。最終的に認められたのは、いわゆる「専門26業務」(1996年)で「専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務」と言いながら、「ファイリング、建築物清掃、受付・案内・駐車場管理など、高度の知識やスキルを要さない単純労働の業務が、こっそりというよりごっそり含まれていた」と著者は喝破する。あ、やっぱりねえ。派遣法をいくら読んでも趣旨が分からなくて、分からないのは私に法律知識がないためかと思っていたが、やっぱり常識的に論理が破綻した法律なのだ。そして財界の期待に応えて制度の規制緩和は着々と進み、2015年9月には「専門26業務」の枠組みが完全に廃され、企業は正社員をいつでも使い捨て可能な派遣労働者に恒久的に置き換えることが可能になってしまった。
次に女性に多いパートタイム労働者。実は戦後しばらくは、臨時雇いや日雇いで働く短時間労働者は男性のほうが多かった。1960年代以降、女性パートが増加し、1975年から90年代にかけて「男は残業(長時間労働)・女はパート」という日本的働き方が一般化し、労働時間の性別二極分化が進む。しかし、国際比較から見ると、日本のパートタイム労働者の就業時間は長い。諸外国のフルタイム並みに働いているにもかかわらず、賃金や労働条件はひどく劣悪なのだ。
最後にホワイトカラー正社員の受難。無際限な長時間労働、過労とストレス。定年制(長期雇用慣行)はもはや風前の灯でしかない。日本成長戦略のひとつとして「40歳定年制」が本気で検討されているらしいのである。このように、どの働き方を選んでも(そもそも選べるのか?)あまり明るい未来は見えない。そして、雇用格差は、所得の面では高所得層の縮小、低所得層の拡大を生んでおり、深刻な貧困をもたらしている。
「まともな働き方」に向けての提言は、(1)労働者派遣制度の見直し・(2)非正規雇用者の比率引き下げ・(3)雇用・労働の規制緩和との決別・(4)最低賃金の引き上げ・(5)八時間労働制の確立・(6)性別賃金格差の解消。当たり前の事ばかりだ。しかし、この当たり前の事が実現できないうちは、どんなに目新しい政策を掲げたところで、目くらましに過ぎないと肝に銘じよう。もちろん企業経営者は嫌がるだろうけど、まともな社会にするには、まともな働き方を取り戻すことが絶対に必要である。
 カバーの折り返しに「この30年で様変わりした雇用関係を概観し、雇用身分社会から抜け出す道筋を考える」とある。30年前といえば、ちょうど私が学業を終えて社会に出た頃だ。「フリーター」という言葉が使われ始め、多様な働き方を選べる時代が始まったかに見えた。私も大学卒業後、しばらく不安定な働き方をしていたが、バブル崩壊の少し前に、いまの仕事に落ち着いたのが、振り返れば幸運だったと言える。
カバーの折り返しに「この30年で様変わりした雇用関係を概観し、雇用身分社会から抜け出す道筋を考える」とある。30年前といえば、ちょうど私が学業を終えて社会に出た頃だ。「フリーター」という言葉が使われ始め、多様な働き方を選べる時代が始まったかに見えた。私も大学卒業後、しばらく不安定な働き方をしていたが、バブル崩壊の少し前に、いまの仕事に落ち着いたのが、振り返れば幸運だったと言える。日本は、この30年間、経済界も政界も「雇用形態の多様化」を進めてきた。その結果、働く人々が、総合職正社員、一般職正社員、限定正社員、嘱託社員、契約社員、パート・アルバイト、派遣労働者のいずれかの「身分」に引き裂かれた「雇用身分社会」が出現したというのが著者の見立てである。
そもそも古い時代の日本ではどうだったのか。第1章は『職工事情』や『女工哀史』を参考に、戦前の日本企業の雇用関係と働かされ方を見ていく。一度きちんと調べてみたいと思っていた事柄で、非常に面白かった。紡績工場の中には文部省認可の小学校を併設しているところもあったが、これは「初等教育を受けていない少女を集めるため」であって、「肯定的に評価することはできない」と著者は述べている。労働時間は11時間を原則としながら、残業が強制されていたり、強制でなくても、わずかな手当のために残業に応じる者が多かったなど、問題の根は現代と変わらないように思った。
戦前の女工たちの多くは、募集人によって集められ、工場に送り込まれた。戦前の日本では、募集人・周旋屋・口入屋・手配師など、労働市場の多様な仲介人が存在し、労働者を食いものにする悪質業者も多かった。企業もまた、仲介業者を利用することで、募集の手間や使用者責任を逃れようとしていた。戦後の1947年、職業安定法に制定によって「使用者と労働者のあいだに中間業者が介在する」前近代的な慣行は原則として禁止された。
しかし、60~70年代になると、職安法の理念はずるずると後退していく。1985年に労働者派遣法が成立し、違法であったはずの労働者供給事業が「労働者派遣事業」として合法化される。最終的に認められたのは、いわゆる「専門26業務」(1996年)で「専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務」と言いながら、「ファイリング、建築物清掃、受付・案内・駐車場管理など、高度の知識やスキルを要さない単純労働の業務が、こっそりというよりごっそり含まれていた」と著者は喝破する。あ、やっぱりねえ。派遣法をいくら読んでも趣旨が分からなくて、分からないのは私に法律知識がないためかと思っていたが、やっぱり常識的に論理が破綻した法律なのだ。そして財界の期待に応えて制度の規制緩和は着々と進み、2015年9月には「専門26業務」の枠組みが完全に廃され、企業は正社員をいつでも使い捨て可能な派遣労働者に恒久的に置き換えることが可能になってしまった。
次に女性に多いパートタイム労働者。実は戦後しばらくは、臨時雇いや日雇いで働く短時間労働者は男性のほうが多かった。1960年代以降、女性パートが増加し、1975年から90年代にかけて「男は残業(長時間労働)・女はパート」という日本的働き方が一般化し、労働時間の性別二極分化が進む。しかし、国際比較から見ると、日本のパートタイム労働者の就業時間は長い。諸外国のフルタイム並みに働いているにもかかわらず、賃金や労働条件はひどく劣悪なのだ。
最後にホワイトカラー正社員の受難。無際限な長時間労働、過労とストレス。定年制(長期雇用慣行)はもはや風前の灯でしかない。日本成長戦略のひとつとして「40歳定年制」が本気で検討されているらしいのである。このように、どの働き方を選んでも(そもそも選べるのか?)あまり明るい未来は見えない。そして、雇用格差は、所得の面では高所得層の縮小、低所得層の拡大を生んでおり、深刻な貧困をもたらしている。
「まともな働き方」に向けての提言は、(1)労働者派遣制度の見直し・(2)非正規雇用者の比率引き下げ・(3)雇用・労働の規制緩和との決別・(4)最低賃金の引き上げ・(5)八時間労働制の確立・(6)性別賃金格差の解消。当たり前の事ばかりだ。しかし、この当たり前の事が実現できないうちは、どんなに目新しい政策を掲げたところで、目くらましに過ぎないと肝に銘じよう。もちろん企業経営者は嫌がるだろうけど、まともな社会にするには、まともな働き方を取り戻すことが絶対に必要である。