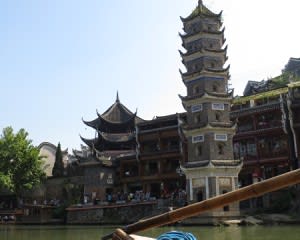○雑誌『芸術新潮』2016年8月号 創刊800号記念特大号「神の空間を旅する 神社100選」 新潮社 2016.8
 読むというより眺める記事が多いので、7月末に購入して以来、気が向くとパラパラ開いて眺めている。「神社100選」は「神社の誕生」「神話の神様とその現場」「神社名建築紀行」「神と仏の千年史」「人、神となる」「山は神さま」「国宝あります」「諸国一の宮めぐり」の8つのカテゴリーに計100社を選び、写真・基本データ(祭神、社格、所在地、行き方など)・短いもので200~300字の紹介文が掲載されている。「日本全国」と言いたいところ、沖縄はあるが、北海道は1社もない。私は、わずかな期間だが道民だったことがあるので、ちょっとショックだったが、まあ妥当かなあ…。江差の姥神大神宮を入れてほしかった。よく見ると、ほかにも1社も入っていない県があって、岩手、山梨、徳島、佐賀が該当する。
読むというより眺める記事が多いので、7月末に購入して以来、気が向くとパラパラ開いて眺めている。「神社100選」は「神社の誕生」「神話の神様とその現場」「神社名建築紀行」「神と仏の千年史」「人、神となる」「山は神さま」「国宝あります」「諸国一の宮めぐり」の8つのカテゴリーに計100社を選び、写真・基本データ(祭神、社格、所在地、行き方など)・短いもので200~300字の紹介文が掲載されている。「日本全国」と言いたいところ、沖縄はあるが、北海道は1社もない。私は、わずかな期間だが道民だったことがあるので、ちょっとショックだったが、まあ妥当かなあ…。江差の姥神大神宮を入れてほしかった。よく見ると、ほかにも1社も入っていない県があって、岩手、山梨、徳島、佐賀が該当する。
100社のうち、行ったことがある(記憶がある)のは、半数を少し超える程度だった。コンプリートだったのは「人、神となる」の10社。日光東照宮とか大宰府天満宮とか明治神宮とか、現代の日本人にとって、最もポピュラーな神社が多いカテゴリーである。私は寺好きだから、「神と仏の千年史」のカテゴリーもかなり踏破している。全滅だったのは「山は神さま」で、山登りを伴う神社には全く行けていないことを自覚した。
個人的に、リストに入れてほしかったな~と思ったのは、島根県の揖屋(いや)神社。入沢康夫さんの詩「わが出雲・わが鎮魂」に登場する神社である。それから、和歌山県の天野社(丹生都比売神社)。逆に、よくこんなところが入ったなあと驚いた(嬉しかった)のは滋賀県の油日神社。のんびりした雰囲気を思い出して懐かしかった。写真を見て、行きたい!と思った第一は、長崎県・対馬の和多都美神社。海上に立つ二基の石の鳥居、見てみたい。社前には不思議な「三柱鳥居」があるという。京都の吉田神社は、参拝したことはあるのだが、奇妙な外観の大元宮という建物は記憶にない。今度、見てこなくちゃ。
さて「神社とは何か」「神道とは何か」「カミとは何か」については、多方面から解説記事が書かれている。私は「神話の神さま名鑑」(死後くん・イラストレーション)の記事がけっこう気に入った。女性にモテモテのオオクニヌシノミコトとか武闘派のタケミカヅチノカミとか、実にイメージどおりで笑った。ただ、スミヨシ三神は、私は老人のイメージである。「人を神として祭るということ」は、茨城大学教授の伊藤聡さんの解説。Q&A方式で分かりやすい。内容をよく分かった人が編集しているなと感じた。ここも別府麻衣さんのイラストレーションが可愛い。日本国の大魔縁となった崇徳院、可愛すぎるw
神社の外観は、お寺に比べると変化に乏しいから、つまらないかと思ったが、けっこう眺めて楽しめるものである。本誌は、日常のたたずまいを中心に掲載しているが、神社は「祭り」のときだけ、全く別の空間に変わってしまうもので、その魅力は、記憶と想像で補う必要がある。
 読むというより眺める記事が多いので、7月末に購入して以来、気が向くとパラパラ開いて眺めている。「神社100選」は「神社の誕生」「神話の神様とその現場」「神社名建築紀行」「神と仏の千年史」「人、神となる」「山は神さま」「国宝あります」「諸国一の宮めぐり」の8つのカテゴリーに計100社を選び、写真・基本データ(祭神、社格、所在地、行き方など)・短いもので200~300字の紹介文が掲載されている。「日本全国」と言いたいところ、沖縄はあるが、北海道は1社もない。私は、わずかな期間だが道民だったことがあるので、ちょっとショックだったが、まあ妥当かなあ…。江差の姥神大神宮を入れてほしかった。よく見ると、ほかにも1社も入っていない県があって、岩手、山梨、徳島、佐賀が該当する。
読むというより眺める記事が多いので、7月末に購入して以来、気が向くとパラパラ開いて眺めている。「神社100選」は「神社の誕生」「神話の神様とその現場」「神社名建築紀行」「神と仏の千年史」「人、神となる」「山は神さま」「国宝あります」「諸国一の宮めぐり」の8つのカテゴリーに計100社を選び、写真・基本データ(祭神、社格、所在地、行き方など)・短いもので200~300字の紹介文が掲載されている。「日本全国」と言いたいところ、沖縄はあるが、北海道は1社もない。私は、わずかな期間だが道民だったことがあるので、ちょっとショックだったが、まあ妥当かなあ…。江差の姥神大神宮を入れてほしかった。よく見ると、ほかにも1社も入っていない県があって、岩手、山梨、徳島、佐賀が該当する。100社のうち、行ったことがある(記憶がある)のは、半数を少し超える程度だった。コンプリートだったのは「人、神となる」の10社。日光東照宮とか大宰府天満宮とか明治神宮とか、現代の日本人にとって、最もポピュラーな神社が多いカテゴリーである。私は寺好きだから、「神と仏の千年史」のカテゴリーもかなり踏破している。全滅だったのは「山は神さま」で、山登りを伴う神社には全く行けていないことを自覚した。
個人的に、リストに入れてほしかったな~と思ったのは、島根県の揖屋(いや)神社。入沢康夫さんの詩「わが出雲・わが鎮魂」に登場する神社である。それから、和歌山県の天野社(丹生都比売神社)。逆に、よくこんなところが入ったなあと驚いた(嬉しかった)のは滋賀県の油日神社。のんびりした雰囲気を思い出して懐かしかった。写真を見て、行きたい!と思った第一は、長崎県・対馬の和多都美神社。海上に立つ二基の石の鳥居、見てみたい。社前には不思議な「三柱鳥居」があるという。京都の吉田神社は、参拝したことはあるのだが、奇妙な外観の大元宮という建物は記憶にない。今度、見てこなくちゃ。
さて「神社とは何か」「神道とは何か」「カミとは何か」については、多方面から解説記事が書かれている。私は「神話の神さま名鑑」(死後くん・イラストレーション)の記事がけっこう気に入った。女性にモテモテのオオクニヌシノミコトとか武闘派のタケミカヅチノカミとか、実にイメージどおりで笑った。ただ、スミヨシ三神は、私は老人のイメージである。「人を神として祭るということ」は、茨城大学教授の伊藤聡さんの解説。Q&A方式で分かりやすい。内容をよく分かった人が編集しているなと感じた。ここも別府麻衣さんのイラストレーションが可愛い。日本国の大魔縁となった崇徳院、可愛すぎるw
神社の外観は、お寺に比べると変化に乏しいから、つまらないかと思ったが、けっこう眺めて楽しめるものである。本誌は、日常のたたずまいを中心に掲載しているが、神社は「祭り」のときだけ、全く別の空間に変わってしまうもので、その魅力は、記憶と想像で補う必要がある。