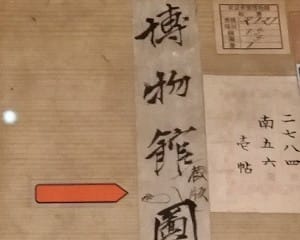〇原田実『オカルト化する日本の教育:江戸しぐさと親学にひそむナショナリズム』(ちくま新書) 筑摩書房 2018.6

「江戸しぐさ」と「親学」という、あやしい教育論の噂は聞いていたので、表題から見て批判的な立場にあるらしい本書で、少し知識を仕入れてみようと思った。
「江戸しぐさ」とは、江戸時代、全国から江戸に集まってきた人たちが、おたがい仲良く平和に暮らしていけるように生み出した生活習慣のことで、具体的な動作として「肩引き」「こぶし浮かせ」「傘かしげ」などがあると言われている。著者の調査によれば、「江戸しぐさ」という語の初出は1981年で、企業の社員研修や経営指導を行っていた芝三光(1928-99)という人物が作り出したものだが、90年代からジャーナリストの越川禮子によって徐々に広まり、2014年には文部科学省が配布した『私たちの道徳 小学五・六年生用』に掲載されるに至った。
私は、かつて東京メトロで「江戸しぐさ」を使ったマナー広告を見た記憶がある。洛中洛外図ふうの江戸の町で「傘かしげ」をしてすれ違ったり「こぶし浮かせ」で席をつめる人々が描かれていた。いま調べてみたら、2005年頃の広告で、山口晃さんの絵であるらしい。山口さんの描く江戸は、武士がオートバイに乗っていたり、お城に高速道路が接続していたりする「架空の江戸」である。当然、描かれた「江戸しぐさ」も、マナー啓発のためのフィクション(パロディ)だと思って当時の私は見ていた。私は大学で日本の古典文学を学び、趣味で古典芸能にも親しんできたが、こんなマナーは聞いたこともなかったから、フィクション以外ではあり得なかった。それが、この10年のうちに「歴史」「伝統」に変わりつつあるというのだから、なんとも困惑する事態である。
「親学」はさらに厄介だ。教育学者の高橋史朗(1950-)が主唱する「親学」とは、親や、これから親になる人に、親になるための教育を提供しようという運動である。これだけなら何の反対もない。しかし、親学が学ばせようとしている内容が、実質不明の「日本の伝統的子育て」で、その実践が、伝統でも何でもない「親守詩(おやもりうた)」(子供が親に感謝を伝える文芸活動)の普及だと聞くと、その恣意性に呆れてしまう。子供が親に対して五七五で呼びかけ、親が子供に七七で応えるって、連歌じゃねえか。
著者によれば、親学の支持者は、単に自分が理想とする親子関係を「伝統的子育て」に仮託している。したがって、その内容には歴史的根拠がなく、「お父さんの育児参加」「ほめてのばす」など、むしろ開明的な印象を受けるものもあるのが興味深い。しかし、理想の親子関係への信仰から、ついには「日本の伝統的な育児が発達障害を防ぐ(治す)」と表明するに至っては、悪影響を看過できない。これが障害学の知見と相いれないものであることは本書に詳しい。偽史や偽科学が教育行政を動かしている状況は、早急に見直されるべきである。
本書の後半は「江戸しぐさ」「親学」を支持する右派保守人脈の思想的背景であるGHQ陰謀論について解説する。GHQが占領政策の一環として「戦争についての罪悪感を日本人に植えつけるための宣伝計画」(WGIP/War Guilt Information Program)を行ったというのは、江藤淳の著書で広まり、今も時々話題に上るのを見かける。ざっくり言うと「江戸しぐさ」も「親学」も、WGIPが葬り去ろうとした「日本の伝統」の復権運動と(支持者には)考えられている。
このような考えを受け入れる下地として、現代日本人の多くは、左右のイデオロギーにかかわらず、アメリカが持ち込んだ悪しきものを否定したいという潜在的な反米感情を持っている、と著者は解説する。これはとても同意できる。また、20世紀から21世紀初頭(00年代)は世界的に陰謀論が流行した時代で、日本も例外ではなかったともいう。へええ!この時代認識はなかった。
陰謀論的発想になじんだ人々が過去の日本に向き合うと、さまざまな歴史の「真実」が発見されることになる。というわけで、思わぬ本から、呉座勇一先生の『
陰謀の日本中世史』を連想させる話になってきた。ただし本書が取り上げているのは、60-80年代の古代史ブームである。まず、敗戦に打ちひしがれていた日本国民の注目を集めたのが、登呂遺跡(静岡)と月の輪遺跡(岡山)。邪馬台国ブーム、梅原猛の法隆寺論などがあり、日本原住民論としての「縄文人」論とその見直しが続く。
最後は表題から予想もしなかったところに来てしまったが、「江戸しぐさ」「親学」ほど分かりやすくない、偽史・偽科学の罠が私たちのまわりには、たくさん仕掛けられているのだと思う。薄氷を履む如く慎重でありたい。