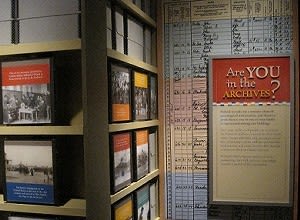振替出勤の関係で、この週末も3連休になったのを幸い、また西国巡礼に行ってきた。初日はひとりで京都の博物館めぐり。
■
高麗美術館 新春特別展『朝鮮 虎展』(2010年1月9日~2月14日)
朝鮮といえば虎、虎といえば朝鮮である(これは私のイメージ)。朝鮮半島の虎は、古来人々と深く関わり、虎を題材とする民話や美術工芸品を伝えてきた。そこで、今年の干支にちなんで、新春特別展は、ズバリ『朝鮮 虎展』。あまり大きくない展示室に入ると、確かに部屋中、トラだらけである。19世紀後半に初めて生きた虎を実見した日本人と違って、身近に虎の生息する朝鮮半島の人々が描く虎は、さすがに写実的…かというと、そうでもない。皿を嵌め込んだような目の玉の大きさ・手(掌)のフカフカした大きさ・尻尾の長さが強調されているように思う。手塚治虫のマンガみたい。
朝鮮以外に、日本人、中国人の描いた虎の絵も出品されている。なんと言っても嬉しいのは、正伝寺蔵の伝李公麟筆『虎図』(虎だけ彩色、背景は水墨、朝鮮、16世紀後半)と全く同じ構図の伊藤若冲の『竹虎図』(水墨、18世紀末)が並んでいること。2007年の暮れに、前者は京博の常設展で、後者は承天閣美術館で、同時期に公開されていたことがあるが、こんなふうにくっつき合って並ぶのは、めったにないことだと思う。もう1点、写真パネルで、プライスコレクションの若冲『虎図』も掲げてある。見比べてみると、プライスコレクションの『虎図』では、お手本の虎の縞模様を精密に写していた若冲だが、水墨の『竹虎図』では、けっこう自由に省略(特に顔のあたり)を加えていることが分かる。なお、正伝寺蔵『虎図』は、表具にも虎モチーフが使われているのをお見逃しなく!
京博でおなじみの光琳の『竹虎図』も来ていた。かわいいなー。参考写真によれば、大坂市立美術館所蔵の「小西家旧蔵尾形光琳関係資料」には、写真の裏焼きみたいな、よく似たポーズの虎図があるそうだ。17世紀初頭の朝鮮の画家、李禎(イ・ジョン)の絹本墨画淡彩(ほとんど色は見えない)『龍虎図』は生彩に富む。この『龍図』を狩野探幽が実見したことが、探幽縮図の一『筆園逸遊』によって分かるそうだ。しかし、李禎の作品は日本の高麗美術館に伝わり、探幽の模写図がベルリン国立アジア美術館にあるというのは、なんとも感慨深い。
美術館を出て、上賀茂神社に参拝。続いて、下鴨神社に向かおうとして、バスを乗り間違える。しかたないので、予定を変更して、相国寺の承天閣美術館に寄る。
■
承天閣美術館 『世界遺産 金閣・銀閣 寺宝展-墨蹟・絵画・茶道具の名品-』(2009年12月13日~2010年3月22日)
金閣寺と銀閣寺の歴史と文化を紹介する展覧会。まあ名品展である。宣伝ではあまり強調されていないが、やはりこの美術館で若冲を忘れるわけにはいかない。ということで、例の『動植綵絵』と一緒に奉納された『釈迦三尊像』を久しぶりに見る。『牡丹百合図』は、この間、MIHOミュージアムでも見たかな。若書きの『厖児戯帚図』(ホウキにじゃれる仔犬、彩色)、「七十五歳画」のサインのある『中鶏左右梅図』、奇想の巨大な『玉熨斗図』。そして『群鶏蔬菜図押絵貼屏風』。うわーこれ、いいなあ。若冲には、同類の屏風がたくさんあるが、これはピカ一ではないかと思う。右隻(右から)3番目の蕪を咥えたニワトリ、4番目のセサミストリートのビッグバードみたいにぬぼーとしたニワトリ、左隻5番目の両の翼の間から顔を出すニワトリ(大根の上に立っている)。どれも個性的で、チャーミングすぎる。
ほか、絵画では室町時代の『妙音弁才天像』が、現実味のある美人で、ふくよかな白い肌が色っぽい。工芸品では、旧金閣閣上の金銅鳳凰。あまりカッコよくないけど。劣化が激しく、明治37年に降ろされたため、昭和25年に焼失を免れたというのが、奇縁である。「唐物」の茶碗、花入には名品多し。相阿弥の『君台観左右帳記』に七宝の記録があるというのは初めて知った。「大食窯」あるいは「鬼国窯」と称されたそうだ。大食(ペルシャ)はともかく、鬼国ってすごいなあ。
と、ゆっくり見ていたら、16:30閉館のアナウンス。17:00閉館だと思っていたので慌てる(※ホームページは17:00閉館になってるんだけど…)。でも、バスに乗り間違えなかったら、下鴨神社→承天閣美術館の予定だったので、幸運だったかもしれない。
最後に下鴨神社に参拝し、初日を終了。京都在住の友人と落ち合って、四条烏丸で飲みながら明日の西国巡礼の打ち合わせ。今回の巡礼には、大事な「鳥」捕獲ミッションが課せられているのである。詳細は、第2日に続く。
↓捕獲対象の「白鳥」