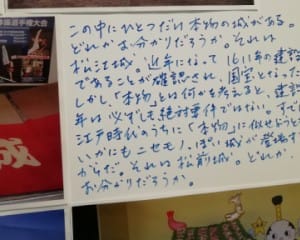■国立西洋美術館 『ルーベンス展-バロックの誕生』(2018年10月16日~2019年1月20日)
今年の年末年始は、上野にムンクもフェルメールも来ていたが、結局ルーベンスしか行かなかった。私はルーベンスと聞くと、肉づき豊かな女性の裸体像を思い出すが、今回は男性の裸体像が多かった。神話・伝説を主題とした作品の中に『ローマの慈愛』と題し、若い娘が獄中の年老いた父親に自分の母乳を飲ませる場面を描いたものがあって、SNSなどで物議を醸していた。まあ確かに現代の感覚ではヘンな絵が多かったが、それもまたよし。
■東京国立博物館 特集展示『博物館に初もうで2019 イノシシ 勢いのある年に』(2019年1月2日~1月27日)
展示品は、古代中国の灰陶豚や玉豚、望月玉泉筆『萩野猪図屏風』など、 だいたい予想どおり作品で、あまり驚きがなかった。本館1階では「高精細複製品によるあたらしい屏風体験」と題して『松林図屏風』の高精細複製品と映像のインスタレーションを展示していた。2017年の「びょうぶとあそぶ」に比べるとこじんまりしたインスタレーションだったが楽しめた。東洋館の『王羲之書法の残影-唐時代への道程-』(2019年1月2日~3月3日)も充実。
■鎌倉国宝館 源実朝没後800年、鎌倉市制施行80周年記念特別展『源実朝とその時代』(2019年1月4日~2月3日)
最近、坂井孝一『承久の乱』でかなり詳しく実朝のことを読んだので、期待して行ったら、ハズレだった。「実朝ゆかり」の展示品は「頼朝ゆかり」に置き換えてもあまり問題ないものばかり。ただ甲斐善光寺の源実朝坐像を見ることができたのはよかった。神護寺の頼朝像と顔のかたちが似ていなくもない。『公家列影図』に描かれている実朝像とも似ていると解説パネルに書いてあったので、ネットで画像を探して納得した。ラグビーボールみたいな瓜実顔で目が小さい。
■戸栗美術館 『初期伊万里-大陸への憧憬-展』(2019年1月8日~3月24日)
戸栗美術館は久しぶりに訪ねた。日本初の国産磁器「伊万里焼」の1610年代から1630年代頃までの作品を「初期伊万里」と呼ぶ。伊万里焼は、朝鮮出兵の際に日本に連行された朝鮮人陶工に始まるが、中国風の画題が好まれた。という説明だが、本家には似ても似つかない、おおらかさ・ゆるさが魅力。特に山水楼閣図は、どこでもないユートピアの趣きがあり、空想と郷愁を誘う。動物もかわいい。
■太田記念美術館 企画展『かわいい浮世絵 おかしな浮世絵』(2019年1月5日~1月27日)
気楽な気持ちで楽しめる「かわいい」「おかしな」浮世絵の特集。その企画意図は当たっていて、若いお客さんたちが、わいわい楽しみながら見ていた。私はヘンな生き物が登場する作品が好き。歌川芳員『東海道五十三次内 大磯 をだハらへ四リ』に登場する虎子石にも久しぶりに対面。
■21_21 DESIGN SIGHT 企画展『民藝 MINGEI - Another Kind of Art展』(2018年11月2日~2019年2月24日)
六本木ミッドタウンの庭園にあるデザイン専門施設で展示もおこなっている。今回、初めて訪ねた。日本民藝館の館長である深澤直人がディレクターをつとめた。あとで開催概要を読んだら「同館の所蔵品から146点の新旧さまざまな民藝を選んで展示」とある。実は、日本民藝館の温もりある展示室と、21_21の無機質な展示会場では、展示品の印象がずいぶん違って見えた。なんだか初めて見る感じの作品がたくさんあって、全て日本民藝館の所蔵品ではないのかしら。深澤直人氏個人のコレクションも混じっているのかしら、と首をひねった。こういう場所で展覧会をすることで、駒場の日本民藝館に新しいお客さんが足を運んでくれたら嬉しい。
今年の年末年始は、上野にムンクもフェルメールも来ていたが、結局ルーベンスしか行かなかった。私はルーベンスと聞くと、肉づき豊かな女性の裸体像を思い出すが、今回は男性の裸体像が多かった。神話・伝説を主題とした作品の中に『ローマの慈愛』と題し、若い娘が獄中の年老いた父親に自分の母乳を飲ませる場面を描いたものがあって、SNSなどで物議を醸していた。まあ確かに現代の感覚ではヘンな絵が多かったが、それもまたよし。
■東京国立博物館 特集展示『博物館に初もうで2019 イノシシ 勢いのある年に』(2019年1月2日~1月27日)
展示品は、古代中国の灰陶豚や玉豚、望月玉泉筆『萩野猪図屏風』など、 だいたい予想どおり作品で、あまり驚きがなかった。本館1階では「高精細複製品によるあたらしい屏風体験」と題して『松林図屏風』の高精細複製品と映像のインスタレーションを展示していた。2017年の「びょうぶとあそぶ」に比べるとこじんまりしたインスタレーションだったが楽しめた。東洋館の『王羲之書法の残影-唐時代への道程-』(2019年1月2日~3月3日)も充実。
■鎌倉国宝館 源実朝没後800年、鎌倉市制施行80周年記念特別展『源実朝とその時代』(2019年1月4日~2月3日)
最近、坂井孝一『承久の乱』でかなり詳しく実朝のことを読んだので、期待して行ったら、ハズレだった。「実朝ゆかり」の展示品は「頼朝ゆかり」に置き換えてもあまり問題ないものばかり。ただ甲斐善光寺の源実朝坐像を見ることができたのはよかった。神護寺の頼朝像と顔のかたちが似ていなくもない。『公家列影図』に描かれている実朝像とも似ていると解説パネルに書いてあったので、ネットで画像を探して納得した。ラグビーボールみたいな瓜実顔で目が小さい。
■戸栗美術館 『初期伊万里-大陸への憧憬-展』(2019年1月8日~3月24日)
戸栗美術館は久しぶりに訪ねた。日本初の国産磁器「伊万里焼」の1610年代から1630年代頃までの作品を「初期伊万里」と呼ぶ。伊万里焼は、朝鮮出兵の際に日本に連行された朝鮮人陶工に始まるが、中国風の画題が好まれた。という説明だが、本家には似ても似つかない、おおらかさ・ゆるさが魅力。特に山水楼閣図は、どこでもないユートピアの趣きがあり、空想と郷愁を誘う。動物もかわいい。
■太田記念美術館 企画展『かわいい浮世絵 おかしな浮世絵』(2019年1月5日~1月27日)
気楽な気持ちで楽しめる「かわいい」「おかしな」浮世絵の特集。その企画意図は当たっていて、若いお客さんたちが、わいわい楽しみながら見ていた。私はヘンな生き物が登場する作品が好き。歌川芳員『東海道五十三次内 大磯 をだハらへ四リ』に登場する虎子石にも久しぶりに対面。
■21_21 DESIGN SIGHT 企画展『民藝 MINGEI - Another Kind of Art展』(2018年11月2日~2019年2月24日)
六本木ミッドタウンの庭園にあるデザイン専門施設で展示もおこなっている。今回、初めて訪ねた。日本民藝館の館長である深澤直人がディレクターをつとめた。あとで開催概要を読んだら「同館の所蔵品から146点の新旧さまざまな民藝を選んで展示」とある。実は、日本民藝館の温もりある展示室と、21_21の無機質な展示会場では、展示品の印象がずいぶん違って見えた。なんだか初めて見る感じの作品がたくさんあって、全て日本民藝館の所蔵品ではないのかしら。深澤直人氏個人のコレクションも混じっているのかしら、と首をひねった。こういう場所で展覧会をすることで、駒場の日本民藝館に新しいお客さんが足を運んでくれたら嬉しい。