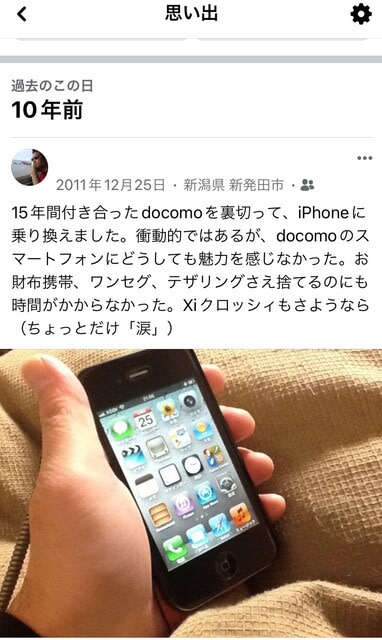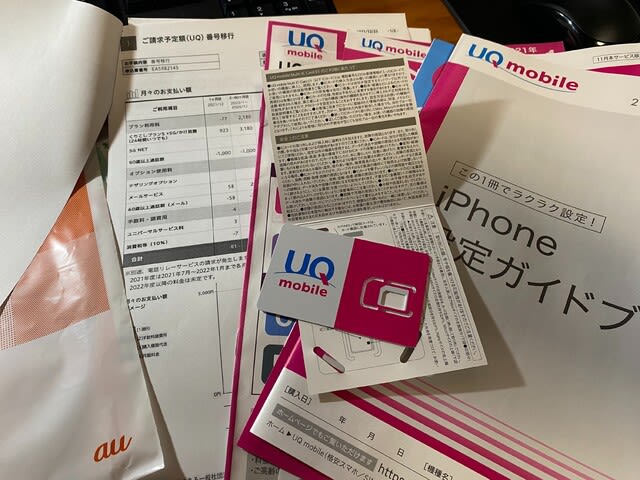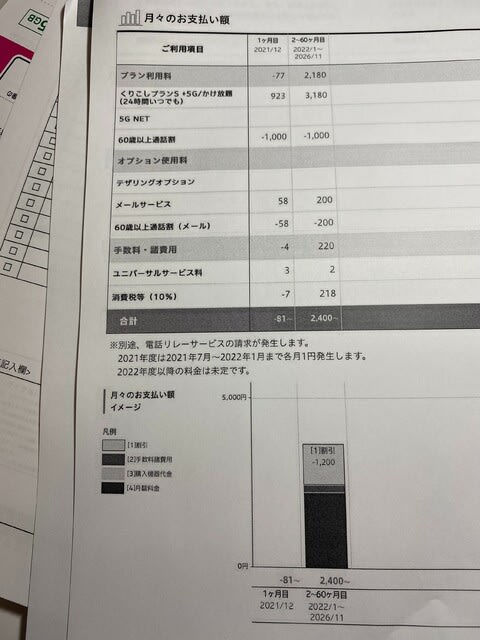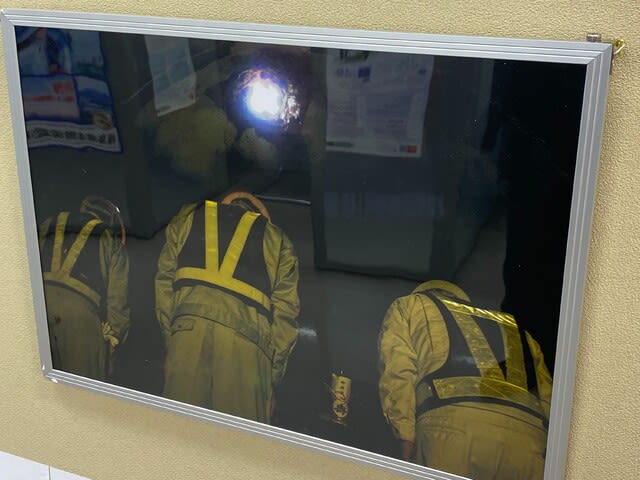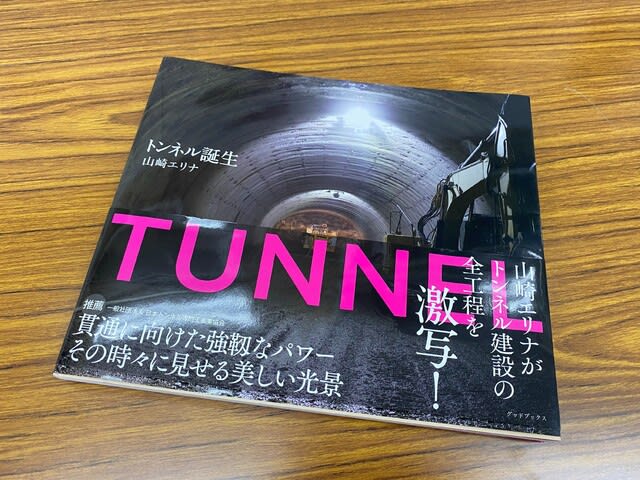コロナ禍で、出張以外で電車に乗ることはなくなった。記録を見ても、昨年秋口(2020年10月)に東北の被災地を巡る旅に出て以来、今年は全く出かけていないといっていい。乗り鉄・時刻表派にとっては、なんとも寂しい一年だった。
それでもたまに時刻表を見たり、写真の整理などをしたりしていると、JRがいよいよ減便に踏み切ったなどというニュースが気になり、地元新潟のダイヤ改正をチェックすることになる。

https://www.jreast.co.jp/press/2021/niigata/20211217_ni01.pdf
上越新幹線は、ご承知のとおりE4Maxが引退し、ますます存在感がなくなってきている?そんな中で、確かに減便になっている。まあ、東北新幹線も北陸新幹線も同様なので、新潟ばかりがというボヤキにはならないのだが…。
「JRニュース」の記載方法は微妙だ。E7(写真下)を増便するという記事を最初に持ってきてはいるものの、「輸送体系の見直し」というソフトな言い回しだが上下2往復分(東京~新潟間)が臨時列車に格下げ。事実上の減便だ。特に速達タイプの列車が減便されているので、東京は遠くなる気がする。
加えてE2(写真下)は希少価値となって、最後の職場が上越新幹線になる可能性も高い。マニアックなファンに支えられて乗車率向上といきたいが、E4Maxほどインパクトはありませんしね。まあ、東北新幹線でもすぐにはなくならないと思いますがー。


さて問題は地元の羽越線。いなほ号にも影響が出ています。新潟~秋田間で運行されていた特急いなほ5号、10号(1往復分)が酒田止まりになる。秋田まで運行されていた3本往復あるいなほが2本に減便ということだ。
加えて、いなほ3号、10号(1往復分)が7両編成から4両編成と短くなる。ここで問題になるのが編成の問題。現在、新潟車両センターにはE653系(写真下)いなほが8編成あるが、先頭車両の1号車はグリーン車で、普通車の4両編成には対応できないはず。
しかし、その後ニュースの下段には、同じE653を使用する特急しらゆき(写真下)が新潟~上越妙高間で1便減便。同じく4編成を持つしらゆきの1編成をいなほ4両編成に転用するのではないかと思われる。1往復とはいえ、4両編成のいなほは違和感ありありかも。


在来線普通列車では、村上以北の交流区間を、すでに磐越西線・米坂線で導入されているGV-E400(写真下:米坂線を走る同系気動車)に統一し、ワンマン運転にするという。キハ40系気動車(キハ40、47形、48形)は予備を含めて完全終焉。鉄道ファンにとってはこちらの方が問題だ。(調査の結果、現在、新津運輸区にはジョイフルトレイン「越乃Shu*Kura」以外、すでにキハ40系の配備はないとのこと。)
また磐越西線では、快速あがの(写真下)の運転を取りやめるとの記事も。会津若松・郡山方面への足として貴重な快速列車だったし、個人的には米坂線を使っての南回り(奥羽線・東北線・磐越西線)の周回ルートに影響がありそうだ(北回りは、奥羽線を北上し、陸羽東線から余目に出るコース)。
確かにコロナの影響で、どの列車も乗車率は低いということは否めない。ただ、地方の貴重な足と列車旅の風情が少しずつ削られていくようで、なんとも寂しい今回のダイヤ改正になりそうである。(ダイヤ改正は、2022年3月12日)


それでもたまに時刻表を見たり、写真の整理などをしたりしていると、JRがいよいよ減便に踏み切ったなどというニュースが気になり、地元新潟のダイヤ改正をチェックすることになる。

https://www.jreast.co.jp/press/2021/niigata/20211217_ni01.pdf
上越新幹線は、ご承知のとおりE4Maxが引退し、ますます存在感がなくなってきている?そんな中で、確かに減便になっている。まあ、東北新幹線も北陸新幹線も同様なので、新潟ばかりがというボヤキにはならないのだが…。
「JRニュース」の記載方法は微妙だ。E7(写真下)を増便するという記事を最初に持ってきてはいるものの、「輸送体系の見直し」というソフトな言い回しだが上下2往復分(東京~新潟間)が臨時列車に格下げ。事実上の減便だ。特に速達タイプの列車が減便されているので、東京は遠くなる気がする。
加えてE2(写真下)は希少価値となって、最後の職場が上越新幹線になる可能性も高い。マニアックなファンに支えられて乗車率向上といきたいが、E4Maxほどインパクトはありませんしね。まあ、東北新幹線でもすぐにはなくならないと思いますがー。


さて問題は地元の羽越線。いなほ号にも影響が出ています。新潟~秋田間で運行されていた特急いなほ5号、10号(1往復分)が酒田止まりになる。秋田まで運行されていた3本往復あるいなほが2本に減便ということだ。
加えて、いなほ3号、10号(1往復分)が7両編成から4両編成と短くなる。ここで問題になるのが編成の問題。現在、新潟車両センターにはE653系(写真下)いなほが8編成あるが、先頭車両の1号車はグリーン車で、普通車の4両編成には対応できないはず。
しかし、その後ニュースの下段には、同じE653を使用する特急しらゆき(写真下)が新潟~上越妙高間で1便減便。同じく4編成を持つしらゆきの1編成をいなほ4両編成に転用するのではないかと思われる。1往復とはいえ、4両編成のいなほは違和感ありありかも。


在来線普通列車では、村上以北の交流区間を、すでに磐越西線・米坂線で導入されているGV-E400(写真下:米坂線を走る同系気動車)に統一し、ワンマン運転にするという。キハ40系気動車(キハ40、47形、48形)は予備を含めて完全終焉。鉄道ファンにとってはこちらの方が問題だ。(調査の結果、現在、新津運輸区にはジョイフルトレイン「越乃Shu*Kura」以外、すでにキハ40系の配備はないとのこと。)
また磐越西線では、快速あがの(写真下)の運転を取りやめるとの記事も。会津若松・郡山方面への足として貴重な快速列車だったし、個人的には米坂線を使っての南回り(奥羽線・東北線・磐越西線)の周回ルートに影響がありそうだ(北回りは、奥羽線を北上し、陸羽東線から余目に出るコース)。
確かにコロナの影響で、どの列車も乗車率は低いということは否めない。ただ、地方の貴重な足と列車旅の風情が少しずつ削られていくようで、なんとも寂しい今回のダイヤ改正になりそうである。(ダイヤ改正は、2022年3月12日)