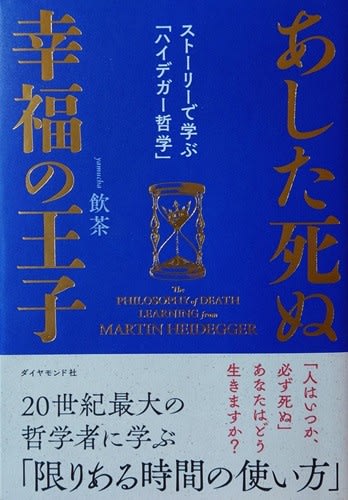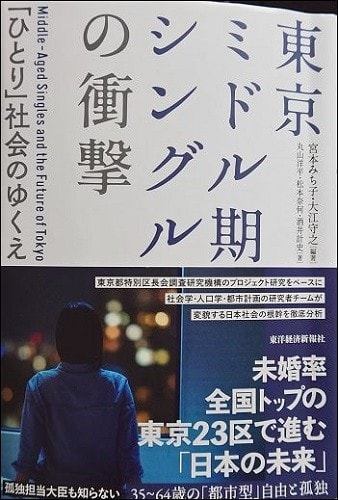話題の医療ノンフィクション「透析を止めた日」を読みました。
著者は既に数々の賞も受賞しているノンフィクション作家の堀川惠子さん。
ノンフィクション作品と言えば、取材を重ねて全体像を構築して真実に迫るという手法。
しかしこの作品はなんと堀川さん自身が夫である林新さんの透析治療とその過酷さを目の当たりにして葛藤し戦い、そしてその戦いに敗れた記録であり、その過程をノンフィクション作家の視点として涙を乗り越えた書かれた鮮烈な作品です。
構成は大きく二部に分かれていて、前半の第一部は腎不全であることを知りながら結婚した林さんとの病気との戦いの記録。
林さんは腎不全から血液透析を余儀なくされますがまずは「止めたら死ぬ」という透析の過酷さが描かれます。
一時は老いた母親からの腎臓移植で透析をしなくて済む時期もありましたがやがてその腎臓も機能を停止し再び透析の世界に戻ります。
シャントという透析専用につくられた血管から血液を外に出して老廃物をろ過して又体内に戻す透析は一週間に三度ほど定期的に確実に行わなければ呼吸困難や高血圧、心不全などで確実に死に至ります。
しかしシャントから行う血液透析も最後にはさまざまな要因で続けることができなくなります。
林さんの場合も最後には全身の痛みが出て透析を止める日が来るのですが、そこから先は塗炭の苦しみを経て亡くなるしかないのだと。
初めて知ったのですが、いわゆる「終末期に痛みをコントロールする緩和ケア」が普及してきたと言いながら日本ではそれはガンと一部の心不全の患者だけに適用される医療行為なのだそう。
海外では腎不全を含めたもう少し幅の広い病気に対して門戸が開かれているところもあるようですが、日本ではそこにまだ理解とリソースが足りていないのが現状なのだそう。
本書ではそうした現状の改善希望が強く訴えられています。
◆
そして後半の二部では、嵐のような夫の看取りを終えた後で透析をめぐる医療の現場に深く入り込んで、よりよい透析環境を取材した記録が語られます。
実は透析には前述のシャントを構築して病院で機械を介して行う血液透析のほかに、自分自身の腹膜を使って行う「腹膜透析」という手段があるのだと、著者自身も取材によって知ります。
そして透析患者のまだ3%にしか行われていない腹膜透析では、何時間も機会に縛り付けられることなく、本人自身のケアや周りのサポートによって自宅や介護施設でも日常に近い生活ができるのだと知って衝撃を受けます。
またその日常に近い生活は終末期の最後まで続けられ、透析患者であっても家族に看取られながらの穏やかな死を迎えられる事例が多いのだと。
そんな中で腹膜透析という医療技術は真に患者に寄り添った一部の熱心な医師によって福音の輪が広がるものの、その医師がいなくなればまた消えてゆくという広がらないものなのだそう。
それは現在の医療制度では、血液透析は病院にとって儲かるビジネスになっている側面があって、認知症や重傷で意識のない患者でも透析を行うことで点数を稼いでいる病院も少なくないといいます。
血液透析には大量の水や電気が必要になりますが、災害時などでそれらが絶たれたときに注目を浴びたのがそれらを必要としない自己完結型の腹膜透析だったというエピソードも紹介されています。
ただ著者自身が、「夫の生前に腹膜透析の存在を知っていたとしてそれに踏み切れたかどうかは自信がない」とも正直に書いています。
それは患者側の知識の問題であったり医療者側の熱意や関心の度合い、医療提供者側の事情など様々な要素があるでしょう。
しかし著者の堀川さんは、終末期の透析患者の辛さを身をもって体験したからこそ、改めて透析における希望の光を見出そうと取材を続け、まさに思いを同じくする医療者に出会うことができました。
しかしまだその広がりは微々たるもので、病気の患者にとって尊厳に満ちた生と穏やかな死を迎えられる日はまだ遠い。
このような水面に石を投じるような良書によって社会や行政や政治にも関心と行動が広がることを期待したいものです。