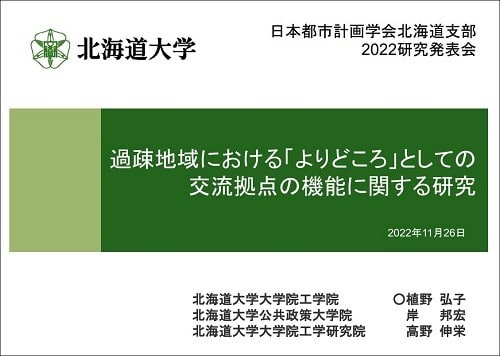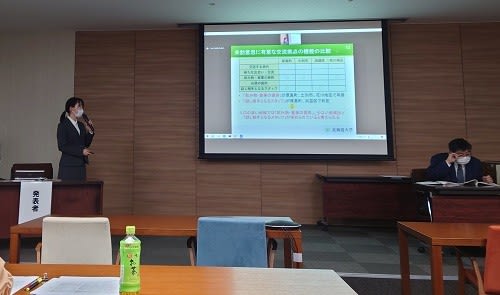昨日は会員になっている日本都市計画学会北海道支部の研究発表会が北大工学部の会場で開催されました。
都市計画やまちづくりに関する日頃の研究成果だけではなく、実践報告や現場での実務報告も含めた幅広い発表が期待されています。
また今回はテーマ論文も募集して、そのテーマは「よりどころ」というキーワードでした。
過疎や災害などに悩む地方や地域にとって「よりどころ」とはどのような空間なのか、ということを問いにしてそれに応える論文が集まりました。
研究発表会はまず基調講演として、胆振東部地震で大きく被災した安平町の及川秀一郎町長から『安平町における北海道胆振東部地震からの復興と「よりどころ」としての場所づくり』というテーマで50分の基調講演をいただきました。
及川町長は初当選直後に大地震で被災し、建物や人的被害を受けたところからいかに今日まで復興をしてきたかについてお話しいただきました。
その中では、「ピンチをチャンスに」という思いで震災前よりも魅力的な町にするという意思を明確にし、具体的には被災した学校を小中学校が合築となって建てなおすとともに、学校を開かれた公民館的な機能を融合させて地域のよりどころ、たまり場として再スタートするという構想を説明されました。
学校を公民館的に使うというのは教育サイドから見るとあまりよく思わない人もいたのかもしれません。
しかし町長曰く、「被災直後は子供たちは公民館の2階、3階で授業を行っていて、町民が出配流する空間で勉強していたことに何の違和感もなかった。それならその逆でも可能だし、それがこれからの地域を一つにする核になりうる。そしてそういう子供たちへの教育の充実が魅力的なものになれば移住・定住への魅力も増してゆくはずだ」とのこと。
安平町立早来学園は、来年4月に開校予定です。
◆
続いては応募者による研究発表会。
一人7分の発表+3分の討論・質疑応答というスタイルで全部で14編の論文発表がありました。
非常に多角的に現代社会を切り取った力作でした。
発表論文からは、優秀なものに対して支部長賞、支部優秀賞、支部奨励賞などの賞が与えられますが、今年の最優秀論文に当たる支部長賞は北大工学部修士1年の植野弘子さんによる「過疎地域における『よりどころ』としての交流拠点の機能に関する研究」が受賞されました。
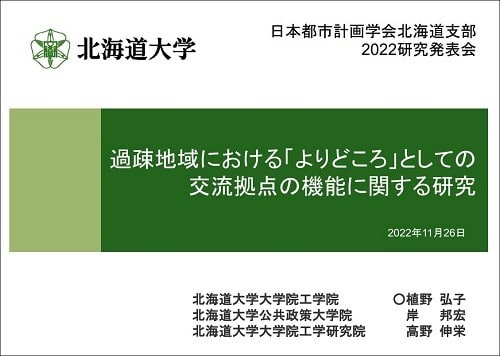
この研究のポイントは、過疎地域において地域の人々が訪れたくなるような交流拠点の機能にはどのようなことがあるのか、ということの調査研究です。
具体的には北海道内の厚真町、士別市、石狩市浜益区、石狩市花川地区の4か所での意識調査を行い、「お酒の提供のある/なし」「交流する世代が同世代/多世代」「飲み物食事提供のある/なし」「新たな出会いのある/なし」「話し相手となるスタッフのある/なし」の組み合わせの違いによって、「週一回~月2回程度訪れたい」と「訪れたくない」という反応がどのように変わってくるかを調べたのです。
この結果として、「飲み物・食事の提供(があれば行きたい)」が厚真町、士別市、花川地区で統計的に有為となり、また「話し相手となるスタッフ(がいれば訪れたい)」が厚真町、浜益区で有為(=ほぼその仮説で合ってる)となりました。
これらの結果が出た地域の特徴としては、厚真町というのは渡海から離れた辺地性が高いこと、士別市は人口も一定程度あって都市的、浜益は人口の減り方が大きく高齢率も高いことから過疎的であることが示されました。
この結果、住民の来訪意思に影響を与えるような交流拠点の機能が明らかになったことや、それらは地元の特性に照らしたアプローチが有効ではないか、ということが示されたということになりました。
しっかりした分析力に加えて、今年の「よりどころ」というテーマにも合致していて、審査員からの評価が高く支部長賞の受賞となりました。
こんごもさらに研究を深めていただくことを期待したいと思います。
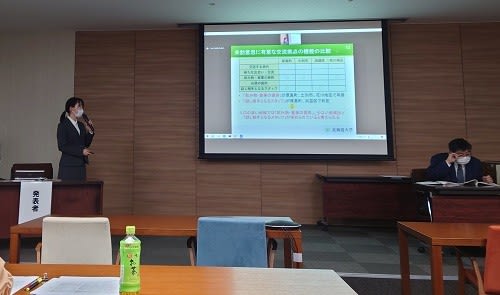
◆ ◆
ただ面白いのはここからです。
研究発表会が終わった後で、関係者有志で近くの居酒屋に繰り出して、改めて今日の発表会全体をお酒の力も借りながら振り返るこの時間が楽しいのです。
この延長戦には支部長賞受賞の植野さんも参加してくれて、会場では話せなかったエピソードなども含めて笑いあり感心ありの会話が盛りだくさん。
そんななか、この論文の指導教官の方からの話で「今日の彼女の論文では、話し相手だとかお酒の提供、飲食の提供なんかのあるなしで、行きたい/行きたいとは思わない、という行動に繋がるという事だったのですが、この手の機能が満載なのが実は街の"スナック"なんですよ」という一言で場が大いに盛り上がりました。
「なるほど、スナックですか!ママさんという話し相手がいて、お酒や食事が提供されて、他人との交流もあると」
「そうなんです。人々が集まってくる『よりどころ』にはやっぱりそういう要素が必要で、それを知らず知らずに体現しているのがスナックだということです」
「ははー、なるほど、面白いですねえ」
「さらに言えば、NHKの朝のテレビ小説を見たことがありますか。あのドラマには必ずと言って良いほど、地域の登場人物が一堂に会してともに悩んだりともに笑い合うシーンが出てくるのですが、その舞台にはスナックが実に多い。あとは食堂とか喫茶店もありますが、それでも店主などが話し相手になって、そこにいる人たちの話題を回してゆくんです。朝の連続テレビ小説におけるスナックの位置づけって、論文のテーマになるかもしれませんよ(笑)」
どんなよりどころを作ればよいか、という研究も研究として、実際にそれを実現しているよりどころがスナックだったとは。
そういえば日頃自分からは行かないけれど、地方への出張で飲んだ時などは二次会がスナックへ行くことが多いですね。
しかし「よりどころ」をさらに、教育や介護・福祉などいろいろな面からのアプローチも考え合わせるともっといろいろな可能性がありそうですね。
皆さんにはよりどころはありますか?
知的で楽しい一日でした。