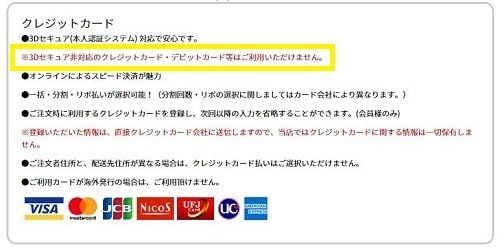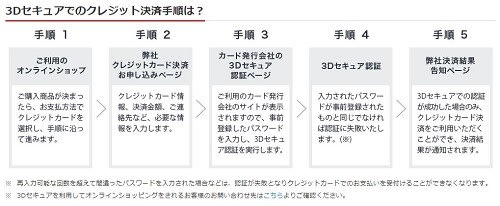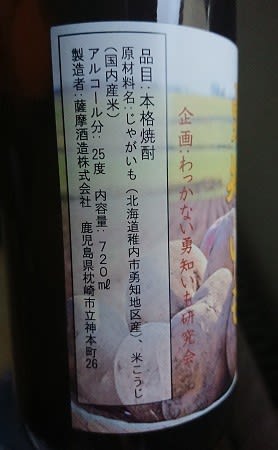再来年度の2022年度から高校の学習指導要領が大きく変わります。
各科目ごとに大きな変更があるのですが、そんななか「地理」という科目は今までの「地理A」「地理B」という区分から必履修の「地理総合」と選択の「地理探求」に変わります。
そしてこの必履修の「地理総合」では、内容構成として「A 地図や地理情報システムと現代世界」,「B 国際理解と国際協力」,「C 持続可能な地域づくりと私たち」の三つの大項目で構成されます。
文字面だけを見ると大変な内容ですが、この中身をつらつらみてみるとそれは「地域の課題を自らみつけてそれを分析して解決の提案を行う」といったイメージが含まれていて、それはこれまで都市計画学会が研究を行ってきたまちづくり分野の調査研究に非常に近しいジャンルであることがわかります。
そしてこうした地域の問題に関心を持つような授業が行われるのであれば、それを少しでも充実させて学習効果を高められることができれば、将来の地域を支える人づくりにつながるものと、期待と希望があります。
そこで都市計画学会では、こうした高校での地理総合授業に何らかの形で関わりを持って何か役に立てないか、という活動を始めています。
私も支部長として、北海道における地理総合を通じたまちづくり授業には非常に期待が大きく、学会支部としてできることを模索しています。
◆
そんなときにある友人から、「小松さん、しかしそれはこちらができることを提示するだけじゃなくて、まずは高校の先生の話を聞いて、そこから何が必要かを絞り出すことが始めなんじゃないか。しかも全道で一斉に動きが起きるわけでもないから、こうした我々のイメージを理解してくれる先生を見つけ出して、協力し合えるような成功事例を作ることが大事だと思うよ」というアドバイスを受けて、すとんと腹落ちした次第。
そんなことから先日人づてにある高校を訪問して、その高校での現在の活動からこれからについての話を伺ってきました。
すると話を聞いてくれた先生は開口一番「小松さん、高校には入ってくる子たちのレベルという現実がありますよ」と言い出しました。
「偏差値で言うと、大体55以上の子たちは黙っていても勉強はできていきます。偏差値が45~55の子たちは教師も一番燃える層です。ここに学習成果を上げれば上のステージに上がることができる可能性があります。
しかし45以下で入ってくる子供たちは正直言って大変です。日本の教育の現実として、小学校・中学校の指導要領が求める力量に達していなくても卒業して半分義務教育化した高校に入ってきます。
そしてうちはまさにそういう子たちが多い高校です。
ところが高校の教師は高校レベルの授業をすることが求められるので、力が不足している子供たちは勉強についてこれなくなり、うらぶれてしまうということも多いのが実際の姿なんです」
非常に厳しい見方ですが、これが現代社会のある一面でもあるのでしょう。
「我々高校側は、その現実からスタートして彼らに3年間という決められた時間の中でスキルとモチベーション、あるいはこの両方を高めるようなことが求められています」
大変なことはよくわかります。しかしこの高校ではそんな現実からスタートしても子供たちに様々な体験をしてもらうことを通じて、地域社会に触れて地域から可愛がられ、自己肯定的になるよう促すユニークな教育を行っていました。
「私たちの高校では、地域の活動に生徒たちを送り込んで地域に触れさせそこから自分たちが何を感じるかを大事にしています。でもそれには敵がいるんです」
「敵とは何ですか?」
「クラブ活動です」「クラブ活動?」
クラブ活動では特に指導を行う指導者にとっては子供たちがクラブ活動に熱中することを求めることが実に多い。
そのため「地域活動に行きたいのでクラブを休みます」という子供たちを頭ごなしに否定する指導者は多いことでしょう。
しかし子供たちが自ら「自分たちは今この瞬間何をなすべきか」を考えて決断することこそ真にせいちょうするということに他ならないはずです。
「うちの高校では最近になってようやく、そうした生徒の判断を尊重する空気が生まれてきました。そして子供たちも地域活動を通じて著しく成長する子たちも増えてきました。子どもたちのその本気に繋がるのは『出会いと原体験』なんだと思います」
「出会いと原体験」に誘い、それを繰り返すことで子供たちの成長を促すという教育方針は実に立派だと感じました。
実際こちらの高校では、我々都市計画学会がイメージしたような地域に出張ってゆく活動を日常的に行っています。
こういうところと連携をして、その学習効果をさらに高めるような支援やお手伝いをするにはどういう道筋があるのでしょう。
まずはこれからも高校の話を聞きながら活動のイメージを固めてゆく必要がありますが、私自身もこうした現場のリアルな話が聞けるのはすばらしい「出会いと原体験」に他なりません。
今回は元気が出る話を聞けましたが、さて次はどんな現場の姿を目の当たりにすることでしょう。
高校生たちに自分たちの町や地域に関心を持ってもらうことへのお手伝いの仕方を模索しています。