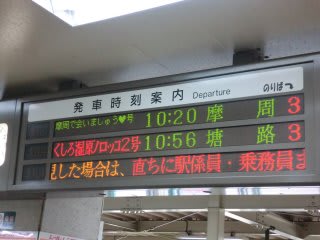ある詩吟の会の創立記念吟道大会で挨拶を述べてきました。
こういう方面には全く素養のない私なので、道内各地から地区を代表するお歴々と共に来賓席に座っているのは何とも気恥ずかしい限りです。
一部には和歌や俳句などもあるそうですが、主には漢詩に節をつけて詩情を表現するという吟道は江戸時代後期に盛んになり、幕末の志士たちは悲憤慷慨を詩に乗せて謡ったそう。
今のような形が整ったのは大正から昭和初期に優れた吟詠家が活躍したおかげで、今日の様々な流派の礎がこの時期に築かれたのだそうです。
漢詩を素読して楽しむというのは分かりますが、これに節をつけて声を出すことを一つの芸術や吟道として成立させるというのは、何にも道を見出す日本人的な楽しみ方だと思わざるを得ません。
市政を全うしようとするなかで、数多くの市民の皆さんとお会いしますが、願いはひたすら一人一人が健康で文化的な生活を送っていただきたいということです。
詩を吟じるというのは、まずは詩を覚えるのに頭を使い、肺と腹筋とのどを使って浪々と声を発するだけではなく、さらには仲間たちと切磋琢磨しながら上手になろうとする向上心を保ち続けるというのですから、健康になるためには非常に良い活動のように思います。
会長さんの挨拶の中では、残念ながら会員数は減少しているとのことですが、少しでも多くの方が参加して健康な生活を営んでいただきたいものです。
いただいた資料には、何人かが合唱のように吟じる「合吟(ごうぎん)」の欄に、朱子学を開いた朱熹の「偶成」という詩が載せられていました。
曰く、
少年老い易く学成り難し
一寸の光陰軽んずべからず
未だ覚めず池塘春草(ちとうしゅんそう)の夢
階前の梧葉(ごよう)已(すで)に秋声
心が洗われるようです。
こういう方面には全く素養のない私なので、道内各地から地区を代表するお歴々と共に来賓席に座っているのは何とも気恥ずかしい限りです。
一部には和歌や俳句などもあるそうですが、主には漢詩に節をつけて詩情を表現するという吟道は江戸時代後期に盛んになり、幕末の志士たちは悲憤慷慨を詩に乗せて謡ったそう。
今のような形が整ったのは大正から昭和初期に優れた吟詠家が活躍したおかげで、今日の様々な流派の礎がこの時期に築かれたのだそうです。
漢詩を素読して楽しむというのは分かりますが、これに節をつけて声を出すことを一つの芸術や吟道として成立させるというのは、何にも道を見出す日本人的な楽しみ方だと思わざるを得ません。
市政を全うしようとするなかで、数多くの市民の皆さんとお会いしますが、願いはひたすら一人一人が健康で文化的な生活を送っていただきたいということです。
詩を吟じるというのは、まずは詩を覚えるのに頭を使い、肺と腹筋とのどを使って浪々と声を発するだけではなく、さらには仲間たちと切磋琢磨しながら上手になろうとする向上心を保ち続けるというのですから、健康になるためには非常に良い活動のように思います。
会長さんの挨拶の中では、残念ながら会員数は減少しているとのことですが、少しでも多くの方が参加して健康な生活を営んでいただきたいものです。
いただいた資料には、何人かが合唱のように吟じる「合吟(ごうぎん)」の欄に、朱子学を開いた朱熹の「偶成」という詩が載せられていました。
曰く、
少年老い易く学成り難し
一寸の光陰軽んずべからず
未だ覚めず池塘春草(ちとうしゅんそう)の夢
階前の梧葉(ごよう)已(すで)に秋声
心が洗われるようです。