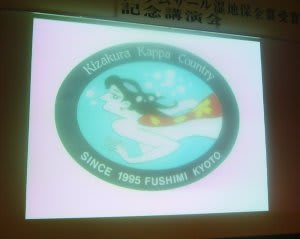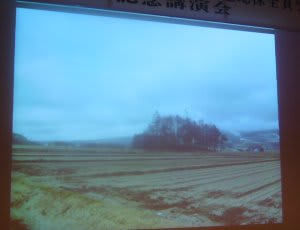釧路湿原にとっては大恩人である湿原研究の大家辻井達一先生がこの7月にルーマニアのブカレストで開催されたラムサール条約締結国会議でラムサール湿地保全賞を受賞された。
また、この秋の叙勲で瑞宝小受章も受賞されたことから、釧路では有志が集まって、先生の両賞受賞をお祝いする会を催し、併せて先生には「ラムサール条約湿地これから」と題して記念講演をお願いした。
講演会では私が釧路市を代表してお祝いとお礼の挨拶をする機会をいただき、かつて北大で辻井先生の講義を受けていた私としては、光栄だった。

◆ ◆ ◆
さて、辻井先生の講義である。
先生曰く、最初は湿地の保全などと言えば、「なんだ、谷地か」と馬鹿にされていたもので、おそらく環境省でも「ラムサール条約って何だ?」と言われるほど関心は薄かったろう。
それが釧路でラムサール条約会議が開催されたことで初めて日本で、あるいはアジアでも湿地が陽の目を見たのだろうと思う。
今日はテーマを三つ用意した。
まず最初は、「全体のテーマとしてラムサール条約湿地の現状」である。
ルーマニアの首都ブカレストでCOP11が開催されたが、ラムサール化学賞受賞の際に、「スピーチは三分以内で」と言われて、カッパの話をしようと思った。
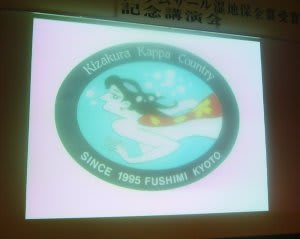
【お酒「黄桜」のかっぱキャラ】
カッパは綺麗な水にいてやや不気味な妖怪として描かれるが、小島功さんの絵にはかわいらしく描かれている。
日本人参加者からは「カッパの絵としてはちょっと色っぽすぎるのではないか(笑)」という声もあったが、まあいいんじゃないか。黄桜からはまだ何ももらっていないが今後交渉してみよう。
「私も湿原研究をしすぎてカッパの水かきがついてきたのじゃないか、と思うが、今後も綺麗な水を守る活動を続けて行こうと思う」とまとめた。
◆ ◆ ◆
またスペインで2002年に行われた会議では、普通はラムサールは水鳥が良く出てくるのに、ここから少しの時期シンボルマークには鳥が消えて魚が出てきた。
今回のルーマニアではマークに鳥が復活して鳥屋さんは胸をなで下ろしたのではないか(笑)
要は湿地といえば水鳥が保護の対象であったのが、魚や植物や、それを活用する人までもが皆恩恵を受けているということであって、それがシンボルマークから水鳥が姿を消した理由だったのだ。
スペインのマークでは水草と魚がはっきり描かれているが、人や水の流れをデザインするということが流行ったのだった。
◆ ◆ ◆
では二つ目、「これまでの日本のラムサール湿地の特徴」について語ろう。
日本には、雨竜沼、阿寒湖、サロベツ原野など多様な湿地が随所に見られる。
これがロシアだと何日も同じ原野の景観がずっと続くものだが、それに比べると日本は実に多様な湿地環境がある。
ラムサール会議は日本で、そしてアジアで初めて開かれたと言ったが、その際東北海道の場合、釧路以東根室までの間で小さなスケールだが国際フィールドシンポジウムを開いた。
参加者はほとんどがヨーロッパの学者だったが、みな「釧路から根村までの間にタイプの違う湿地が30分走るごとに一つ見られて非常に興味深い。博物館の部屋のドアを挙げると違う展示物が見られるのと同じように、釧路から根室には、厚岸、ペカンぺウシ、霧多布湿原、風蓮湖、尾岱沼、根室半島、などが次々に見られるのだ。そういうところは世界でも極めて珍しいのではないか」という反応だった。
却って自分たちのように、毎日のように同じポイントを見続けている地元民には一種の慣れが出てきてしまって真の価値に気がつかないことがある。
◆
「ニューヨークのセントラルパークには中央に池があるが、かつての池を残そうという素晴らしい感性の都市計画屋がやったのだろう」
皇居の中にも多くの池が残っている。私は次のラムサール湿地を、今は汚いが道頓堀で行けないか(笑)とすら思う。
これまではラムサール湿地と言えば「綺麗な場所」ばかりなのだ。
道頓堀は阪神が勝つと人が飛び込むようなところだが(笑)、ラムサール湿地になることを機会にして綺麗にするということだってあるのではないか。環境省は十分に研究して欲しい。
◆
次に湿原の恩恵について話そう。琵琶湖の鮒寿司。魚だというと欧米人も二の足を踏むが、「チーズだよ」というと平気で食べる。

【今やこのおおきさだと1万円はするとか】
鮒寿司の材料であるニゴロブナは琵琶湖の外にある内湖で育つのだが、米を作ろうというので80%を田んぼにしてしまった。
ところが今や鮒寿司が1万円で売れるというので、いまや米よりも内湖を復活してニゴロブナを増やそうという動きになってきた。現金な話だが、私はそれでも良いのではないかと思う。
その結果として内湖が復活するなら湿原の復活だ。決してマイナスになるものではない。
伝統的食文化の再生といえば十分に説明ができるだろう、ということで大いに賛成したい。
◆
アイルランドのアイラ島というところでは泥炭を掘っている。この泥炭で麦芽を燻すことでアイラウイスキーというのができるが、クレオソートを飲んでいるかのような強烈な香りがするウィスキーが出来上がる。
ウィスキーの原酒ができたときに、天使の分け前「angel's share」というのがあって、分量が減るのだが、そこに最後に泥炭を通ってきた水を足して泥炭の香りを付けた酒にする。
このアイラウィスキーを生の牡蛎にちょっとたらして食べるととても美味しいのだ。
なぜ厚岸でやらないのかなあ。東北海道の名物に十分なると思う。
◆ ◆ ◆
さてそれでは最後に三つ目の、「これからどうするか」についてだ。
2012年のCOP11では「湿地のツーリズム」というのが提唱されたが、北海道の大沼がエコツーリズムとしてラムサール湿地に登録された。

函館の人たちにとっての大沼は、函館山の次にお客さんを連れて行く自分たちの庭でありツーリズムの対象だ。
しかしおそらく大沼を湿地としては捉えていなかっただろうから、湿原という意味で捉えたのははじめてだ。
実はここをラムサール湿地とするのならエコツーリズムしかないと思ったが、それならば駒ヶ岳まで入れるべきだと思った。
それは『流山』と呼ばれているが、駒ヶ岳が溶岩を流し込んだ末端が流山なのであって、陸地にも残っていたりそのいくつかが湖の中の島になっている。
溶岩流がはっきり分かっているというのはこの駒ヶ岳しかないのであって、北海道に加わった13番目の登録湿地としていいのじゃなかろうか。
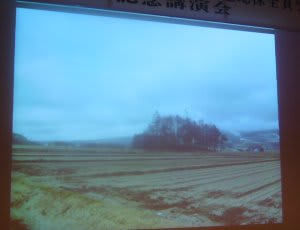
【これが陸に残された流れ山だ】
◆
さて、最後に尾岱沼の打瀬船である。
尾岱沼は打瀬船も含めて登録湿地になっているが、ここは北海シマエビの優良な漁場である。
なぜいまでも打瀬船を使っているかというと、アマモに稚エビが育つのだが、これをスクリューでかき回してしまっては行けないからだ。つまり取りすぎないための経験であり知恵なのだ。
もともと尾岱沼をラムサール登録湿地にするとなったときに、最初地元の漁場は反対をした。
しかし「そうではない。昔ながらの漁法で取っているということは一種のブランドになる。現にここで取れているシマエビは他に比べると二割ほど高い。ひげ一本折れていない、が売り物でブランドなのだ」
特にファストフードに対するスローフードに対してはちゃんと金を出すという時代になりつつある。我々はこれを先取りすべきなのだ。
◆
似たようなことは霧多布湿原をラムサールにする時にもあった。
最初漁協は、「我々は昆布でやっているが湿原とどんな関係があるのだ?」と反対だったのだ。
そのときにある先生が、湿原から流れ出る鉄分が昆布を育成するのに役立っているという論文を書いてくださり、それを説明したところ漁協は一夜にして反対を取り下げた。
◆
これからはワイズユース(賢い利用)ということで、それは利息だけを使って元手には手をつけない、という考え方だ。
利息だけで充分やれる世界として産業と十分に折り合いをつける社会でありたいと思っているのだ。
◆ ◆ ◆
辻井先生は最初から湿原もワイズユースで行くべきだとおっしゃっていた。保全のための保全では力が尽きてしまうからだ。
水鳥だけでなく、虫も植物も、周辺で生活をする人間ですら湿原の恩恵を受けている。
元手をなくさずに利息だけで、というのは辻井先生らしい素晴らしい考えだ。
最初からこの思想で活動ができた釧路湿原は本当に幸運だったと思う。
辻井先生におかれましては、これからも健康でご活躍をお祈りしたい。今日は誠にありがとうございました。