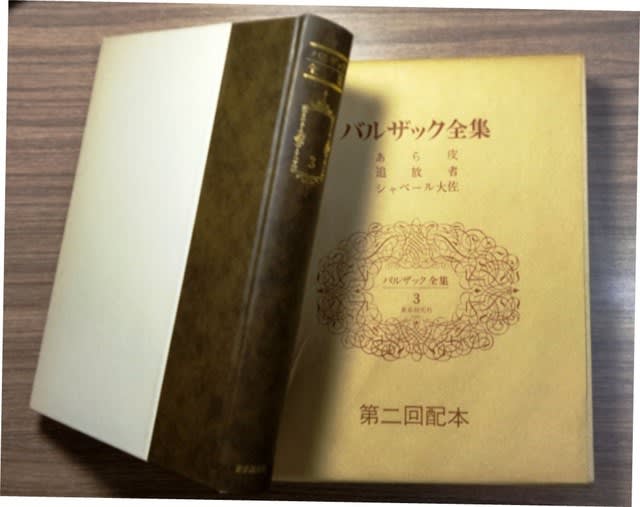「あら皮」が収められた、バルザック全集第3巻に併載された「シャベール大佐」を読んだ。これは「面白」かった。1832年の刊行。
最初は、巻末の解説(川口篤)を読むだけでスルーするつもりだったが、ぱらぱらとページをめくってみると、面白そうだったので、読むことにした。枚数も2段組み約50ページ、文庫本なら100頁程度だろうか、分量も丁度よかった。
実は、昨日からBSのAXMミステリー・チャンネルで「オックスフォード・ミステリー ルイス警部」を連続放映しているのだが、それを観ないで「シャベール大佐」を読んだ。
外は梅雨明け近い大雨だった。雨の日の読書は気分がよい。
テーマは、(法律的にいえば)<失踪宣告と重婚>である。「イノック・アーデン」、わがモームの「夫が多すぎて」から、映画「ひまわり」まで、このテーマを取り上げた作品はいくつかある。
夫婦の一方がいなくなってしまう。失踪の原因は様々である。結婚生活が嫌になって意図的に蒸発する場合もあれば、事故や事件に巻きこまれて殺されてしまったが遺体が発見されない場合もある。船舶の遭難(タイタニック号!)や、戦闘行為のために死亡したと思われるが遺体が見つからない場合もある(「ひまわり」や「シャベール大佐」がこれである)。
そのような場合には、わが民法では家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができ、裁判所が失踪宣告をした場合には、前者(普通の失踪)であれば、最後に音信があった時から7年経過した時に死亡したものと見なされ、後者(危難による失踪)であれば船舶の沈没または戦闘がやんだ時に死亡したものとみなされる(民法30、31条)。
このような生死不明の人間の配偶者らに、いつまでも行方不明者の財産を維持、管理させたり、婚姻を継続させて帰還を待たせるのは酷であるという考えによる。
もし失踪者が生還した場合には失踪宣告は取り消されるが、その場合でも、失踪宣告中に善意で(失踪者が生きているとは知らずに)行なった契約(相続財産の売却など)は、そのまま有効とされる(民法32条)。
失踪宣告の後、失踪宣告の取消し前に、(配偶者が死んだものと思って)生存配偶者が再婚した場合の、再婚の効力についてわが民法には規定はないが、常に再婚を有効とし前婚は復活しないとする説、双方が善意の場合にのみ再婚を有効とし、悪意の場合は前婚が復活するとする説、前婚・再婚ともに有効であり、再婚のほうが重婚となるとする説など、学説は対立している。
バルザック当時のナポレオン民法には、失踪(生死不明)宣告に関してわが民法より詳細な規定がある。生死不明が4年間継続した場合に失踪宣告の判決を申し立てることができ(115条)、失踪宣告が取り消された場合には、生還した失踪者は、この間に再婚していた配偶者に対して、再婚の異議を申し立てることができる(139条)とされていた(中村義孝氏「ナポレオン民法典」立命館法学による)。
さて、「シャベール大佐」である。
ナポレオンのモスクワ遠征に従軍して、負傷し敗走時に死んだものと間違われて遺体置き場に捨てられたシャベール大佐が、現地の人に助けられ、這う這うの体でパリに戻ってきた。しかし妻は、夫からの手紙を受け取って、夫(大佐)が生きていることを知っていたにもかかわらず、死亡したものとして、彼の財産や年金を相続し、別の男性と再婚していた。
シャベール大佐の訴えを聞いた若い代訴人は、死亡証書などを取り寄せるなどして、依頼人が本当にシャベール大佐であることを確認したうえで、示談のために妻のもとを訪ねる。
妻は新しい夫を上院議員にすべく、スキャンダルを恐れており、代訴人が提案する示談に応じるかの意向を表明する。しかし大佐に財産を返す意志はまったくなく、彼をだまして精神病院に入れてしまおうともくろむ。
このことを大佐は知ることになるが、大佐は怒りはするものの、妻のもとを去っていく。
法廷闘争の描写を期待したぼくは肩透かしを食った。バルザックは<法廷もの>を書く気はなかったようだ。
法科大学で学びながら、公証人(代書人だったかも)書記の書生を務めた経験をもつバルザックは、裁判官職が売買され賄賂がまかり通る王政復古、七月王政当時のフランスにおいて、裁判によって正義が実現するとは考えていなかったのだろう。
もともとこの作品は「示談」という題名で公表され、後の1844年にいたって「シャベール大佐」に改題されたという(川口解説、316頁)。代訴人は、最初から裁判ではなく、妻との駆け引きによる示談を目ざしていたのである。
彼が描きたかったのは、ナポレオンを信奉して彼の戦争に従軍し、武勲も立てたが(エジプト遠征に参加した軍人を「エジプト人」と呼んだそうだが、シャベール大佐も「エジプト人」である)、最後は敗北したうえに、上記のような悲運に見舞われながらも、自分の身よりも、セントヘレナに幽閉されたナポレオンの不遇を託つ老兵の「情念」だったようである。
バルザックが描いたのは「人間」ではなく、その「情念」だったということを、月報2号(第3巻付録)に掲載された中村真一郎「バルザックと現代」でぼくは学んだ。
この老兵の情念はぼくには理解不能だった。日本の戦後小説にこのような作品はあっただろうか。広田弘毅を描いた城山三郎「落日燃ゆ」あたりか・・・。
なお、最後にもう一つどんでん返しかと思われるエピソードが語られるのだが、それは書かないでおこう。
「結婚の生理学」よりも「あら皮」よりも、ぼくには面白い小説だった。あえて擬えるなら、山田風太郎の明治伝奇小説(「警視庁草紙」「幻燈辻馬車」など)に近いだろうか。
2020年7月25日 記