毎度のGoogleのロゴがこんなことに!
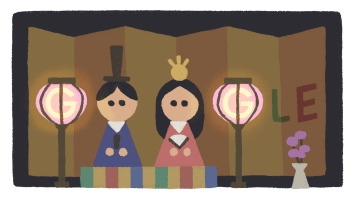
2021年 ひな祭り
毎年書いてるけど毎度の Wikipediaから引用
Wikipediaから引用
(Wikipediaは特性上不確かな情報も含みます)
雛祭り(ひなまつり)は、日本において、女子の健やかな成長を祈る節句の年中行事。
ひな人形(「男雛」と「女雛」を中心とする人形)に桜や橘、桃の花など木々の飾り、
江戸時代までは、和暦(太陰太陽暦)の3月の節句(上巳、桃の節句)である
明治の改暦以後はグレゴリオ暦(新暦)の3月3日に行なうことが一般的になった。
一部の地域では、引き続きに旧暦3月3日に祝うか、
「雛祭り」はいつ頃から始まったのか歴史的には判然とせず、その起源説は複数ある。
平安時代の京都で既に平安貴族の子女の雅びな「遊びごと」として行われていたとする記録がある。
その当時においても、
やはり小さな御所風の御殿「屋形」をしつらえ飾ったものと考えられている。
初めは儀式ではなく遊びであり、
雛祭りが「ひなあそび」とも呼ばれるのはそのためである。
江戸時代になり女子の「人形遊び」と節物の「節句の儀式」が結びつき、
全国に広まり、雛人形が飾られるようになった。
3月の節句の祓に雛祭りを行うようになったのは、
ひな人形は、形代(かたしろ)と呼ばれる人形の一種で、
娘の身代わりとして、娘に襲い掛かろうとする病などの災厄、
穢れを、ひな人形にうつして避けるという行事がひな祭りの元になっている。
紙や土などで作られた原始的で簡単な人形で、
1年の災いを受け止めた後に川や海に流された。
これを「ひな流し」という。
人形についての詳細や、種類などについてはWikipediaを見ていただくとして、
あとは休日でない理由を引用しておく
江戸時代、雛祭りは「五節句」のひとつとして「祝日として存在した」とされる。
しかし、1873年の新暦採用が「五節句(=雛祭り等を含む)」の祝日廃止となって、
さらに「国民の祝日」より「皇室の祝日」色が濃くなった。
このため、戦後になって新たに祝日を作ろうとする動きが見られるようになる。
祝日制定にあたり3月3日の案や、新年度の4月1日の案も出ていたが、
最終的には5月5日の端午の節句を祝日(こどもの日)とする案が採用された。
とのこと😢
検索画面のロゴはこんな感じ


よいひな祭りを🎎















