企業と大学との共同研究についてのコンサルティング、セミナー講師、論文執筆をしていますが、共同研究の成果の活用で常に問題となるのが、いわゆる不実施補償です。
不実施補償とは、企業と大学との共有特許がある場合に、大学は実施機関でないので、共同研究の成果を実施して収益をあげることはできません。
そこで、大学が企業に対して要求するのが不実施補償という名目のライセンス料です。
企業が独占的に実施する場合は、独占的利益の額に応じて金銭を支払うことは問題ないのですが、問題となるのは非独占に実施に対しても不実施補償を要求されることです。
この頭の痛い問題について朗報がありました。
それは、「産業技術総合研究所は30日、民間企業との共同研究で生まれた共有の知的財産権の取り扱いを見直すと発表した。これまで企業が非独占的に使って利益をあげた場合、利益の一部を産総研に払わなければならなかったが、11月からこの制度を廃止する。産総研は企業との共同研究が加速すると期待している。」という記事です。
産総研も変わってきたな〜。
記事によると、「産総研は企業と共同研究契約や受託研究契約を結ぶ際、共有知財の取り扱いを決めている。従来は研究の成果である知財を共同研究の相手先に独占的に使ってもらう場合も非独占的に使ってもらう場合も、知財を使わない産総研に「不実施補償料」として支払っていた。
今回、知財を独占的に相手先企業が使用する場合は従来通り不実施補償料を産総研がもらうが、非独占的に使う場合は不実施補償料をもらわないことにした。」ということですから、私が主張している「独占の対価補償」という考え方と同じです。
産総研の新提案は嬉しいですね。
私の論文の効果かな?(そんなことはないでしょうが)。
これで大学の考え方も変わってくれると良いのですが。
ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。
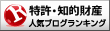 特許・知的財産 ブログランキングへ
特許・知的財産 ブログランキングへ
 弁理士 ブログランキングへ
弁理士 ブログランキングへ
不実施補償とは、企業と大学との共有特許がある場合に、大学は実施機関でないので、共同研究の成果を実施して収益をあげることはできません。
そこで、大学が企業に対して要求するのが不実施補償という名目のライセンス料です。
企業が独占的に実施する場合は、独占的利益の額に応じて金銭を支払うことは問題ないのですが、問題となるのは非独占に実施に対しても不実施補償を要求されることです。
この頭の痛い問題について朗報がありました。
それは、「産業技術総合研究所は30日、民間企業との共同研究で生まれた共有の知的財産権の取り扱いを見直すと発表した。これまで企業が非独占的に使って利益をあげた場合、利益の一部を産総研に払わなければならなかったが、11月からこの制度を廃止する。産総研は企業との共同研究が加速すると期待している。」という記事です。
産総研も変わってきたな〜。
記事によると、「産総研は企業と共同研究契約や受託研究契約を結ぶ際、共有知財の取り扱いを決めている。従来は研究の成果である知財を共同研究の相手先に独占的に使ってもらう場合も非独占的に使ってもらう場合も、知財を使わない産総研に「不実施補償料」として支払っていた。
今回、知財を独占的に相手先企業が使用する場合は従来通り不実施補償料を産総研がもらうが、非独占的に使う場合は不実施補償料をもらわないことにした。」ということですから、私が主張している「独占の対価補償」という考え方と同じです。
産総研の新提案は嬉しいですね。
私の論文の効果かな?(そんなことはないでしょうが)。
これで大学の考え方も変わってくれると良いのですが。
ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。














