京の冬の旅で公開されている「寺町 阿弥陀寺」にお詣りしたミモロ。そこで聞いた名物の鎌餅を求め、一目散に。
 阿弥陀寺の正面から伸びる道を西へ。ちょっと行ったところに、古い佇まいのお店が見えてきます。
阿弥陀寺の正面から伸びる道を西へ。ちょっと行ったところに、古い佇まいのお店が見えてきます。「あ、ここだー」




店の前に飾られたお菓子の数々。「どれにしようかなぁー」と、店に入る前から悩むミモロです。
「大黒屋鎌餅本舗」は、明治30年に創業された店。古い情緒ある建物が、阿弥陀寺からの道沿いにあります。
木の戸をあけて中へ。
 「いらっしゃいませー」
「いらっしゃいませー」 三代目店主の山田充哉さんが、笑顔で迎えてくださいました。
三代目店主の山田充哉さんが、笑顔で迎えてくださいました。
「あのー鎌餅って、まだありますか?」と、恐る恐る尋ねます。というのは、先ほど訪れた「阿弥陀寺」には、ツアー客のみなさんがいらして、集団で訪れたら、きっと売り切れになっちゃうーと心配していたのです。
信長公のお墓にお詣りしても、鎌餅が気になってしかたなかったミモロです。
「はい、まだありますよー」と。「よかった~売り切れかと心配しちゃったー」やっとミモロの顔にも笑みが。
 これが名物の鎌餅。薄い木に包まれた、細長い柔らかいそうなお餅です。「へえーこれが鎌餅なんだー」と、ミモロはじっと見つめます。
これが名物の鎌餅。薄い木に包まれた、細長い柔らかいそうなお餅です。「へえーこれが鎌餅なんだー」と、ミモロはじっと見つめます。「鎌餅は、江戸時代から鞍馬口の近くの茶店で、作られていたもので、鎌の形が豊作を意味しているんですよ。、豊かさを刈り取るとか、、また、旅の厄を払うという意味から作られたもの。鞍馬口にあった茶店がなくなり、明治になって、その味を復活させたのが、創業者である先々代です」と、山田さん。
お腹が空いていたミモロ、思わず、「あのーここで食べてもいいですか~」と我慢しきれずに…。「はい、どうぞー」ミモロに鎌餅が手渡されました。
 「うー素朴な感じが、いい感じ…。いただきまーすと、いっきにペロリ「柔らかーいお餅…中の餡もほんのり甘くて美味しい…こういうシンプルな和菓子が飽きないんだよねー」
「うー素朴な感じが、いい感じ…。いただきまーすと、いっきにペロリ「柔らかーいお餅…中の餡もほんのり甘くて美味しい…こういうシンプルな和菓子が飽きないんだよねー」店先で、ひとつ鎌餅を食べたミモロは、その横に並ぶ品にも注目。
 「これ、なんですか?」鎌餅と違って、硬い感じのお菓子です。「これも食べたいな~」
「これ、なんですか?」鎌餅と違って、硬い感じのお菓子です。「これも食べたいな~」「懐中しるこですから、ここでは食べられませんよ」
 めでたい烏帽子の形の懐中しるこです。「表面の焼き色は、炭火で焼いたもの…。お椀に入れてお湯を注いで食べてくださいねー」と。「おしるこなんだー。じゃ、おうちで食べるので、ひとつください…」。ミモロは、ひとつ袋に入れてもらいました。
めでたい烏帽子の形の懐中しるこです。「表面の焼き色は、炭火で焼いたもの…。お椀に入れてお湯を注いで食べてくださいねー」と。「おしるこなんだー。じゃ、おうちで食べるので、ひとつください…」。ミモロは、ひとつ袋に入れてもらいました。「あ、羊羹もあるー」
 でっち羊羹という薄い形の羊羹です。でっち羊羹というのは、竹皮に包まれた蒸羊羹で、竹皮の香りがほんのり羊羹に移った味が美味しさをさらに…。京都のお店に奉公に来ていたでっちさんが、里帰りのおみやげにしたという値段控えめの羊羹です。薄いので、持ち運びに便利で、竹皮による殺菌作用もあり日持ちしたそう。練羊羹に比べ、甘さも控えめ、食べやすい羊羹です。
でっち羊羹という薄い形の羊羹です。でっち羊羹というのは、竹皮に包まれた蒸羊羹で、竹皮の香りがほんのり羊羹に移った味が美味しさをさらに…。京都のお店に奉公に来ていたでっちさんが、里帰りのおみやげにしたという値段控えめの羊羹です。薄いので、持ち運びに便利で、竹皮による殺菌作用もあり日持ちしたそう。練羊羹に比べ、甘さも控えめ、食べやすい羊羹です。こちらのお店では、鎌餅、懐中しるこ、でっち羊羹、そして最中を買うことができます。
京の冬の旅で、「阿弥陀寺」を訪れた後に、ぜひお土産にしたい京都の名物のひとつです。「阿弥陀寺」からすぐです。
*「大黒矢鎌餅本舗」 京都市上京区今出川上ル4丁目西入ル阿弥陀寺町25 075-231-1495 8:30~20:00 第1・3水曜休み 鎌餅210円、懐中しるこ315円、 でっち羊羹840円、最中170円
 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへブログを見たら、金魚をクリックしてねー。よろしく~ミモロより
特許庁 商標登録第5629481号 copyright2010Sea Hawk Japan co.,ltd. All rights reserved.













 この寺は、浄土宗鎮西派で、御本尊は、阿弥陀如来さま。織田家の菩提寺と言われます。
この寺は、浄土宗鎮西派で、御本尊は、阿弥陀如来さま。織田家の菩提寺と言われます。 さて、阿弥陀寺のある寺町通は、南は五条通、北は紫明通まで続く長い道。四条通りから御池通までアーケードになっています。その道の東側に、天正18年(1590)に、秀吉により多くの寺院が集められ、寺町とよばれるようになったそう。
さて、阿弥陀寺のある寺町通は、南は五条通、北は紫明通まで続く長い道。四条通りから御池通までアーケードになっています。その道の東側に、天正18年(1590)に、秀吉により多くの寺院が集められ、寺町とよばれるようになったそう。 今回、公開された本堂では、信長公の木像や位牌、鞍覆い、弓掛など、信長ゆかりの品々を見ることができます。
今回、公開された本堂では、信長公の木像や位牌、鞍覆い、弓掛など、信長ゆかりの品々を見ることができます。 本堂内は、残念ながら撮影禁止。案内役の方が、歴史や当時の様子などを、わかりやすく説明してくれます。
本堂内は、残念ながら撮影禁止。案内役の方が、歴史や当時の様子などを、わかりやすく説明してくれます。 「本堂では、こんな信長公木像がありました~。思ったより小さい感じだったけど…。それから森蘭丸のお位牌もあったよ」とミモロ。
「本堂では、こんな信長公木像がありました~。思ったより小さい感じだったけど…。それから森蘭丸のお位牌もあったよ」とミモロ。 「境内の奥ですよ、案内板が出てますから、すぐわかります」と。「あのーそれから、名物のお菓子が近くで売ってるって聞いたんですけど…」「はい、鎌餅ですね。お寺を出て、すぐのところにありますよ。おじさん一人でやってるから、売り切れになることもあるんです」と。
「境内の奥ですよ、案内板が出てますから、すぐわかります」と。「あのーそれから、名物のお菓子が近くで売ってるって聞いたんですけど…」「はい、鎌餅ですね。お寺を出て、すぐのところにありますよ。おじさん一人でやってるから、売り切れになることもあるんです」と。
 ミモロの大きさから、わかると思います。
ミモロの大きさから、わかると思います。 右が信長公、左が息子の信忠公のもの。
右が信長公、左が息子の信忠公のもの。 この日は、「手習講 千鳥会」の稽古始です。場所は、地下鉄東西線の終点「太秦天神川」から、嵐電嵐山本線に乗り換え、1つ目の「山ノ内」という駅のすぐ前。
この日は、「手習講 千鳥会」の稽古始です。場所は、地下鉄東西線の終点「太秦天神川」から、嵐電嵐山本線に乗り換え、1つ目の「山ノ内」という駅のすぐ前。 お教室は2階です。
お教室は2階です。
 柳本先生は、1970年、京都の西、山ノ内の大きな農家生まれ。同志社大学を卒業。幼い頃から書に興味を抱き腕を磨き、京展、日本書芸院展などで入賞。「大蔵流狂言」に魅了され、木村正雄、綱谷正美に師事、さらに十三世茂山千五郎に師事した元大蔵流狂言師。現在、書と狂言という日本の伝統文化を広く海外に普及させるため、ハーバード大学などでワークショップや講演をおこなっていらっしゃいます。もちろん、今も、実家の農業にも従事。
柳本先生は、1970年、京都の西、山ノ内の大きな農家生まれ。同志社大学を卒業。幼い頃から書に興味を抱き腕を磨き、京展、日本書芸院展などで入賞。「大蔵流狂言」に魅了され、木村正雄、綱谷正美に師事、さらに十三世茂山千五郎に師事した元大蔵流狂言師。現在、書と狂言という日本の伝統文化を広く海外に普及させるため、ハーバード大学などでワークショップや講演をおこなっていらっしゃいます。もちろん、今も、実家の農業にも従事。
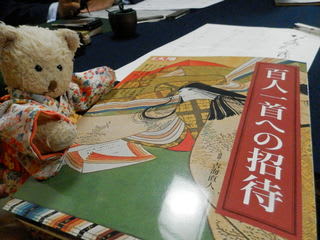

 「まず墨をすらなくちゃ…筆もつの久しぶり~」と、相変わらずのミモロ。他の熱心な生徒さんのお話に耳を傾けながら、墨をすります。
「まず墨をすらなくちゃ…筆もつの久しぶり~」と、相変わらずのミモロ。他の熱心な生徒さんのお話に耳を傾けながら、墨をすります。
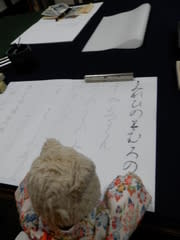 「上から書くのうまくなったよー」と、これは筆使いを学ぶ初歩のやり方。でも、これもなかなかむずかしい…。「たまに筆を持つっていいねぇー」とミモロ。全く申し訳ありません。
「上から書くのうまくなったよー」と、これは筆使いを学ぶ初歩のやり方。でも、これもなかなかむずかしい…。「たまに筆を持つっていいねぇー」とミモロ。全く申し訳ありません。
 「なるほどー」
「なるほどー」 「ここは、筆を持ち上げるように…」「そうだったーすっかり忘れてたー」とミモロ。「でも、今日は、なかなかうまく書けたみたい…」と反省の色はありません。ともかくミモロは、このお教室の雰囲気が大好き。他の生徒さんたちも、そんなミモロを温かく迎えてくださっています。ありがたい…
「ここは、筆を持ち上げるように…」「そうだったーすっかり忘れてたー」とミモロ。「でも、今日は、なかなかうまく書けたみたい…」と反省の色はありません。ともかくミモロは、このお教室の雰囲気が大好き。他の生徒さんたちも、そんなミモロを温かく迎えてくださっています。ありがたい…















 正絹の布で作られた小さなテディベア。バッグなどのアクセサリーに人気。ひとつひとつ違った表情なので、じっくり選ぶ楽しさも。
正絹の布で作られた小さなテディベア。バッグなどのアクセサリーに人気。ひとつひとつ違った表情なので、じっくり選ぶ楽しさも。
 その前に切り売りの表示が
その前に切り売りの表示が
 見るからに和服がピッタリの京美人。
見るからに和服がピッタリの京美人。 高級な絞りの生地も切り売り可能。「総絞りは、振袖もってるしー。もっと気軽に普段着られるお着物が欲しいなぁー」と。
高級な絞りの生地も切り売り可能。「総絞りは、振袖もってるしー。もっと気軽に普段着られるお着物が欲しいなぁー」と。



 「朱塗りの建物じゃないから、地味かもねー」と、正直、あまり期待しないで行ったミモロ。ところが、境内に一歩入ると、ミモロは、茫然…
「朱塗りの建物じゃないから、地味かもねー」と、正直、あまり期待しないで行ったミモロ。ところが、境内に一歩入ると、ミモロは、茫然…
 「わー白い木がいっぱいー」三門までの道を歩きながら、見上げると、楓の枝に雪がつき、木全体が白い花をつけているよう。
「わー白い木がいっぱいー」三門までの道を歩きながら、見上げると、楓の枝に雪がつき、木全体が白い花をつけているよう。 「うわーすごくキレイ・・・まるで白い桜が咲いてるみたい…」。南禅寺は、紅葉で有名。どちらかというと桜は、それほど多くありません。でも、この日は、まるで満開の桜を見た心地に。
「うわーすごくキレイ・・・まるで白い桜が咲いてるみたい…」。南禅寺は、紅葉で有名。どちらかというと桜は、それほど多くありません。でも、この日は、まるで満開の桜を見た心地に。 ただただ感激しています。
ただただ感激しています。 屋根の雪がなければ、桜にみえませんか?「南禅寺の雪桜…って、いいんじゃない?」と勝手に命名。
屋根の雪がなければ、桜にみえませんか?「南禅寺の雪桜…って、いいんじゃない?」と勝手に命名。

 繊細な花のようにはなりません。「と、いうことは、楓の木の雪景色って、すごくキレイってことかも…」とミモロ。
繊細な花のようにはなりません。「と、いうことは、楓の木の雪景色って、すごくキレイってことかも…」とミモロ。
 境内の中を歩きながら、静寂と純白の世界の素晴らしさに、寒さも忘れてしまいます。
境内の中を歩きながら、静寂と純白の世界の素晴らしさに、寒さも忘れてしまいます。 山の木々も薄っすらと雪をかぶり、山の色を消しています。しばし我を忘れたように、雪景色を前に立ち尽くすミモロです。
山の木々も薄っすらと雪をかぶり、山の色を消しています。しばし我を忘れたように、雪景色を前に立ち尽くすミモロです。
 緑の苔の上にも
緑の苔の上にも ドカ雪でなく、薄っすらと…というところに風情が漂います。「こんな素敵な景色が見られるなんて、しあわせ~」。京都に生まれ育った人にとっては、見慣れた雪景色も、東京生まれのミモロには、感激もいっそう。
ドカ雪でなく、薄っすらと…というところに風情が漂います。「こんな素敵な景色が見られるなんて、しあわせ~」。京都に生まれ育った人にとっては、見慣れた雪景色も、東京生まれのミモロには、感激もいっそう。









