
石川氏の「笹竜胆(ささりんどう)」
1590~1613年
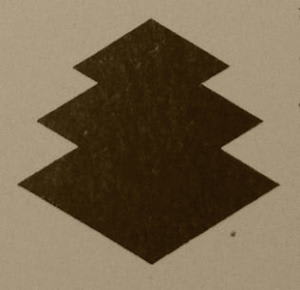
小笠原氏の「三階菱(さんがいびし)」
1613~1617年

戸田氏の「はなれ六星(はなれむつぼし)」
1617~1633年

松平氏の「丸に三つ葉葵(まるにみつばあおい)」
1633~1638年

堀田氏の「黒餅竪木爪(くろもちたてもっこう)」
1642~1642年

水野氏の「丸に花沢潟(まるにはなおもだか)」
1642~1725年

戸田氏の「はなれ六星(はなれむつぼし)」
1726~1868年
☞ 松本城いろいろ一覧に戻る

1714年頃に描かれた「信州松本城之図」によるとここには二重二階の櫓がありました。
1960年には「黒門」、1999年には「太鼓門」が復元されていますが、この「二の丸東北隅櫓」も復元の対象になっているようです。
☞ 松本城いろいろ一覧に戻る

天守の壁は各階とも外壁は塗りごめの「大壁(おおかべ)」、内壁は柱の見える「真壁(しんかべ)」となっています。
外壁の白い部分は白漆喰(しろしっくい)と呼ばれるもので、石灰に麻すさ(刻んだ麻)やふのり等を混ぜあわせたものです。
下地には、径1.5~3Cmのサクラ、カエデ、リョウブなどの細い丸太材が用いられているそうです。
壁の厚さは1・2階で28.8~29.4Cmあり、上の階ほど薄くなっていますが、火縄銃の玉は通さないようです。
写真の壁は昭和の大修理の時に一部切り取った壁で、天守一階に展示されています。
☞ 松本城いろいろ一覧に戻る


松本城は大天守・乾小天守・渡櫓・辰巳附櫓・月見櫓の5棟からなる連結複合式天守です。
文献によると築造は二期に渡り、一期目は文禄二・三年(1593・4)に天守と乾小天守及び二つの天守を連結する渡櫓、二期目は寛永十一年(1634)頃で天守に付設される形で辰巳付櫓と月見櫓が築造されています。
大天守・乾小天守・渡櫓が連結式、天守・辰巳付櫓・月見櫓が複合式となってます。
連結複合式天守は日本の城では松本城だけに見られる特色ある構造のようです。
☞ 松本城いろいろ一覧に戻る

鯱(しゃち)は想像上の海魚で、水を噴いて雨を呼ぶと言われ、火災除けの願いをこめて天主などの大棟にあげられ棟飾りとして使われています。
中国の漢時代から使われ始め、日本の城では織田信長が築城した安土城で用いられたのが最初と言われています。
松本城では大天主と乾小天主に雌雄一対の鯱が飾られています。
「松本城の鯱には耳が無い」といわれているようで、耳が小さいです。
これは初期の安土桃山時代の鯱に共通している点でのようで、松本城の鯱が古い時代に造られた事を物語っているようです。
普通鯱は南北に並んでいる場合は南が雄で北が雌、東西に並んでいる場合は東が雄で西が雌という事です。
松本城内に展示されている古い鯱は雄が127Cm、雌が124Cmです。

右が南、左が北です。

北の雌。

南の雄。

大棟の鬼瓦は戸田家の「はなれ六ツ星」、巴瓦は「左巴」になっています。
☞ 松本城いろいろ一覧に戻る




























