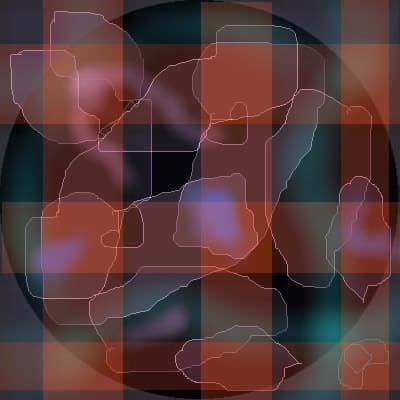
満員の列車の中で、私たちは通路に並んで立っていて、わずかに肩が触れ合うことがあった。すると里依子の温かさがそっと私に届いた。そのたびに彼女は静かに身を離した。私もまた、それを追おうとはしなかった。身を固くして吊皮を持った手を握りしめるばかりで、ただそんな里依子を淋しくあるいはいじらしく感じるのだ。そして今度は私が深いため息をついて本から目を離すのだった。
車窓からは相変わらずの雪原が私をあざ笑うように流れて来て私の眼を彷徨わせる。
やがて里依子も本を読むのをやめ、その窓を眺めている。私はそれを横合いに感じながら、愕然として彼女を見た。
里依子の顔はまるで泣きはらした後のような悲しい顔をしているのだ。目が赤く涙に濡れているように思われた。
いったい何がそんなに悲しいのだろうか。何が彼女をそんな風にさせてしまうのか。私はそんな彼女にかける言葉さえなかった。私は何も知らない木偶の坊でどうすることも出来ず、気付かないふりをして本に目を戻した。胸が張り裂けるようにガリガリと何かが渦巻いていた。私はただ抗するように身を固くして立ち尽くすしかなかった。
 HPのしてんてん
HPのしてんてん 


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます