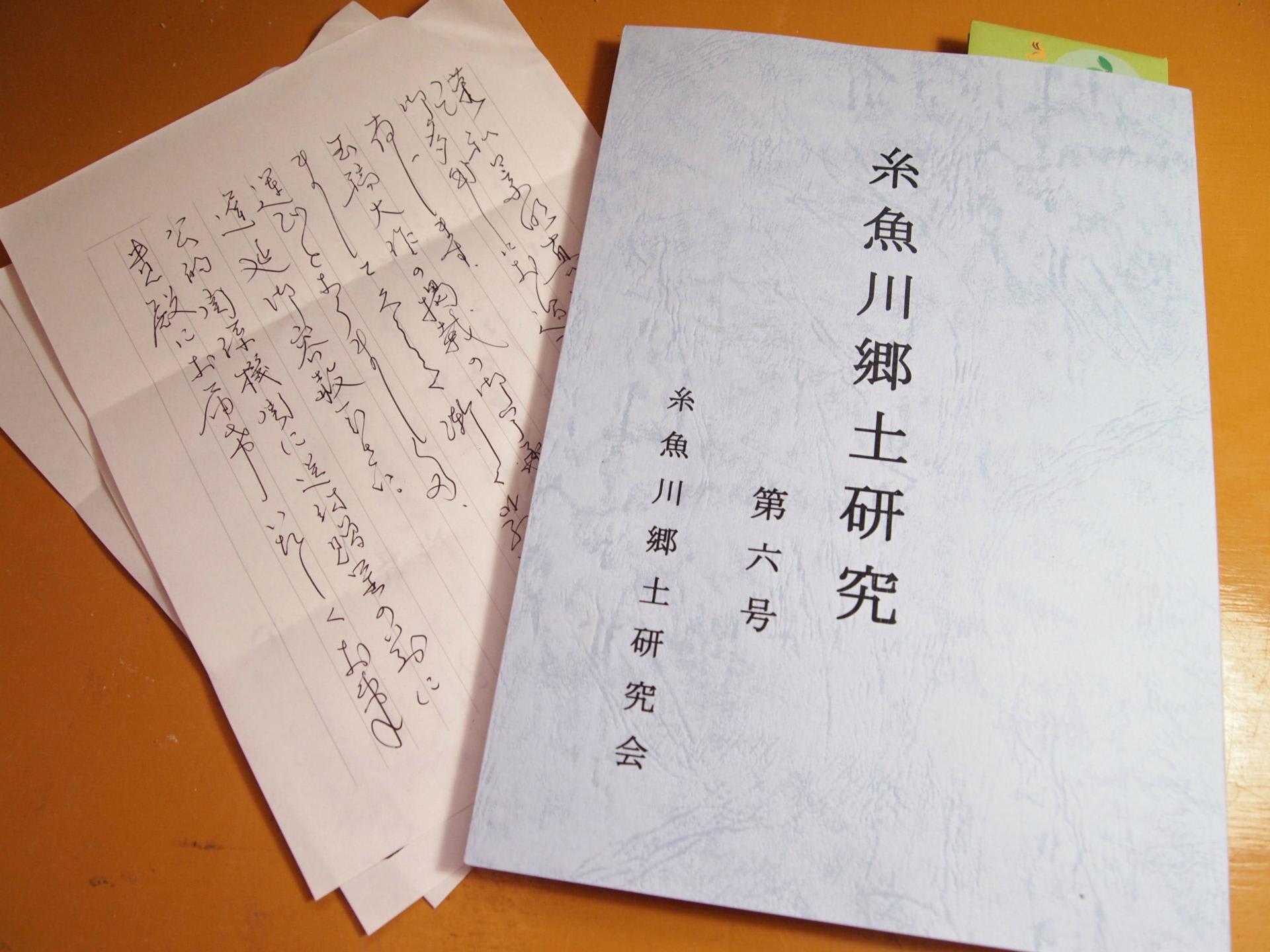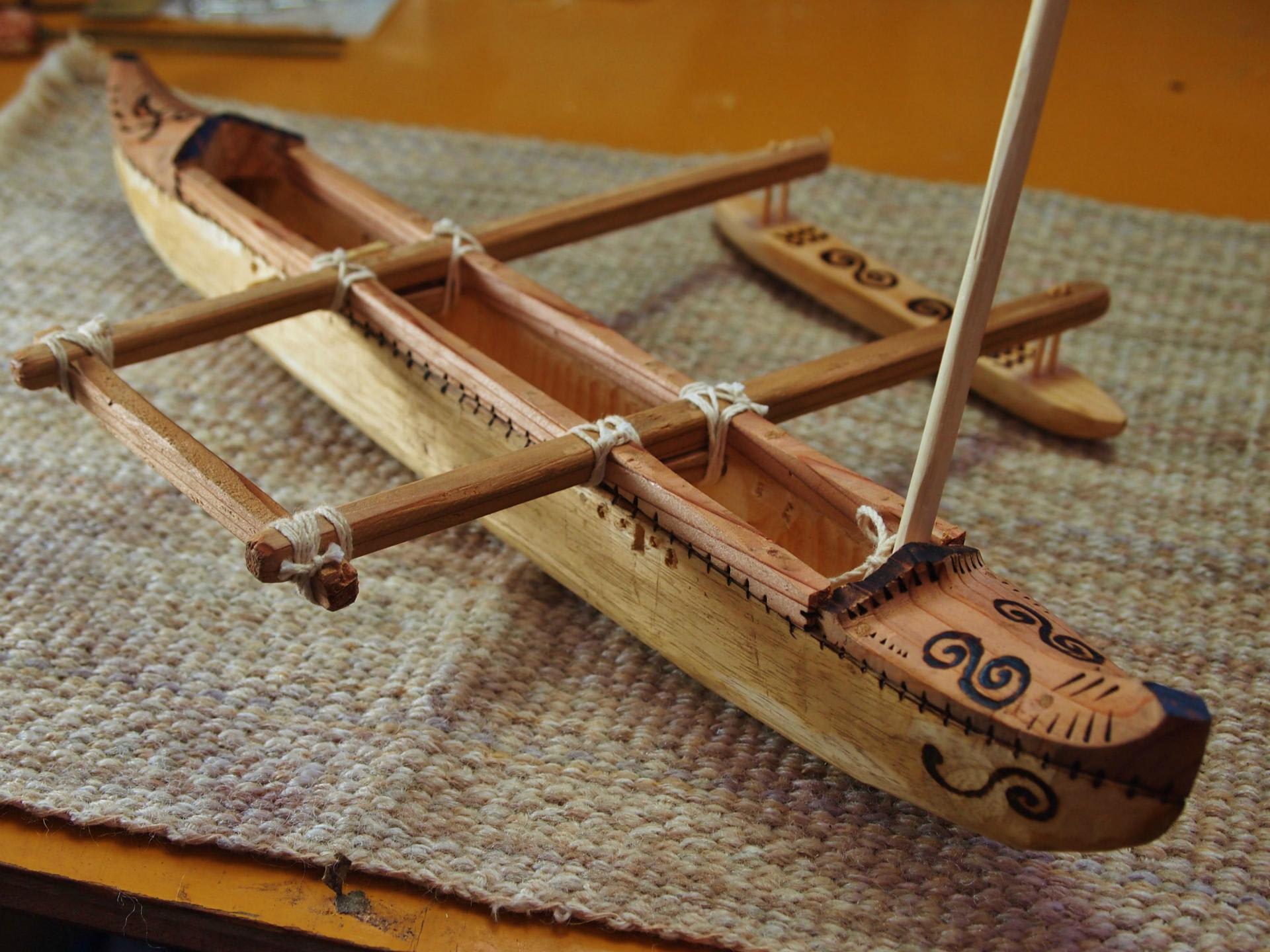「くびき野天地ひとカレッジ」の魔除け講座は、友人達も駆けつけてくれて満員御礼の内に終了・・・やれうでしや。
帰宅したら古い友達から手紙が届いていた。
草の根運動の草の根的存在として世界に名を知られる山田征さんからで、ご主人が国立能楽堂で主宰する観能会の招待券と私信である。
観能会にはここ十五年ほど毎年ご招待を受けているのだけど、Uターン帰郷して七年目になっても律儀に贈って頂いて恐縮・・どなたか行ける人に無料でお譲りします。
連絡はこのブログにコメント下さいな。
演目は私はまだ観ていないけども何時か観たいと思っていた「隅田川」。

在る時、日本文化に興味を持ったジョン・レノンが懇意にしていた銀座の骨董屋の主人に人形浄瑠璃に連れていってもらった。
子供をさらわれた母親が、子供を探して放浪の旅に出た挙句、隅田川の川岸に埋葬された我が子の墓を見つけ狂い踊るという筋書きの演目・・・であったらしいが、恐らくその時の演目は「隅田川」ではなかったか?と推測している。
陰気な演目だったので、骨董屋の主人が日本語も解らないのにジョンさんはさぞ退屈だろう、外に出ましょうか?と隣りの席のジョンに話しかけたら、ジョンは涙を流して感動していたそう。
ジョンさん、日本語も解らないのにこの演目が理解できるのですか?と聞いたら、ジョンは筋書きを正確に理解しており「こんな素晴らしい芸術に退屈するなんてとんでもない!」と答えたそうだ。
ジョンが感動した隅田川、見逃すな!!
即日、東京在住の幼馴染の女社長、直子嬢に譲る事になりました・・・。
・