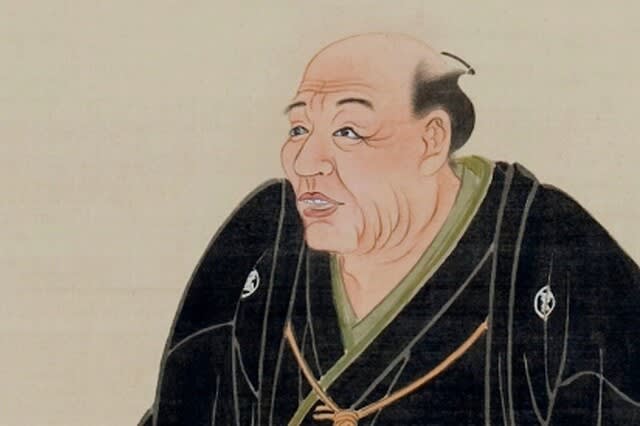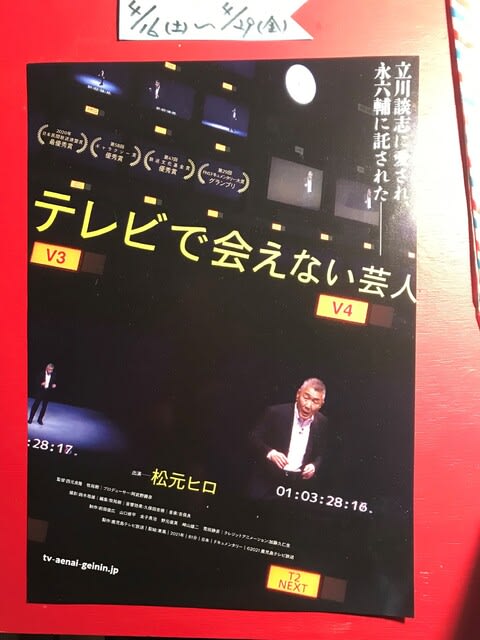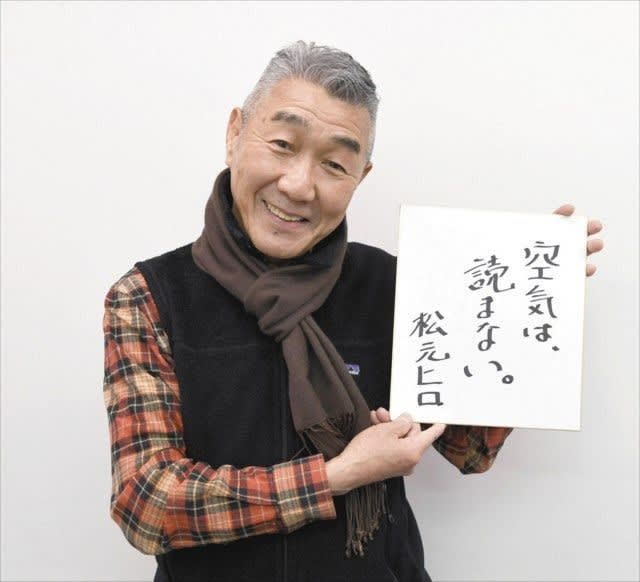ボクシングの階級で多くの天才を輩出したのがバンタム級(53キロ前後)であることから、「黄金のバンタム」とも呼ばれる。
ちなみに「あしたのジョー」の矢吹丈もバンタム級。

しかし本来の「黄金のバンタム」は、不世出のブラジルのボクサー、人格者でもあったエデル・ジョフレに冠された異名だった。
昨夜の井上VSドネア戦は、井上の圧倒的勝利に終わり、井上が正真正銘の「黄金のバンタム」の継承者であることが証明された。
強いだけでは「黄金のバンタム」に相応しくない。
アグレッシブでクレバーな試合運び、謙虚で紳士的な言動、対戦相手への敬意が揃ってこそ、「黄金のバンタム」。
おそらく同じ階級で井上に挑戦する勇敢なボクサーはいないだろうから、階級をあげていくことになるだろう。
井上の身長は165㎝だから、フェザー級くらいまでなら、粉飾なしのリアルな4階級制覇、統一王者も夢ではない。
強いボクサーがノックアウトされるのは淋しい。あのドネアがリングを降りて泣いていた。
「黄金のバンタム」が、ドネアから井上にバトンタッチされた歴史的な夜。
ジョフレに唯一勝利したボクサーは、ファイティング原田だけで、二人とも階級制覇をなしとげて、殿堂入りしている。
10代の井上がドネアに憧れたように、次は井上が若いボクサーに追われる立場。そしていつかはリングに這いつくばる日がくるかも知れない。
井上のみならず、ドネアへも拍手と謝辞を贈りたい。