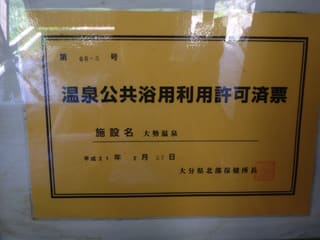玖珠町の中心部(豊後森)と耶馬渓を結ぶ大分県道43号線を走行している途中、路傍に温泉と書かれた看板を見かけたので、ちょっと立ち寄ってみることにしました。その温泉の名前は「鶴川温泉」。その名のように、鶴が飛来してきても不思議ではないほど大変長閑な田園風景が広がっており、夏にはホタルが飛び交うんだとか。


瓦屋根の渋い建物の前には「営業中」の立て看板が客を出迎えていました。こちらの温泉は(平日は)夕方4時からの営業。昼間に行っても開いていません。玄関入ってすぐのところに窓口を開けている番台で、朗らかな笑顔のおばちゃんに湯銭を支払い、下足場の前から伸びる階段で階下へ下っていきます。

階段を下りきった先の突き当たりには一台の洗面台と家族風呂のドアが並んでおり、その左右両側に紺と紅の暖簾が掛けられていました。なお家族風呂は一人500円というお手頃価格なんだそうですが、今回は利用しておりません。天井が低く薄暗い脱衣室は、実用本位で至って簡素。長居するような部屋ではないので、ササッと着替えてお風呂へ。


浴室も奇を衒わずシンプル。まるで地元民向け共同浴場を思わせる渋い佇まいです。男湯の場合は、入って右手に浴槽が据えられ、左手の壁沿いに洗い場が配置されていました。


洗い場にシャワーはなく、昔ながらの蛇口が7つ並んでだけというのもまた渋い。でもこの蛇口、一見するとどれも同じに見えますが、交互で段違いに取り付けられており、高い方の蛇口(計4つ)のハンドルを捻ると、温泉のお湯が吐出されました。



浴槽の寸法は(目測で)1.8m×2.4mの長方形。湯船にはジャスミン茶のような淡い褐色を呈した透明の温泉が湛えられています。41〜2℃というちょっとぬるめの湯加減ですので、のんびりゆっくり長湯を楽しむことができるでしょう。お湯は槽内の穴から投入されており、その勢いで白い筋が見えました。そして湯船に数分浸かっていると、全身に気泡がビッシリと付着し、湯口の近くでは白い泡の塊も見られました。おそらく湯使いは純然たる放流式かと思われます。
お湯からは木材を焦がしたようなモール臭が放たれ、清涼感を伴うほろ苦みと少々の金気が感じられます。玖珠盆地周辺の温泉でよく見られるモール泉的案特徴が表れている温泉ですが、周辺の他湯に比べると、その特徴はやや大人しめであるように思われます。でも湯中で得られるツルツルスベスベの大変滑らかな浴感が気持ちよく、しかもたっぷりのアワアワに包まれますので、モール泉且つぬる湯が好きな私にとっては最高の湯浴みでした。


300円の公衆浴場でありながら露天風呂に入れるというのが、こちらの施設の素晴らしいところ。しかも、内湯は質素でしたが、露天風呂は立派な日本庭園のような趣きで、私が訪問した時にはツツジが花を咲かせており、既に花を散らして青葉を茂らせていた桜の樹の下では、石仏が湯浴み客を穏やかな面持ちで見守っていました。周囲の里山も借景になっており、まるで昔話の世界に紛れ込んだかのような、実に純朴な光景です。
お風呂は岩風呂で、浴槽内はモルタル塗り。ぱっと見回したところ、露天専用の湯口は無いらしく、内湯から流れてくるお湯を受けているほか、仕切り塀の向こう側にある女湯露天からもお湯を受けており、つまり全ての浴槽の最下流が男湯の露天となっているようでした。内湯ですら41〜2℃ですから、露天では40℃以下のぬる湯であり、しかも泡つきも見られませんでしたが、その湯加減ゆえに寧ろ体への負担は軽く、長湯するにはもってこい。時の流れ方が都会と異なるこの長閑な温泉で、おかげさまで身も心もすっかり癒されました。
分析書見当たらず
単純温泉
大分県玖珠郡玖珠町太田3935-5 地図
0973-72-4426
平日16:00~21:00 土日祝11:00~21:00 火曜定休(祝日は営業)
300円
ロッカーあり(有料100円)・ドライヤーあり、石鹸などは番台で販売(備え付けなし)
私の好み:★★+0.5