一関市街地のマンリョウ(万両)
2008年4月15日


2008年4月15日(火)、一関市街地の民家の庭で、鉢植えの
「マンリョウ(万両)」が赤く熟した実を沢山つけていました。





奈良県飛鳥寺のマンリョウ(万両) 2006年5月11日

2006年5月11日(木)、奈良県明日香村にある飛鳥寺(現在は安居院
[あんごいん])を訪ねた。「蘇我入鹿首塚」がある方から入ったのだ
が、真っ先に目に付いたのが、「マンリョウ(万両)」の赤い実だった。
また、ほとんどのお寺が仏像の撮影を禁じているのに、ここでは撮影し
ても良いと言ってくださいました。






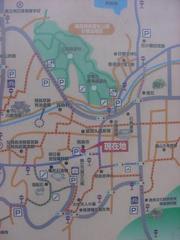

飛鳥寺について
飛鳥寺は、第32代崇峻天皇元年(588)曽我馬子が発願し、
第33代推古天皇4年(596)に創建された日本最初の大寺院であり、寺名
を法興寺、元興寺、飛鳥寺(現在は安居院)とも呼んだという。(仏教
の受入れをめぐって物部氏と争っていた曽我馬子が、戦いに勝った記念
に創建したとされる。大化の改新前に、中大兄皇子と中臣鎌足が出会っ
た場所でもある。)
近年(昭和31年)の発掘調査により、創建時の寺は塔を中心に東西と北
にそれぞれ金堂を配する日本最初の本格的寺院で、その外側に回廊をめ
ぐらし更に講堂を含む壮大な伽藍であったという。
本尊飛鳥大仏(釈迦如来坐像)は推古天皇17年(609)天皇が詔して鞍作
鳥(止利仏師)に造らせた日本最古の仏像である。旧伽藍は仁和3年(887)
と建久7年(1196)の火災によって焼失し、室町以降は荒廃したが、寛永9
年(1696)と文政9年(1826)に再建され今日に至っている。現在真言宗豊
山派に属し、新西国第9番、聖徳太子第11番の霊場でもあるという。
(製作年代が明らかなものでは日本最古の仏像とか)



マンリョウ(万両)ヤブコウジ科 ヤブコウジ(アルディシア)属
Ardisia crenata
暖地の林の中に生える常緑小低木。縁起のいい木とされており、庭な
どによく植えられているし、赤く熟した実が美しいので鉢植えにされ
て正月飾りによく利用される。
高さは20~100cm、ときには2mにもなるものもあるという。ヤブコウ
ジと異なり匍匐茎はない。上方で分枝し、厚手の葉を互生する。葉身
は長さ5~15cmの楕円状披針形~倒披針形で、縁には波状の鋸歯
があり、葉縁は波打つ。
7月頃、枝先や葉腋から散形または散房状の花序を出し、花びらがクル
リとそり返った直径8mmほどの白またはピンク小花を多数下向きに咲か
せる。
花が終わると球形の実を結ぶ。果実の大きさは様々だが、直径6~8mm
ほどの球形で、晩秋(11月ごろ)に赤く熟し、翌年の春まで残る。
「宝船cv.Takarabune」のように大型品種が愛培される。 「千鳥白実cv.
Chidorishiromi」のように果実が黄色のもの(キミノマンリョウ)
や白いもの(シロミノマンリョウ)もある。
また、斑入り葉など葉色の変化により、多くの品種が江戸期より栽培
されている。
[栽培]低温にはかなり強いが、関東地方以北では冬期保護が必要。
分布:本州(関東地方以西)、四国、九州、沖縄、朝鮮、中国、台湾、
インド北部。
ヤブコウジ(アルディシア)属 Ardisia
日本の暖地を含むアジア、オーストラリア、南北アメリカに約250種の
常緑低木、高木が自生している。
2008年4月15日


2008年4月15日(火)、一関市街地の民家の庭で、鉢植えの
「マンリョウ(万両)」が赤く熟した実を沢山つけていました。





奈良県飛鳥寺のマンリョウ(万両) 2006年5月11日

2006年5月11日(木)、奈良県明日香村にある飛鳥寺(現在は安居院
[あんごいん])を訪ねた。「蘇我入鹿首塚」がある方から入ったのだ
が、真っ先に目に付いたのが、「マンリョウ(万両)」の赤い実だった。
また、ほとんどのお寺が仏像の撮影を禁じているのに、ここでは撮影し
ても良いと言ってくださいました。






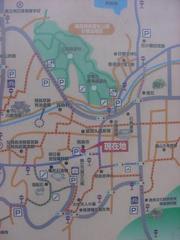

飛鳥寺について
飛鳥寺は、第32代崇峻天皇元年(588)曽我馬子が発願し、
第33代推古天皇4年(596)に創建された日本最初の大寺院であり、寺名
を法興寺、元興寺、飛鳥寺(現在は安居院)とも呼んだという。(仏教
の受入れをめぐって物部氏と争っていた曽我馬子が、戦いに勝った記念
に創建したとされる。大化の改新前に、中大兄皇子と中臣鎌足が出会っ
た場所でもある。)
近年(昭和31年)の発掘調査により、創建時の寺は塔を中心に東西と北
にそれぞれ金堂を配する日本最初の本格的寺院で、その外側に回廊をめ
ぐらし更に講堂を含む壮大な伽藍であったという。
本尊飛鳥大仏(釈迦如来坐像)は推古天皇17年(609)天皇が詔して鞍作
鳥(止利仏師)に造らせた日本最古の仏像である。旧伽藍は仁和3年(887)
と建久7年(1196)の火災によって焼失し、室町以降は荒廃したが、寛永9
年(1696)と文政9年(1826)に再建され今日に至っている。現在真言宗豊
山派に属し、新西国第9番、聖徳太子第11番の霊場でもあるという。
(製作年代が明らかなものでは日本最古の仏像とか)



マンリョウ(万両)ヤブコウジ科 ヤブコウジ(アルディシア)属
Ardisia crenata
暖地の林の中に生える常緑小低木。縁起のいい木とされており、庭な
どによく植えられているし、赤く熟した実が美しいので鉢植えにされ
て正月飾りによく利用される。
高さは20~100cm、ときには2mにもなるものもあるという。ヤブコウ
ジと異なり匍匐茎はない。上方で分枝し、厚手の葉を互生する。葉身
は長さ5~15cmの楕円状披針形~倒披針形で、縁には波状の鋸歯
があり、葉縁は波打つ。
7月頃、枝先や葉腋から散形または散房状の花序を出し、花びらがクル
リとそり返った直径8mmほどの白またはピンク小花を多数下向きに咲か
せる。
花が終わると球形の実を結ぶ。果実の大きさは様々だが、直径6~8mm
ほどの球形で、晩秋(11月ごろ)に赤く熟し、翌年の春まで残る。
「宝船cv.Takarabune」のように大型品種が愛培される。 「千鳥白実cv.
Chidorishiromi」のように果実が黄色のもの(キミノマンリョウ)
や白いもの(シロミノマンリョウ)もある。
また、斑入り葉など葉色の変化により、多くの品種が江戸期より栽培
されている。
[栽培]低温にはかなり強いが、関東地方以北では冬期保護が必要。
分布:本州(関東地方以西)、四国、九州、沖縄、朝鮮、中国、台湾、
インド北部。
ヤブコウジ(アルディシア)属 Ardisia
日本の暖地を含むアジア、オーストラリア、南北アメリカに約250種の
常緑低木、高木が自生している。



















