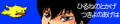今日は、真面目にいきます。
帰省している折、地方紙で、介護従事者に対するアンケート調査を行ったところ、「ケア・ハラスメント」なるものを受けたことがあると答えた人が8割(すみません、正確に覚えてません)程度もいるという記事が載っていました。その内容は、セクハラのようなことから、「規定外のことを頼まれる」など多岐にわたっているようでした。流し読みしてしまい、あとでゆっくり読もうと思って、そのままにしてしまったので、詳しい内容はわかりません。でも殆どのケア・ワーカーが「ケア・ハラスメント」を経験しているということと、その内容が、なんだか「えっ」と、心にひっかかったのでした。
そういえば、以前「セクハラ」という言葉が一般化し始めた頃、女性社員の8割以上が「セクハラ」を経験したことがあるという調査もあったっけな。いや、9割りだったかな?
今回の「ケアハラ」調査、健全な大人同士の職場間ということが前提でのセクハラ問題とはちょっと違うのでは。介護をする人、される人、ということでお互いのポジションがまず違います。
たくさんの企業がこぞって介護業界にも参入して、介護産業はいきなり賑わって、整備が遅れている感じがあります。
私は、この記事を読んだとき、「そりゃー、ケア・ワーカーの資質の問題では?」とまず思いましたが、いかがでしょうか。極端にいえば、マニュアルだけをインプットされた従事者が大量に排出されているのでは…、、、
以前、音楽を通して、福祉大の学生の人たちとお友達になりました。
彼らは、それぞれ考えるところや、志があって、この大学を選んだと言っていました。家族に障碍のある人がいて、日常の中で自然にいろいろ考えたり、子供の頃の経験したことや、将来の夢などと、今大学で学んでいることが自然に結びついていました。その点で、彼らは理想や目標がしっかりとあって、とても頼もしく、こんな若い人たちが、将来福祉の分野で活躍してくれると思うと嬉しかったのです。
けれど、ケア・ワーカーさんがそんな人たちばかりなら、「8割」という数字にはならなかったのでは。
もちろん、我が儘で意地悪で気難しい高齢者や、非常識な家族もいるとは思います。でも、8割が「ケアハラ」をしているとは考えにくい。
規定外のことをさせられることがすべて「ケアハラ」と感じるケア・ワーカー、恐いです。マニュアルを作成している企業はもっと恐い。
私のイメージは、ケア・ワーカーさんが来るのを心待ちにして、「ありがとう」という感謝の気持ちで介護を受けるお年寄りの姿です。これって、今どき、幻想でしょうか? 少なくとも、私が高齢になって、介護を受ける立場になったら、心を通わせられない相手に、着替えや食事やトイレを介助して貰うなんて、考えられないのですが。
「介護」「看護」とは、専門的な知識や技術が必要なのは当然ですが、メンタルな部分に対してというのが、半分以上を占めるのではないかと私は思うのですが…。知識と技術だけをもって、きっちりマニュアルの範囲で介護、看護に従事する人材が今後増え続けるのではないか。誰も口に出さなくとも、介護認定を受けた高齢者は、社会での役割を終えて、命を終えるまで非生産的な、無駄な時間を過ごす者として、暗黙のうちに位置付けられていくのではないか…という、うすら寒い思いがしました。
少子高齢社会を効率良くまわしていくには、社会の役割を終えた人間に、優秀なケア・ワーカーをつけることも無駄…?
じゃあ、どうすればいいんだい?
…
以前読んだ小説の中で、「人は、子供を育て、働いて収入を得、親を介護して見送る。この三拍子が揃って真っ当なのだ」というようなことを、ある高齢者施設だか病院だかの院長?(だったとおもう)が語る場面がありました。
働いて高収入を得ている部分だけで人を評価できないというような意味あいも含めて。また、この三拍子とはひとりの人間だけでなく、「人間というもの」延いては社会のあるべき姿を語っているのでした、これはとてもとても心に響きました。
「じゃあ、どうすればいいんだい?」
いつも、そうやって、ひとつひとつ自分の中で、少しでも前向きな答えを捜しながら過ごしていきたいと思います。
この本を読んだのは6年前。郷里に帰ることに気持ちが向かったことには、この言葉の影響はとても大きかったのです。
ケア・ワーカーさんを否定するつもりは全くありません。こんな社会のなかでも、できるだけ「心ある」介護従事者が育ってくれることを、もちろん願っているけど、私にできることはなんなんだ? そんな中で自分を中心に周囲の人との関係を考えたとき、両親がいて、Takがいて、親族もいて、その絆を感じながらやがては自分も介護にかかわり、親を見送り、自分も老いていく、それをTakに見せることは尊い…と感じました。
それから、私は老いても歌うつもり。これも
「じゃあ、どうすればいいんだい?」の、自分の中での答えのひとつです。
続きはこちら
帰省している折、地方紙で、介護従事者に対するアンケート調査を行ったところ、「ケア・ハラスメント」なるものを受けたことがあると答えた人が8割(すみません、正確に覚えてません)程度もいるという記事が載っていました。その内容は、セクハラのようなことから、「規定外のことを頼まれる」など多岐にわたっているようでした。流し読みしてしまい、あとでゆっくり読もうと思って、そのままにしてしまったので、詳しい内容はわかりません。でも殆どのケア・ワーカーが「ケア・ハラスメント」を経験しているということと、その内容が、なんだか「えっ」と、心にひっかかったのでした。
そういえば、以前「セクハラ」という言葉が一般化し始めた頃、女性社員の8割以上が「セクハラ」を経験したことがあるという調査もあったっけな。いや、9割りだったかな?
今回の「ケアハラ」調査、健全な大人同士の職場間ということが前提でのセクハラ問題とはちょっと違うのでは。介護をする人、される人、ということでお互いのポジションがまず違います。
たくさんの企業がこぞって介護業界にも参入して、介護産業はいきなり賑わって、整備が遅れている感じがあります。
私は、この記事を読んだとき、「そりゃー、ケア・ワーカーの資質の問題では?」とまず思いましたが、いかがでしょうか。極端にいえば、マニュアルだけをインプットされた従事者が大量に排出されているのでは…、、、
以前、音楽を通して、福祉大の学生の人たちとお友達になりました。
彼らは、それぞれ考えるところや、志があって、この大学を選んだと言っていました。家族に障碍のある人がいて、日常の中で自然にいろいろ考えたり、子供の頃の経験したことや、将来の夢などと、今大学で学んでいることが自然に結びついていました。その点で、彼らは理想や目標がしっかりとあって、とても頼もしく、こんな若い人たちが、将来福祉の分野で活躍してくれると思うと嬉しかったのです。
けれど、ケア・ワーカーさんがそんな人たちばかりなら、「8割」という数字にはならなかったのでは。
もちろん、我が儘で意地悪で気難しい高齢者や、非常識な家族もいるとは思います。でも、8割が「ケアハラ」をしているとは考えにくい。
規定外のことをさせられることがすべて「ケアハラ」と感じるケア・ワーカー、恐いです。マニュアルを作成している企業はもっと恐い。
私のイメージは、ケア・ワーカーさんが来るのを心待ちにして、「ありがとう」という感謝の気持ちで介護を受けるお年寄りの姿です。これって、今どき、幻想でしょうか? 少なくとも、私が高齢になって、介護を受ける立場になったら、心を通わせられない相手に、着替えや食事やトイレを介助して貰うなんて、考えられないのですが。
「介護」「看護」とは、専門的な知識や技術が必要なのは当然ですが、メンタルな部分に対してというのが、半分以上を占めるのではないかと私は思うのですが…。知識と技術だけをもって、きっちりマニュアルの範囲で介護、看護に従事する人材が今後増え続けるのではないか。誰も口に出さなくとも、介護認定を受けた高齢者は、社会での役割を終えて、命を終えるまで非生産的な、無駄な時間を過ごす者として、暗黙のうちに位置付けられていくのではないか…という、うすら寒い思いがしました。
少子高齢社会を効率良くまわしていくには、社会の役割を終えた人間に、優秀なケア・ワーカーをつけることも無駄…?
じゃあ、どうすればいいんだい?
…
以前読んだ小説の中で、「人は、子供を育て、働いて収入を得、親を介護して見送る。この三拍子が揃って真っ当なのだ」というようなことを、ある高齢者施設だか病院だかの院長?(だったとおもう)が語る場面がありました。
働いて高収入を得ている部分だけで人を評価できないというような意味あいも含めて。また、この三拍子とはひとりの人間だけでなく、「人間というもの」延いては社会のあるべき姿を語っているのでした、これはとてもとても心に響きました。
「じゃあ、どうすればいいんだい?」
いつも、そうやって、ひとつひとつ自分の中で、少しでも前向きな答えを捜しながら過ごしていきたいと思います。
この本を読んだのは6年前。郷里に帰ることに気持ちが向かったことには、この言葉の影響はとても大きかったのです。
ケア・ワーカーさんを否定するつもりは全くありません。こんな社会のなかでも、できるだけ「心ある」介護従事者が育ってくれることを、もちろん願っているけど、私にできることはなんなんだ? そんな中で自分を中心に周囲の人との関係を考えたとき、両親がいて、Takがいて、親族もいて、その絆を感じながらやがては自分も介護にかかわり、親を見送り、自分も老いていく、それをTakに見せることは尊い…と感じました。
それから、私は老いても歌うつもり。これも
「じゃあ、どうすればいいんだい?」の、自分の中での答えのひとつです。
続きはこちら