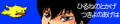さて、話はまた、感受性のかけらもないと言い放つHIROくんママにいったん戻ります。
彼女は、一昨年、フラミンゴで子供のクリスマスコンサートを催したとき、急遽「チケットもぎり」をお願いしなきゃならない羽目になって、「もぎり」どころじゃなく、当日のマネージメント全般を、ものすごく頼もしく引き受けて下さいました。
チケットの釣銭用の大量の両替や、受付で小銭を並べるケースや、私には全く思い至らないような「経理系」の冴え渡る頭脳を、ここぞとばかりに発揮して下さり、ホントに、彼女がいてくれればこそ…いや、いなかったらいったいどんなことになっていたんだろう…( ̄_ ̄|||)
フラミンゴや、その周辺の協力して下さった人たちには、彼女のような経理系頭脳の持ち主は誰もいなかったのです。
HIROくんママは、フラミンゴのコンサートに、ふっか~く参画してくれたのでした。
HIROくん親子には、プールや、イベントや、いろんなところにお誘いいただいて、ものぐさTAKAMI&Tak親子は、ものすごく充実した府中時代を過ごすことができました。
音楽は、そんな私の生活の中で、私達とともにあるもの…だったと思う。ここからここまでが、音楽…と、区切ることができないもの。「演じ手」と「受け手」の境界線も必要がない、「生活とともにある音楽」とは、そういうものだという気がしています。
音楽には「つくり手」「演じ手」と「受け手」がいて、さらに「担い手」(スタッフ…といえばわかり易いんだけど、、、なんか違う)がいる。
実はこの三者っていうのは同じ時間を共有してる…っていうより、一緒になって時間を紡いでいるのではないかと思う。それぞれの感受性で。
「演じ手」の私も、その時その場で、「受け手」になっていたりする。
フラミンゴのLIVEやコンサートも、フラミンゴ美人ユニット「風の鈴」のボランティア活動も、HIROくんママの発表会参加や、卒園の謝恩会の演奏も、ピアノの生徒のご父兄からのイベントの依頼も、全部、私にとっては1本の太い流れだし、その時間って、そこにいる人たち全員で紡いでいる時間だった。
私が求めているもの、大切に思っていることは、その時間のうねりの中での「呼応」なんだと思う。
私はうたを創って歌います。でも、その課程で、産みの苦しみや独りの練習や、いろんなところを通過するけれど、いちばん大事なのは、人に投げかけて受け取ってもらう、その瞬間なのだと思う。
そこに「創り手」と「受け手」の境界線ってあるのだろうか?
大学時代の「音楽鑑賞論」の講義で、「作曲家の譜面(神からの啓示)」「演奏者の出す音」「聴衆」このうちの、どこに「音楽」があるのか、「解釈」とはなにか…などという問題を、1年間かけて、いろんな学者の学説を学ぶ…ってのをやりました。
(おもしろいことに、この学説ってのも、時代とともに変遷していくのです)
こんなことを真剣に考えて時間を費やす哲学者がいるんだなあ…などと、その時には思いながら、一応レポートも書かなきゃいけないので、自分なりにもアタマを沸騰させて考えてみたものでしたが、私が今書いてることってのは、正にそれに繋がるのかも。
音楽とは、単なる伝達の媒体。
「おもい」を伝える媒体なんだけど、100の「歓び」を表現した創り手に対して、受け手のなかで、10の歓びと90の「孤独」に還元されてしまった…としても、総量100の伝達は完了、成功。
私は、モーパッサン「女の一生」のある場面をモティーフに「ムーンライトワルツ」をつくりました。この本の内容は全く憶えていません。思春期に読んだ本なんて、殆どそんなもんなのですが。(なんだか全部がゲル状になって集まって、生きてはいるけど、底のほうで、目立たないように眠っている感じ。)
物語のテーマとはあまり深くかかわりのない、なにげない情景描写の美しさを、何十年も記憶の底で眠らせておいて、それが全く違ったかたちで自分の表現に生かされる。
私は「女の一生」をうけとめて、作者の意図するところ?とは全く関係のないところに反応してしまったワケなのですが、これもアリだと思います。こんなことからも私は、「音楽と、音楽でないものの境目」も、「創り手と受け手の境目」もどうでもいい、生活とともにある音楽を続けていきたい…というような思いが強くなっていったんじゃないだろうか、、、
うーん、書いてることが飛躍しているのはわかってるけど、どーやってまとめたらいいんだい…???
「それぞれの感受性」ということで考えはじめましたが、日々の暮らしの中で、なにかを「感じる」こと、「受け取る」こと、それは誰でも当たり前にしていることだと思います。逆に、あまり受け取りたくないところには蓋もしている。蓋の使い分けも任意にできる。
感じたり受け取ったりしたことは、そのまま、ときにはかたちを変えて、表現したり伝えたりする。暫く寝かせたりもする。
部屋が汚れていたら、掃除機をかけたり、子供に片付けなさいと命令する。
創作活動やその他で崖っぷちのときには、「散らかってる」を感じる心には蓋をする、または寝かせておく…ってなもんです。
お友達の家に遊びにいったら、とっても美味しい料理をご馳走になったので、作り方を聞いて帰って、自分でつくって家族にも食べさせる…とかね。
幸せに豊かに暮らすということは、この「感じる」「うけとる」「あらわす」「つたえる」などの循環が自然にスムースにできるってことじゃないでしょうか。健康な体を血がさらさらと流れるのと同じように。
この長い文章は、未完で終わりにしようとおもいます。
ここから先は、また自分の「暮らし」の中から紡ぎつづけていくしかないです(*^_^*)