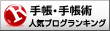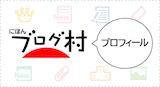(↑40年ほど前にUrsulaからもらった焼きリンゴの陶器)
ドイツの Ursulaから新年になってメールが届きました。
彼女らしい長いメールで、
クリスマスカード、クリスマスプレゼントのお礼が丁寧に書かれていたり(萩焼のカップはとても嬉しかったようです〜。良かった!)、
ご家族の様子、
ドイツのコロナ事情(フランスに比べてドイツの感染者数が少ないのは、PCR検査を抑えているからじゃないかと不審がってました。彼女たちはワクチン接種3回目をすでに12月に受けたそうです)、
老後のことなど、
結構読み応えのある内容でした。
その中には、前にわたしが記事に書いた内容についての返信も含まれていました。
実はわたし、
年末にはカードだけでなくメールも送ったんです。
下に貼り付けている記事にも書きましたように、
丁寧に連絡を取ろうと決めましたからね。
その際に40年前にもらった焼きリンゴ用の陶器のことや、
ドイツ旅行で出会った時の話なども写真付きで書きました。
そして今回の彼女のメール。
部分的に少しアップしますと・・・。
・・・・・・・・・
And also thank you very, very much for heart-warming e-mail! I was really deeply moved by everything that you wrote about our long-existing friendship! And I felt my tears coming when I saw the pictures of your visit in Frankfurt (that was long before our sons were born!) and of the baked apple dish (about 40 years ago!). Incredible that you have kept the dish ever since in spite of your removals! 40 years that is about two thirds of our respective lives!That was before I started my first job as an urban planner and probably even before I went to university! I think that I was 15 or 16 when we began our pen-friendship. I'll look it up one day - I have kept all your letters, they are in one of the boxes in our cellar. Unfortunately our cellar is full of boxes (mostly filled with things that my husband or I inherited) but the box with your letters is there for sure!
It is something very, very special to have such a good friend for so many decades! Besides three friends from school you are my eldest friend! Thank you for keeping in touch with me despite all the ups and downs of life!!! More than forty years - that's a long, long time. Just think of all that has happened in all those years, in our private lives as well as in the world in general. When we started our pen-friendship, the PC didn't even exist - we used pen and paper. Writing a letter by hand with a pen on a sheet of paper is something that the generation of our sons can hardly imagine! And I still prefer a hand-written letter to an e-mail but I must admit that my hand-writing is just terrible nowadays due to the lack of training! So I'm writing these very personal sentences to you on my computer (what a pity)...
・・・・・・・・・
ドイツ旅行や焼きリンゴの陶器の写真を見て涙が出たこと、
40年ほど前の彼女からのプレゼントを
わたしがずっと持ち回っていたことへの驚き、
おそらく15,6歳からこの文通が始まったこと、
わたしからの手紙を一つのボックスに入れてまだ保管していること(超はずかしい!)、
わたしは彼女のeldest friendだということ、
人生のいい時も悪い時も繋がって来れたことへの感謝などなどが書かれていて、
わたし自身も読みながらドバドバと涙が出てきました。
全く同じ思いで繋がって来れたということ、
またこの奇跡的とも思える関係が、
今も続いていることへの感謝が再び湧き上がってきたのです。
彼女のメール、
後半は今後のことが書かれていて、
「とにかく完璧に健康でいましょう」と締め括られ、
そしてそして、
最後の最後には、
also hope that one day we will be able to celebrate our 70th pen-friendship anniversary as old, wise women in the middle of our families!
すごすぎません〜〜??
すごすぎません〜〜??
50thではなく、70th??
彼女のその強烈な言葉に背中を押されたまんじゅう顔、
「そろそろ終活」と自分の人生をまとめ始めてたことが恥ずかしくなりました。
まずはこれからの10年を大事に、
そして、
彼女との関係もさらに大事にして歩んでいきたいと
もう一度年頭に誓いました。
↓二つのランキングに参加しています。
それぞれポチッと押して応援してくださると嬉しいです。
励みになります。