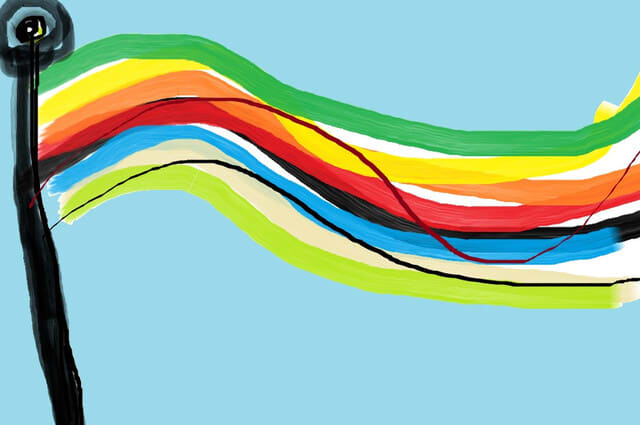
江戸時代には老牛馬を屠殺委棄するの無慈悲なる行為を禁じたが為に(奈良奉行の触書にこの禁制見ゆ。他の地方でもそうであったらしい)老牛馬は通例飼養者の飼い殺しとなっていたが、斃死の後は必ず捨場に委棄するか、しからずばエタに通告してその処理に委せねばならなかった。武蔵八王子在の百姓がかつて自らこれを処理したが為に、エタ頭弾左衛門より抗議を提出して、為に面倒な悶着を惹き起した事件もあった。
――喜田貞吉「牛捨場馬捨場」
牛や馬と一緒にくらしてないと我々は素朴さなんかを欠落させてしまうかもしれない。「素朴」は文学でもいろいろと肯定的に論じられてきたわけだが、そういう精神は――がんばっても見直すためのものではなく、我々が馬や牛に触って馬や牛になった結果が「素朴」なのだ。
ドジャース大谷。眼が悪い愚民たちよ、ドラゴンズ大谷だよ。――ある種の素朴さはこういうものは許容する。
象徴派だって素朴なのだ。牛の死体や妊婦の姿態に対しても、我々は素朴になる。小林秀雄がボードレールに感じたのもそんな感じだから、「夢を懐疑的に」と言ってしまうのだ。実際は、懐疑的な夢であったに違いない。
昨日はダヌンチオの「死の勝利」とか「トリスタンとイゾルデ」などの反動的授業をおこなった。今回は、「トリスタン」の愛の二重唱についての解説動画を使ったが、案外学生がまどろみの中から覚醒した。もっとも、共通科目などで学生が覚醒するのはこれである↓
ヒトラー生誕記念前夜祭の第九 指揮フルトヴェングラー (日本語翻訳付き) 映像:1942年4月19日、 演奏音声:同年3月22~24日ライブ
こういう動画を参考にしてみりゃ、研究インテグリティなんかどうでもいい話だ。そもそも国文学なみに外国にとってワケワカメになれば全然気合いを入れなくても遂行できるし、自国がナチスなみに発狂していてはどうしようもない。ベートーベンはそんな環境でも高らかに鳴り響く。言うまでもなく、ベートーベンは特殊な文化の中にあったのである。









