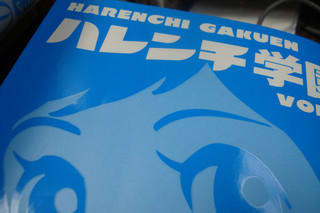https://blog.goo.ne.jp/mimasaka_chiko/e/f85b557ea1143493a8f762ff911abfb4
妹の例の会
望月理子氏の『日本文学』所載の論文を読んだから、「猫の事務所」を読み直してみたが、昔読んだときと同じく、いやな話であった。結末部、「僕は半分獅子に同感です」と話者は言うが、何が「半分」なのであろう?「半分」などというてすむ話かにゃん
しかし、ある種の教育分野の論文を読むと、この「半分同感です」みたいな論旨が多く、なぜその先に行かないのか合点がいかないことが多い。もっとも、これは時間的な問題かもしれない。先生方は、その先に行く時間的余裕がないのだ。
大学時代、研究会の先輩だった人がよく『日本文学』に書いているので、時々読むのだが、――教育現場で「その先」に行こうとするとすごく精神的に追い詰められることがよくわかる。実際、その「半分」という認識が何を生むかというと、人間に対する認識が明確になるのではなく、二つに、割れる――つまり、問題がもうひとつ増えるということを意味するのである。クラスに三〇人生徒がいるとすると、だいたい六〇人ぐらいの雰囲気だ。複数のグループがアメーバみたいに移動しているから、それを考慮してまた「半分、同感」みたいな考え方をしてみると、だいたい一二〇人ぐらいに増える。先生方はこれにはおそらく耐えられないし、実際に耐えてもいないのが現状であろうと思う。その「半分」という認識形式が間違っているのである。
芥川龍之介の「鼻」のネタになった「池の尾の禅珍内供の鼻の語」(『今昔物語集』)は、内供の鼻を棒で支えていた童が、つい鼻を汁のなかに落っことしてしまい、「お前は、あたまがおかしいのかっ」と激怒した内供が
「我にあらぬやむごとなき人の御鼻をももたげむには、かくやせむとする。」
と言ったところ、童は陰で
「世にかかる鼻つきある人のおはさばこそは、外にては鼻ももたげめ。をこの事仰せらるる御坊かな。」
と云った。語り手は、
「此れを思ふに、まことにいかなりける鼻にかありけむ。いとあさましかりける鼻なり。童のいとをかしく云ひたる事をぞ、聞く人讃めけるとなむ語り伝へたるとや。」
と話を締めるのであった。思うに、話者がわざわざ「まことにいかなりける鼻にかありけむ」とか言っているのは何なのであろう。この童の発言は、本当にそんなに「をかし」いものであろうか。だいたい内供の鼻がどんなであったかは、ここまでの話でクワシク描写してるのでよみゃわかる。むしろ話者は、「世にかかる鼻つきある人」、実際は「やむごとなき人の御鼻をももたげむ」様を想起させたかったのではなかろうか。この童の話で盛り上がったど大衆が何で盛り上がっていたのかを書いていないのは卑怯なり。実際、この話を学校で読ませてみりゃ、自分の鼻に筆箱や消しゴムをくっつけて遊ぶ輩がタケノコのように生える(知らんけど)
考えてみると、内供はたぶん何か病気だったに違いないのだ。まったくかわいそうである。それをまた「半分同感」であるみたいな態度をとった芥川も大概であった。童にこびたふりをする今昔の話者もいやなやつである。